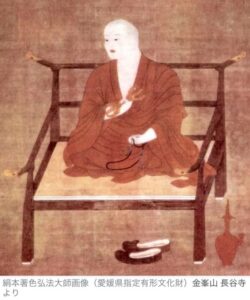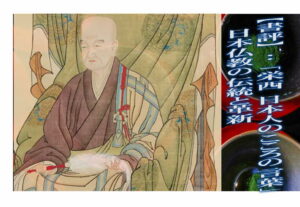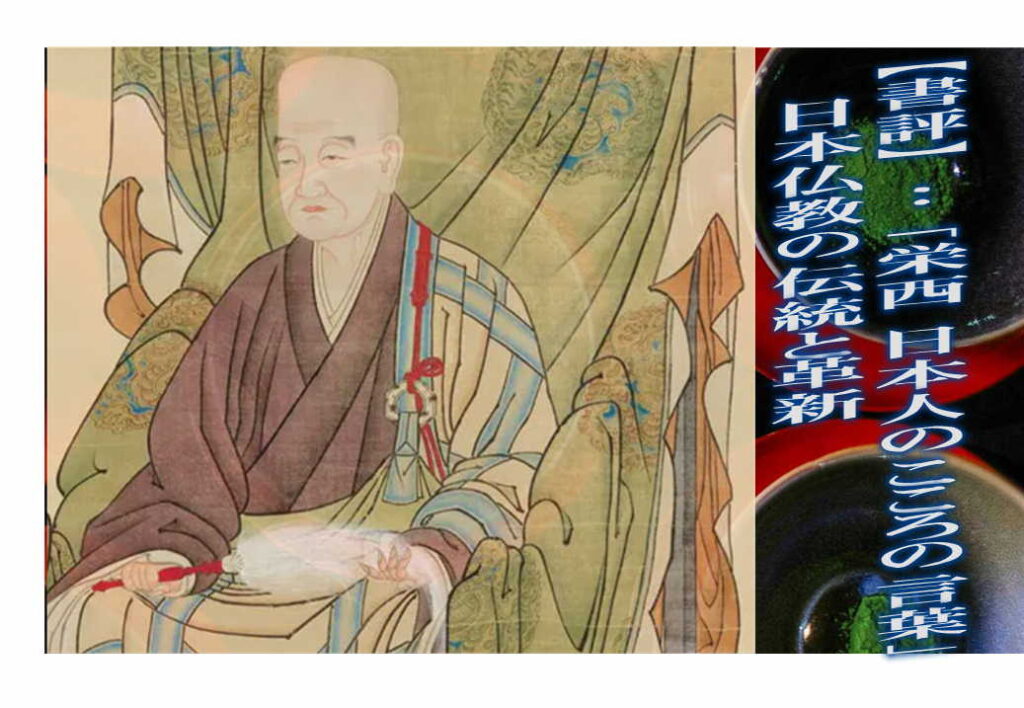
日本仏教の歴史において、鎌倉時代に活躍した栄西(1141-1215)は伝統を受け継ぎながら新しい風を吹き込んだ重要な宗教者である。
臨済宗の祖として知られる栄西は、禅の普及、厳格な戒律の重視、茶の効能の紹介など多方面にわたる活動を通じて、日本の宗教・文化に大きな影響を与えた。
本書は、栄西の思想と活動を多角的に検討し、日本仏教史における彼の位置づけを明らかにする試みをしている。
著者紹介
中尾良信(なかお・りょうしん)
1952年兵庫県生まれ。
駒澤大学仏教学部卒業、同大学院博士後期課程満期退学。
曹洞宗宗学研究所を経て、現在は花園大学文学部仏教学科教授。
専門は日本中世禅宗史で、栄西をテーマにした研究を長年続けている。
著書に『日本禅宗の伝説と歴史』『図解雑学 禅』などがあり、日本仏教史の解説者として高い評価を得ている。
瀧瀬尚純(たきせ・しょうじゅん)
1975年大阪府生まれ。
花園大学文学部仏教学科卒業後、同大学院博士課程単位取得満期退学。
現在は花園大学国際禅学研究所研究員、東洋大学東洋学研究所客員研究員。
臨済宗の僧侶として実践的な修行経験を持ち、禅の思想や文化に関する研究を進めている。本書では『興禅護国論』や『喫茶養生記』の解説を担当し、実践と学術の両面から栄西の思想を掘り下げている。
伝統との連続性:比叡山と禅の関係
栄西は鎌倉時代に活躍した僧侶であるが、単純に「鎌倉新仏教」の祖師として彼を位置づけることには再考の余地がある。
栄西自身が強調していたのは、自らの活動は比叡山の伝統的な教えからの断絶ではなく、むしろ最澄が中国から持ち帰った禅の教えを「復興」させることであった。
「日本国は天平中、唐の道琳が大安寺にあって、禅宗をもって、行表和尚に授くと。
(中略)その後、今までに四百年に及べるなり」
栄西は「日本における禅の伝統が奈良時代にまで遡り、最澄の時代にも受け継がれていた」と主張している。
彼は『内証仏法相承血脈譜』を引用し、比叡山に最澄以来の禅の伝統が脈々と四百年間受け継がれてきたことを強強調する。
栄西が禅を広めようとした活動は、彼の視点では全く新しい教えを導入することではなく、日本仏教の伝統を復活させるという意義を持っていた。
栄西は十四歳で比叡山に登り出家し、天台密教の研鑽に励んだ。
しかし、二度の入宋(中国渡航)を経て、特に二度目の入宋(1187年)で禅僧の虚庵懐敞のもとに参じ、印可(悟りの証明)を受けて帰国した。
この経験が栄西の禅に対する理解を深め、比叡山に存在していた禅の伝統を復興させようという使命感を強めたと考えられる。
禅の教えと栄西の理解
栄西が伝えた禅の核心は「即心是仏」(この心そのものが仏である)という教えである。
彼は『興禅護国論』の冒頭で「大いなる哉、心や」と述べ、心の偉大さを賞賛している。
「心とは何と大きな存在なのでしょうか」
栄西の理解では、この「心」とは釈尊の悟り、あるいはその教えを端的に指すものであり、「仏心」「仏性」「自性清浄心」とも定義される。
すべての人が本来的には仏と同じ存在であり、その本性に気づくことが禅の目的だという理解である。
また栄西は禅の伝統的な教えである「不立文字」「教外別伝」「見性成仏」を重視した。
彼は『興禅護国論』で以下のように述べている。
「禅の祖である達磨大師は、文字によらず(不立文字)、直に人びとのもつ仏心を指し示し(心指人心)、その本性を見せしめて仏と成らしめた(見性成仏)。
これを「禅の法門」といいます」
しかし、栄西は文字や経典を否定していたわけではなく、「釈尊の説かれたすべての経典が拠り所」であると述べている。
彼が批判したのは、経典の文字に執着して本来の意味を見失うことであって、経典そのものを軽視していたわけではない。
「釈尊が説かれた諸々の経典には、かりそめに設けられた教えと真実そのものの教えがありますが、それらすべては、一切衆生に、二つとない釈尊の悟りを保持させるためのものです。真理を得るための道具や手段にたとえられるすぐれた方便として設けられたものなのです」
栄西は経典を「筌蹄の善巧方便」(魚を捕るカゴや兎を捕るワナのような優れた方便)と位置づけ、真理に至るための手段として重視していた。
戒律重視の姿勢:「持律第一」としての栄西
栄西は「持律第一」と称されるほど、戒律の厳守を重視した僧侶であった。
彼の著作『出家大綱』は、出家者の心得と戒律の重要性を説いたものである。
彼は禅の修行と戒律の遵守を不可分のものとして捉えていた。
「わが禅宗は、戒を護ることから始め、禅を修めることを最も大切な教えとしています」
栄西が戒律を重視した背景には、当時の比叡山における破戒の現状への批判があった。
彼は比叡山で「持律第一葉上房」と呼ばれるほど戒律に厳格であったが、晩年には比叡山や南都(奈良)の仏教の堕落を嘆き、戒律の復興を訴えていた。
栄西は大乗戒だけでなく小乗の戒律も重視すべきだと主張した。
彼は比叡山で受けた大乗戒のみでは足りず、より具体的な小乗の戒律も学ぶべきだと考えた。
「まだ修行を完成していないのに、小乗の境地に退いてしまったならば、それは(大乗の)菩薩の死です。だから考え方ではなく、具体的な規定だけを取り入れるのです」
栄西は、出家者の生活全般にわたる戒律―食事、衣服、歯磨きなど―を細かく定め、それを守ることで内面の菩薩心が保たれると説いた。
特に「少欲知足」(欲を少なくして足ることを知る)の精神を重視し、食事の節制や時間外に食事をしないこと(非時食の禁止)なども強調した。
さらに、栄西は共生の精神を重視し、食事を三等分して仏・法・僧の三宝、貧しい人や鳥獣、そして自分自身のために分かち合うことも説いた。
これは出家者の持つべき慈悲の精神を具体的に示すものであった。
喫茶の普及と養生思想
栄西は「茶祖」とも称され、日本における喫茶文化の普及に大きく貢献した。
彼は二度目の入宋で茶の効能を学び、帰国後に『喫茶養生記』を著して茶の身体的・精神的効用を説いた。
「「茶」とは、我(われ)を心身健やかならしめる仙薬(不老不死の仙人になる薬)であって、その茶を飲むことは、我の寿命を延ばしてくれるすぐれた手段です」
と述べている。
栄西は茶が特に心臓に良い効能をもたらすと考えていた。
彼は五臓(肝・心・脾・肺・腎)と五味(酸・苦・甘・辛・塩)の対応関係に基づき、心臓は苦味を好むため、苦味を持つ茶が心臓を健康にすると説いた。
「心臓を健康に保つ方法としては、茶を飲むことが一番です。心臓が弱まってしまうと、五臓のすべてが病を生ずることになってしまいます」
また、栄西は茶が睡眠を抑制する効果があることも指摘している。
彼は修行者にとって過剰な睡眠は煩悩であり、茶を飲むことでこの煩悩を抑制できると考えていた。
これは禅の修行と喫茶を結びつける重要な視点であった。
歴史的には、栄西が鎌倉幕府の第三代将軍・源実朝に茶を献上したというエピソードも知られている。
『吾妻鏡』によれば、実朝が二日酔いで体調を崩した際、栄西が茶を献上して回復させ、同時に『喫茶養生記』も献上したという。
栄西は茶の効能を日本人に広めるだけでなく、茶樹を脊振山系(福岡県と佐賀県の県境)に植えたとも伝えられており、栽培方法や製法についても詳しく記している。
彼は茶の摘み取り、精製、保存の方法まで具体的に説明し、日本における茶の普及に努めた。
朝廷・幕府との関係:社会的活動
栄西の活動は宗教的な側面だけでなく、政治的・社会的な側面も持っていた。
彼は『興禅護国論』という書名にあるように、禅が国家を守る教えであることを強調し、天皇や朝廷の支持を得ようとした。
「およそ、天子こそ禅の教えに率先して帰依すべきではないかと思います。そうであれば、禅宗を興すことが、天子の御耳に入って驚かせたとしても、失礼にあたりましょうか」
栄西は朝廷から「伝燈法師」の位を授かっていたことを誇りとし、それを根拠に禅宗の独立を求めた。
彼は『日本仏法中興願文』で以下のように述べている。
「できれば(天子の近くにいる)廷臣や公卿は、私のこの願文に込めた志を受け止め、天子にも奏聞することによって「中興」の思し召しがめぐらされ、仏陀の教えと王法(天皇の統治)がともに回復されれば、もっとも望むところです」
一方、栄西は鎌倉幕府とも深い関わりを持っていた。
また、源頼朝の一周忌法要の導師を務め、二代将軍頼家の支援で京都に建仁寺を開創した。
三代将軍実朝とも親交があり、茶を献上するなどの交流があったとされる。
しかし栄西は、単に権力者に迎合したわけではなく、仏教の復興のために彼らの支援を得ようとしていたと考えられる。彼は東大寺の復興(東大寺大勧進職)なども担い、日本仏教の中興に尽力した。
修行者としての理想像:菩薩の道
栄西は禅の修行者の理想像として、「菩薩」の道を説いた。
菩薩とは自らが悟るだけでなく、他者の救済にも尽力する修行者である。
「もし求道者がいて、禅を修行しようとしたならば、「般若」という仏智そのものを学ぶ菩薩でなければなりません。
大慈悲心を起こし、弘誓願を発して、もっぱら禅定を修め、菩薩が守る清らかな戒をそなえ、あまねく衆生を救わんとして、自分ひとりだけ迷いからの脱却(解脱)を求めてはなりません」
栄西は「四弘誓願」(衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成)を重視し、自己の修行と衆生救済の両輪が禅の実践において不可欠だと考えていた。
この姿勢は、彼の著作や活動全般に一貫していた。
また、栄西は「応病与薬」(病に応じて薬を与える)という教えも重視した。
これは相手の状態や能力に応じて適切な教えを説くという仏教の伝統的な方法である。
「すぐれた禅僧の尊宿は、病に応じて薬を与えるような教化の手段を駆使します。薬を一服飲ませるだけで効果があらわれる者もいれば、逆に、さまざまな薬を調合したり、針や灸を施してようやく効果があらわれる者もいます」
栄西はこの教えを通じて、人々を導く方法の多様性と柔軟性を認めつつ、最終的には「自ら仏性に気づく」という同じ目的に向かわせることの重要性を説いた。
「四弘誓願」
「四弘誓願」は仏教の修行者が立てる4つの誓いで、菩薩の精神を表しています。
- 衆生無辺誓願度(すべての人々を救う):世の中の苦しむ人々を助けることを誓います。
- 煩悩無尽誓願断(尽きない煩悩を断つ):自分の欲や怒りなどの煩悩を克服することを目指します。
- 法門無量誓願学(無限にある教えを学ぶ):仏教の教えを広く深く学び続けることを誓います。
- 仏道無上誓願成(悟りへの道を完成させる):最高の悟りを目指して修行を続けます。
これは、自分だけでなく他者も救いながら、心を磨き、仏教の真理に近づくための大切な指針です。
1. 衆生無辺誓願度(すべての人々を救う)
この誓いは、「苦しんでいるすべての人々を救いたい」という思いを表しています。
仏教では、人々が抱える苦しみ(病気、貧困、孤独など)は無限にあると考えますが、それでも一人ひとりに寄り添い、助ける努力を続けることが大切だと説きます。
これは「他者への思いやり」を実践する誓いであり、自分の利益だけでなく、周囲の人々の幸せを願う菩薩の精神を象徴しています。
2. 煩悩無尽誓願断(尽きない煩悩を断つ)
「煩悩」とは、人間が持つ欲望や怒り、嫉妬、不安など、心を乱す感情や執着のことです。
この誓いは、それらの煩悩がどれだけ多くても、それを克服していこうという決意を示しています。
煩悩は完全に消えることは難しいですが、それに振り回されず、自分自身を見つめ直し、心の平穏を保つ努力を続けることが大切だと教えています。
3. 法門無量誓願学(無限にある教えを学ぶ)
仏教には数え切れないほど多くの教えがあります。
この誓いは、それらすべてを学び続けようという姿勢を表しています。
ただし、単に知識として学ぶだけではなく、日常生活で実践することが重要です。
仏教の教えは、人々の苦しみを和らげたり、自分自身の成長につながるものです。
この誓いは「学び続ける心」を忘れないことの大切さを教えています。
4. 仏道無上誓願成(悟りへの道を完成させる)
仏教では「悟り」とは、自分自身や世界の真理を深く理解することです。
この誓いは、その悟りへの道がどれほど遠くても、諦めずに歩み続ける決意を表しています。
悟りに到達することで、自分自身だけでなく他者も救える存在になれるとされています。
この誓いは、「自分自身の成長」と「他者への貢献」を両立させる目標として重要な意味を持っています。
結論:伝統と革新の架け橋
栄西の思想と活動を通じて見えてくるのは、伝統と革新の両立を図った宗教者の姿である。
彼は比叡山の伝統を重視しながらも、中国から新たに学んだ禅の教えを日本に広め、また喫茶文化という新しい習慣も導入した。
栄西の禅は単なる坐禅修行ではなく、戒律の厳守、菩薩としての利他行、心身の養生など、多面的な修行体系であった。
それは鎌倉時代の仏教刷新の流れの中で、伝統的な日本仏教の価値を保ちつつ、新しい要素を加えることで仏教の再活性化を目指すものであった。
栄西の活動と思想は、単なる宗派の開祖としてだけでなく、日本仏教の大きな転換点において、伝統と革新をつなぐ架け橋としての役割を果たしたと評価できる。
彼の残した多くの著作と、彼が築いた寺院や伝えた文化は、日本の宗教史・文化史において今なお重要な位置を占めている。
この本の評価
ネット上の評価
ネット上では、本書は「栄西の思想や生涯を平易に解説した良書」として評価されています。
特に、禅と茶文化に関する栄西の功績を具体的に掘り下げている点が好評です
。一方で、専門的な用語や内容が多く、初心者にはやや難解との意見も見られます。総合的には星4.0/5.0といった印象です。
筆者の評価
本書は、栄西の思想や活動を多角的に解説し、彼の歴史的意義を深く掘り下げています。
特に『興禅護国論』や『喫茶養生記』の背景を丁寧に解説し、現代にも通じる教訓を示している点が秀逸です。
また、著者二人の専門的な視点と実践的な解釈が融合しており、学術性と読みやすさを両立しています。
筆者としては星4.5/5.0と評価します。