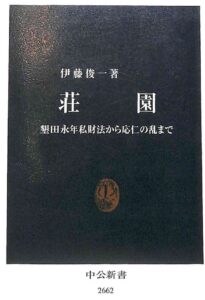歴史の教科書でおなじみの「大化の改新」。
「乙巳の変(いっしのへん)」とか「公地公民制」という言葉だけは覚えているけど、実際何だったの?
という人も多いのでは?
実は、この改革が日本の国のかたちを根本から変えた超大事件だったんです!
今から約1400年前、645年に始まったこの政治改革は、豪族たちが牛耳っていた日本を、天皇中心の国へと大変身させました。
最近の研究では、教科書の定説とは違う見方も出てきているんですよ。
古代史ミステリーとも言える「大化の改新」の真実に迫ってみましょう!
《このブログの概要》
- 大化の改新は飛鳥時代の645年に起きた画期的な政治改革
- 皇極天皇4年(645年)6月12日の「乙巳の変」(蘇我入鹿暗殺)から始まる
- 中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足(後の藤原鎌足)が中心となって推進
- 豪族中心の政治から天皇中心の中央集権国家への転換
- 日本初の元号「大化」がこの時に定められた
- 大化2年(646年)1月に「改新の詔」が出され、政策が表明された
- 主な改革内容:
- 公地公民制:土地と人民をすべて国家の支配下に置く
- 国郡制度:地方行政区画の整備と国司・郡司の設置
- 班田収授法:戸籍・計帳の作成
- 租庸調:新しい税制の導入
- 狭義には大化年間(645〜650年)の改革、広義には大宝律令完成(701年)までの約60年間の改革を指す
- 研究史では実在性について議論があったが、21世紀に入り考古学的発見から政治変革を評価する「新肯定論」が主流に
- 律令国家体制の基礎を築いた歴史的に重要な出来事
大化の改新とは?歴史を変えた政治改革の全貌

大化の改新は何時代?いつ起きた改革なの?
大化の改新は、飛鳥時代の645年に始まりました。
この改革は、中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足(後の藤原鎌足)が中心となって進めた政治改革で、それまでの豪族中心の政治体制から天皇を中心とする中央集権国家への転換を図ったものです。
狭義には「大化」という元号(日本初の元号!)が使われた645年から650年までの改革を指しますが、
広義には701年の大宝律令が完成するまでの約60年間の一連の改革をすべて含みます。
つまり、たった1回の出来事ではなく、長い時間をかけて日本の政治体制が大きく変わっていった過程なんです。
まず押さえておきたいのは、大化の改新は「乙巳の変」というクーデターと、その後の「改新の詔」に始まる政治改革の二つの出来事を含むということ。
以前は両者をひとまとめに「大化の改新」と呼んでいましたが、最近の教科書では区別して説明するようになっています。
大化の改新の目的は?簡単に説明すると
大化の改新の目的は、端的に言えば「天皇を中心とする強力な中央集権国家を作ること」でした。
当時、蘇我氏をはじめとする有力豪族が政治を牛耳り、天皇(当時は大王と呼ばれていました)の権威を脅かす状況になっていました。
また、国際情勢も重要な背景です。
618年に隋に代わって中国を統一した唐が強大な力を持ち、朝鮮半島でも高句麗・新羅・百済の三国が緊張関係にありました。
こうした国際環境の中で日本も国力を強化する必要があり、それには国内の統一的な政治体制が不可欠だったのです。
わかりやすく例えると、それまでの日本は「地方分権」のような状態で、各地の豪族がそれぞれの地域を自由に支配していました。
これを、「中央政府(天皇)」がすべてをコントロールする体制に変えようとしたのが大化の改新だったのです。
現代の政治で言えば、「地方分権から中央集権へ」の大転換だったわけですね。
乙巳の変と改新の立役者たち ―― 歴史を動かした人々

大化の改新の中心人物は誰?
大化の改新の立役者として最も有名なのは、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ、後の天智天皇)と中臣鎌足(なかとみのかまたり、後の藤原鎌足)の二人です。
当時皇極天皇の息子だった中大兄皇子は、まだ20歳程度の若さでしたが、政治改革の中心的な存在でした。
中臣鎌足は朝廷の官僚で、後に藤原氏の祖となる人物です。
二人は協力して蘇我氏打倒を計画し、実行に移しました。
改革を進めるにあたっては、他にも重要な人物がいます。
蘇我氏打倒後に即位した孝徳天皇(こうとくてんのう、元の名は軽皇子)、そして僧の旻(みん)や高向玄理(たかむこのげんり)といった知識人たちも改革を支えました。
彼らは唐の制度に詳しく、新しい政治制度の設計に貢献しました。
興味深いのは、最近の研究では改革の真の首謀者は中大兄皇子と中臣鎌足ではなく、軽皇子(孝徳天皇)自身だったという説も出ていること。
当時まだ下級官僚だった中臣鎌足が若い中大兄皇子を操れたはずがなく、天皇の座を狙っていた軽皇子が二人を使って蘇我氏を倒したという見方もあるんです。
乙巳の変 ―― 劇的な権力闘争の真相
大化の改新の起点となったのが「乙巳の変」(いっしのへん)です。
645年6月12日、中大兄皇子と中臣鎌足は、朝鮮半島からの使者を迎える儀式の場で、強大な権力を持つようになっていた蘇我入鹿(そがのいるか)を暗殺しました。
『日本書紀』によれば、中大兄皇子は入鹿の首に切りかかり、中臣鎌足らがとどめを刺したとされています。
入鹿の父である蘇我蝦夷(そがのえみし)も館に火を放って自害することになりました。
このクーデターは単なる権力闘争だったのでしょうか?
実は、最近の研究では、蘇我氏自体も改革派だった可能性も指摘されています。
蘇我氏も推古朝からの改革を進めようとしていたのに対し、中大兄皇子と中臣鎌足はより急進的な改革を望んでいたという見方もあるのです。
乙巳の変の直後、皇極天皇は退位し、その弟である軽皇子が孝徳天皇として即位しました。
そして日本で初めて「大化」という元号が定められたのです。
中国の元号に依存せず、独自の元号を定めたことは、自立した国家としての意識の表れとも言えるでしょう。
学校の先生は、ぜひ児童・生徒たちにこのことを教えていただければと願います。
改新がもたらした日本の大変革 ―― 新しい国のかたち

公地公民制 ―― 土地と人民の国家管理
大化の改新の中核となる政策が「公地公民制」(こうちこうみんせい)です。
これは何かというと、それまで豪族が私有していた土地(田荘・たどころ)や人民(部民・べみん)、そして天皇の私有地(屯倉・みやけ)や私有民(名代・子代)をすべて廃止し、国家が一元的に管理する制度です。
簡単に言えば、「すべての土地と人は国のもの」という考え方です。
今の時代では考えられないかもしれませんが、これによって豪族の経済的基盤を奪い、天皇(国家)の下に統一的な支配体制を作ろうとしたのです。
この制度を実現するため、「班田収授法」(はんでんしゅうじゅほう)という仕組みも導入されました。
これは6歳以上の人民に口分田(くぶんでん)と呼ばれる土地を国が貸し与え、死後に国に返却する制度です。
現代で言えば、土地の「所有」ではなく「利用権」を与えるような発想です。
実はこの制度、日本オリジナルではなく、唐の律令制度を参考にしたものでした。
当時の日本の指導者たちは、強大な唐をモデルに国づくりを進めていたんですね。
国郡制度と租庸調 ―― 地方行政と統一税制
大化の改新では地方行政制度も大きく変わりました。
それまでの国造(くにのみやつこ)などによる分権的な統治から、国-郡-里という階層的な行政区画を設け、中央から派遣された役人(国司など)が統治する仕組みを目指しました。
ただし、実際にはこの制度はすぐには実現せず、「評(こおり)」という中間的な制度が先に導入されたことが木簡の発掘から判明しています。
郡制が完全に実施されたのは、701年の大宝律令以降のことでした。
また、税制も「租庸調」(そようちょう)という統一的な制度が導入されました。
田に対する租(米)、戸別の調(特産物)、労役の庸を体系的に徴収する仕組みです。
これにより、国家は全国から安定した収入を得られるようになりました。
現代で例えるなら、所得税(租)、消費税(調)、労働義務(庸)のような多層的な税制を全国で統一的に実施する改革だったと言えるでしょう。
大化の改新後の政治と歴史的意義 ―― 時代を超える視点

大化の改新後の政治 ―― 律令国家への道
大化の改新後、日本の政治はどう変わったのでしょうか。
有力な豪族たちは「貴族」という位の高い役人となり、政治に参加する仕組みが作られました。
地方は国や郡(実際には最初は「評」)に分けられ、中央から役人が派遣されるようになりました。
ただし、改革はスムーズに進んだわけではありません。
大化4年(648年)には左右両大臣が新制の冠の着用を拒んだり、大化5年(649年)には右大臣の蘇我倉山田石川麻呂が謀反の嫌疑をかけられて自殺する事件が起きるなど、政情は不安定でした。
また、660年には百済が唐・新羅連合軍に滅ぼされ、662年には日本軍が白村江の戦いで大敗するという国際的危機も訪れます。
これに対応するため、九州北部に防人を配置したり、水城を築いたりと防衛体制も整えられました。
こうした試行錯誤を経ながら、大化の改新から始まった改革は、天智天皇・天武天皇の時代を経て、最終的に701年の大宝律令制定によって完成することになります。
時代の特色 ―― 古墳時代から飛鳥時代へ
大化の改新は、文化的にも大きな転換点となりました。
特に「薄葬令(はくそうれい)」により、天皇陵の造営に費やす時間が制限され、殉死も禁止されるなど、古墳の造営に関する規制が設けられました。
これにより、事実上、古墳時代は終わりを告げることになったのです。
また、唐の文化や制度を積極的に取り入れることで、日本の文化や社会制度も大きく変容していきました。
仏教の興隆もこの改新期の特徴の一つです。
この時期、冠位制度も大化3年に十三階、大化5年に十九階、天智3年に二十六階へと改訂が重ねられ、血縁や伝統に基づく支配から、より制度化された官僚制に基づく政治運営への移行が進みました。
歴史的意義と最新研究 ―― 近年の発見から見えてきたもの
大化の改新をめぐる研究は時代とともに変化してきました。
1930年代には坂本太郎が改新を律令制国家の起源として評価しましたが、1950年代以降、『日本書紀』の記述の信頼性が疑問視されるようになりました。
特に「郡評論争」では、改新の詔に記された郡制がすぐには実現せず、「評」という制度が先に導入されたことが明らかになりました。
さらに原秀三郎らは「改新否定論」を唱え、大化期の改革自体を『日本書紀』の編纂者による虚構とする見解も出てきましたのです。
また山尾幸久名誉教授は、『日本書紀』に記された改新の詔が和化漢文で書かれているのに対し、和化漢文が一般化するのは670年頃のことであること、また孝徳天皇が営んだとされる前期難波宮が実際にはもっと後世のものではないかという考古学的知見などから、大化の改新なるものには疑いの余地があると主張しました。
しかし21世紀に入ると、考古学的発見が相次ぎ、前期難波宮の発掘調査や「戊申年(大化4年・648年)」銘木簡の発見などにより、改新の実在性を支持する「新肯定論」が主流となっています。
現在の定説では、『日本書紀』の記述そのままではないものの、この時期に実際に大きな政治改革が行われたことは事実とされています。
つまり、教科書に書かれている「大化の改新」は、多少の脚色はあるかもしれませんが、実際に起きた歴史的出来事なのです。
国際関係の視点 ―― 東アジア情勢との関連

大化の改新を理解する上で欠かせないのが、当時の東アジア情勢です。
中国では618年に唐が成立し、強大な中央集権国家を形成していました。
朝鮮半島では高句麗・新羅・百済の三国が緊張関係にあり、唐の圧力も強まっていました。
この国際関係、国際的な緊張の理解無くして当時の国家がなぜ、中央集権化を急いだのかを理解することはできないでしょう。
こうした国際環境の中、日本も国力を強化し、外部の脅威に対応できる国家体制を整える必要がありました。
大化の改新は、国内改革であると同時に、国際情勢への対応策でもあったのです。
具体的には、589年に建国した強国隋に代わって唐が誕生し、その圧倒的な勢力を背景に朝鮮半島の情勢が不安定化したことが、日本の指導者たちに危機感を抱かせたのです。
国際関係の視点からみると、大化の改新は単なる国内政治の変革ではなく、東アジアの国際秩序における日本の生き残り戦略だったとも言えるでしょう。
まとめ:大化の改新の今日的意義 ―― 古代からのメッセージ
大化の改新は、日本の古代国家形成における重大な転換点でした。
豪族中心から天皇中心へ、分権的統治から中央集権へと国のかたちを変えたこの改革は、その後の日本の歴史に大きな影響を与えました。
最新の研究では、従来の定説に修正を加えながらも、この時期の政治変革の重要性が再評価されています。
歴史は常に新しい発見や解釈によって書き換えられていくもの。
大化の改新の研究からは、過去を知るだけでなく、現代の政治や社会の仕組みを考えるヒントも得られるのではないでしょうか。
中央集権と地方分権のバランス、国際情勢への対応、政治改革の進め方など、1400年前の改革が問いかける課題は、今日も色褪せていません。
「温故知新」―古きを訪ねて新しきを知る。
それが歴史を学ぶ醍醐味なのです。
大化の改新という古代の政治ドラマから、現代の私たちも多くを学ぶことができるでしょう。