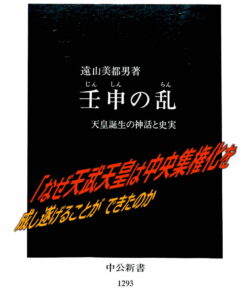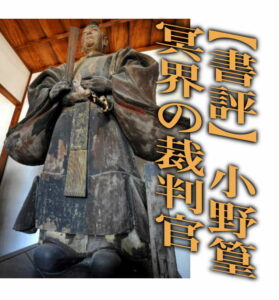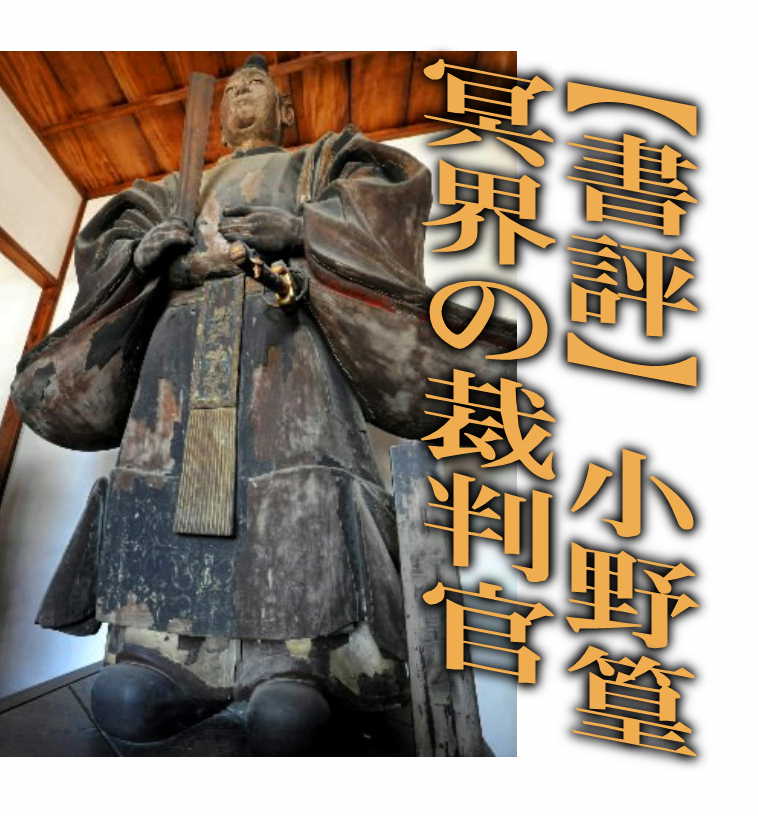
小野篁の概要と歴史的重要性
平安時代初期から前期にかけて活躍した小野篁(おののたかむら)は、延暦21年(802年)に生まれ、仁寿2年(852年)に51歳でその生涯を閉じた漢学者・詩人・官僚です。
彼は嵯峨天皇から仁明天皇、文徳天皇に至る六代の天皇に仕え、参議にまで昇進した実在の人物でありながら、後世には冥界の裁判官として数々の伝説を残した稀有な存在でした。
小野篁の魅力は、その卓越した漢詩の才能と機知に富んだ言動にあります。「無悪善」の高札を「嵯峨なくてよからん」と読み解いて嵯峨天皇を驚かせたエピソードや、
「子子子子子子子子子子子子」という文字列を「猫の子、仔猫。鹿の子、仔鹿」と解読した逸話は、彼の並外れた才知を示すものとして広く知られています。
歴史的には、小野篁は平安時代の文化形成に大きく貢献しました。
『令義解』の序文を執筆し、『経国集』や『文華秀麗集』に漢詩作品を残すなど、当時の文化的発展に寄与しています。
また、遣唐副使として任命されながらも渡航を拒否し、隠岐に流されるという波乱に満ちた経験は、当時の政治状況や外交政策を考察する上で重要な視点を提供しています。
本書は、そんな小野篁の実像に迫り、彼の生涯と業績を多角的に検証することで、平安時代の政治・文化の理解を深めるとともに、伝説と史実が交錯する魅力的な人物像を浮かび上がらせています。
本書の特徴と意義
本書の最大の特徴は、史実と伝説を明確に区別しながら、小野篁という人物の全体像を描き出そうとする姿勢にあります。
従来の研究では、篁は「冥界の裁判官」という伝説上の人物として扱われることが多く、実在の人物としての側面が十分に検討されてきませんでした。
本書では、『日本文徳天皇実録』に収められた篁の麗伝(こうでん)や『続日本後紀』などの一次史料を丹念に読み解き、彼の官歴や政治的活動を詳細に追跡しています。
同時に、『宇治拾遺物語』『十訓抄』などの説話集に見られる伝説的エピソードの形成過程も分析し、なぜ篁がそのような伝説の主人公となったのかを考察しています。
また、小野氏という氏族の歴史的背景にも光を当て、遣唐使や遣新羅使として活躍した小野妹子から連なる外交官としての家系の伝統が、篁の人生にどのような影響を与えたかを明らかにしています。
さらに、篁の漢詩作品を詳細に分析することで、彼の内面世界や思想にも迫っています。
本書の意義は、単に一人の歴史上の人物の伝記としてだけでなく、平安時代の政治・文化・外交の実態を具体的に理解するための窓口として機能している点にあります。
篁の生涯を通して、当時の官僚制度や外交政策、文学的営為の実態が浮き彫りになっており、平安時代研究の新たな視座を提供したといえます。
小野篁の生涯
誕生と家系背景
小野篁は延暦21年(802年)、桓武天皇の治世末期に生まれました。
父親は参議を務めた小野零守(みねもり)、祖父は征夷副将軍を務めた小野永見(ながみ)でした。
小野氏は、遣隋使として有名な小野妹子の子孫であり、古くから外交に携わる氏族として朝廷に仕えてきました。
小野氏の起源は、和珂(わに)氏に遡ります。
和珂氏は、「海人族(かいじんぞく)」と呼ばれる海の民を起源とする氏族で、鮫(わに)を自らの祖先と見なしていたとされています。
平安時代に入ると、和珂氏の一部は「小野」を名乗るようになり、近江国滋賀郡小野郷(現在の滋賀県大津市小野)を本拠地としました。
篁の祖父・永見は、漢詩人としても知られ、『凌雲集』に「田家」と題する詩を残しています。
父・零守も嵯峨天皇の側近として仕え、同天皇の漢学の師でもありました。
このように、篁は代々漢学の素養を持つ家系に生まれ、幼少期から学問的環境に恵まれていたのです。
若年期の才能の開花
篁の幼少期については詳しく知られていませんが、父・零守が弘仁6年(815年)に陸奥守に任命された際、篁は父に従って陸奥国に下向しました。
当時14歳だった篁は、陸奥の地で馬に乗ることに夢中になり、学問に身を入れることが遅れたといいます。
しかし、弘仁13年(822年)、篁は文章生試(もんじょうしょうし)に合格し、大学寮の文章生となります。
この試験は、『文選』や『史記』などの中国古典に精通していることが求められる難関試験でした。
21歳での合格は、菅原道真の18歳での合格に比べれば遅いものの、陸奥での生活から一転して学問に打ち込んだ成果と言えるでしょう。
文章生となった篁は、その才能を『経国集』に収められた「朧頭秋月明」の詩で示しました。
この詩は文章生試の答案として提出されたもので、辺境の地での軍事的緊張感を鮮やかに描き出しています。
彼の詩才は、陸奥での経験が生かされたものと考えられます。
この頃、篁は権中納言藤原三守の娘と結婚します。
彼は「奉右大臣書」という漢文の書状で結婚を申し込み、その文才によって三守家の婿となりました。
通常、結婚の申し込みは和歌で行われるのが慣例でしたが、篁は敢えて漢文を用い、しかも自ら相手方に持参するという異例の方法を取りました。
この逸話は、後に『篁物語』や『十訓抄』にも記されています。
官僚としてのキャリア
天長元年(824年)、篁は22歳で巡察弾正に任命されます。
これは諸官司を視察して不正を摘発する役職で、彼の官僚としてのキャリアの第一歩となりました。
翌年には弾正少忠に昇進し、天長5年(828年)には大内記に転じます。
大内記は詔勅や宣命といった重要文書を起草する職で、文才ある者が就くべき名誉ある地位でした。
天長7年(830年)、篁は式部少丞に転じ、同時に蔵人を兼ねて「蔵人式部丞」となります。
蔵人は天皇の側近として仕える役職で、これを兼任することで篁は朝廷の中枢に近づきました。
この年、篁は父・零守を亡くしますが、麗伝によれば「父親の死を悼むにあたって、節度を越える振る舞いに及んだ」とされています。
天長9年(832年)、篁は従五位下に叙され、貴族の仲間入りを果たします。
同時に大宰少弐に任命されますが、特別に在京のまま任務を遂行することを許されました。
これは、彼が『令義解』の編纂に関わっていたためと考えられます。
『令義解』は養老令の公式注釈書で、篁はその序文を執筆しました。
序文では「刑名は、天地と倶に興る」と述べ、法の重要性を強調しています。
遣唐使としての経験と挫折
承和元年(834年)、篁は遣唐副使に任命されます。
遣唐使は当時の日本にとって最も重要な外交使節であり、副使という地位は大きな名誉でした。
しかし、この任命が篁の人生における最大の試練となります。
承和3年(836年)、遣唐使の第一次派遣が行われますが、大使・藤原常嗣の船と副使・篁の船が損傷して帰国を余儀なくされます。
承和5年(838年)の再派遣に際し、船の割当をめぐって常嗣と対立した篁は、「老親養育」を理由に渡航を拒否します。
この行動は「違勅」(天皇の命令に背くこと)として重大な罪とされ、篁は官位を剥奪され、庶民の身分に落とされた上で隠岐国へ流罪となりました。
流配の途上で詠んだ「謫行吟」は『経国集』に収録され、彼の詩人としての評価を高める契機となりました。
篁の遣唐使拒否については様々な解釈があります。
実務官僚としての安全配慮説、遣唐使制度への批判的姿勢説、現実的なリスク管理説などが挙げられますが、いずれにせよ、この事件は彼の人生における大きな転機となりました。
晩年の活躍
承和8年(841年)、篁は赦免され、刑部大輔として官界に復帰します。
その後、東宮学士として文徳天皇(当時は道康親王)の教育にあたりました。
承和13年(846年)の法隆寺僧善愷訴訟では、僧侶の訴訟権限をめぐる法解釈論争で明法博士を論破し、訴訟手続きの整備に貢献しました。
承和14年(847年)、篁は参議に昇進し、公卿の一員となります。その後も左大弁など重要な官職を歴任しましたが、嘉祥2年(849年)に病気を理由に官職を辞そうとします。
しかし、朝廷はその辞表を受理せず、篁は引き続き公務に従事しました。
仁寿元年(851年)、篁は近江守に任命され、翌年には左大弁を再び兼ねますが、同年に病が再発し、ついに朝廷への出仕が困難になります。
文徳天皇は篁の病床を見舞う使者を幾度も送り、銭貨や米穀を下賜するなど、篁への深い配慮を示しました。
仁寿2年(852年)12月22日、篁は在宅のまま従三位を授かるという栄誉に浴しますが、その直後に51歳で生涯を閉じました。
死に際に篁は子どもたちに「私が息を引き取ったなら、ただちに葬るように。
また、私が死んだことは、わざわざ人々に知らせるには及ばない」と遺言したと伝えられています。
小野篁は、漢学者・詩人・官僚として優れた才能を発揮し、平安時代の文化と政治に大きな足跡を残しました。
同時に、その破天荒な性格から「野狂」とも呼ばれ、死後は冥界の裁判官として数々の伝説を生み出す存在となります。
本書は、そんな小野篁の実像と伝説の両面に光を当て、平安時代を生きた一人の知識人の姿を鮮やかに描き出しています。
小野篁の才能と業績
小野篁は平安時代初期から前期にかけて活躍した貴族であり、漢学者、詩人、官僚として多方面で優れた才能を発揮した人物です。
彼の生涯は多くの伝説や逸話に彩られており、その才能と業績は後世にまで大きな影響を与えました。
漢詩人としての評価
小野篁は漢詩の分野で卓越した才能を持ち、「天下に並ぶ者のない第一人者」と評されるほどでした。
彼の詩才は若い頃から顕著で、文章生試に及第した際に詠んだ「朧頭秋月明」の詩は、その優れた表現力と感性を示しています。
篁の漢詩の特徴は、繊細な自然描写と深い感情表現にあります。
例えば「雑言秋雲篇示同舎郎」では、秋の空の雲に思いを馳せ、俗世を離れたいという憧れを詠んでいます。
気膠標具品秋
客在西歳欲逡
登山臨水耶楚望
移目寒雲遠近愁
この詩からは、期待に応えなければならない重圧に疲れた篁の心情が伝わってきます。
彼は雲のように自由に空を漂いたいと願っていたのでしょう。
また、隠岐国への流罪の途上で詠んだ「謫行吟」は『経国集』に収録され、彼の詩人としての評価を高める契機となりました。
この詩には、流罪という厳しい状況の中でも失われない篁の気品と才気が表れています。
機知に富んだエピソード
小野篁の機知は、「無悪善」の高札解読の逸話に最もよく表れています。
『宇治拾遺物語』によれば、嵯峨天皇の時代、内裏に「無悪善」と書かれた高札が立てられ、誰もその意味を解読できませんでした。
しかし篁は、「悪」を「さが」と読み、「嵯峨なくてよからん(嵯峨天皇など、いない方がよい)」と解釈しました。
これは天皇に対する呪誼の言葉となりかねない危険な解釈でしたが、篁はそれを堂々と述べたとされています。
嵯峨天皇は篁の解読に驚き、「このような高札は、そなたの他に、いったい誰が書くだろうか」と疑いましたが、篁は巧みに言い逃れました。
さらに嵯峨天皇は篁の機知を試すため、「子子子子子子子子子子子子」という文字列を示し、読み方を尋ねました。
篁はすかさず「猫の子、仔猫。鹿の子、仔鹿」と答え、天皇を感心させたといいます。
また『十訓抄』では、「一伏三仰不来待書暗降雨恋筒寝」という複雑な文字列を「月夜には/来ぬ人待たる/掻き暗し/雨も降らなむ/恋ひつつも寝む」と読み解いたエピソードも伝わっています。
これは「むきさい」という遊戯の知識を応用した見事な解読でした。
法律家としての側面
小野篁は法律家としても優れた才能を発揮しました。
彼は『令義解』の編纂に携わり、その序文を執筆するという重要な役割を担いました。
この序文では「刑名は、天地と倶に興る」と述べ、法の重要性を強調しています。
特に有名なのは、承和13年(846年)の法隆寺僧善愷訴訟事件での活躍です。
この事件では、僧侶の訴訟権限をめぐる法解釈論争が起こりましたが、篁は明法博士を論破し、不毛な法解釈論議に終止符を打ちました。
篁は法律の専門家として、単なる条文の解釈だけでなく、法の本質を見抜く洞察力を持っていたのです。
彼の法解釈は、形式的な解釈に固執せず、実質的な正義を重視するものでした。
ただし、晩年には自らの法解釈が政治的に利用されたことを後悔したとも伝えられています。
外交官としての役割
小野氏は代々外交に携わる氏族であり、篁もその伝統を受け継いでいました。
承和元年(834年)、篁は遣唐副使に任命されます。
しかし、承和3年(836年)の第一次派遣では大使・藤原常嗣の船と副使・篁の船が損傷し帰国を余儀なくされました。
承和5年(838年)の再派遣に際し、船の割当をめぐって常嗣と対立した篁は、「老親養育」を理由に渡航を拒否します。
この行動は「違勅」として重大な罪とされ、篁は官位を剥奪され、庶民の身分に落とされた上で隠岐国へ流罪となりました。
篁の遣唐使拒否については様々な解釈があります。
実務官僚としての安全配慮説、遣唐使制度への批判的姿勢説、現実的なリスク管理説などが挙げられますが、いずれにせよ、この事件は彼の人生における大きな転機となりました。
小野篁をめぐる伝説と逸話
小野篁の人物像は、実在の人物でありながら、多くの伝説や逸話によって彩られています。
これらの伝説は、篁の才能と人格が後世の人々に与えた強い印象を示しています。
冥界の裁判官説
最も有名な伝説は、篁が昼間は朝廷の官人として働き、夜になると冥界に赴いて閻魔王のもとで亡者たちを裁く裁判官を務めていたというものです。
『宇治拾遺物語』などによれば、藤原良相が病で亡くなった際、冥界で篁に助けられて蘇生したとされています。
この伝説の背景には、篁の法律家としての卓越した能力があります。
現実世界での法的判断の確かさが、冥界の裁判官という神秘的な役割に結びついたのでしょう。
また、六道珍皇寺には「冥土通いの井戸」「黄泉がえりの井戸」と呼ばれる二つの井戸があり、篁が冥界との行き来に使ったと伝えられています。

「無悪善」の高札解読
先に述べた「無悪善」の高札解読の逸話は、篁の機知と大胆さを示す最も有名なエピソードの一つです。
この逸話には、『宇治拾遺物語』『十訓抄』『江談抄』など複数のバージョンがあり、細部に違いはあるものの、篁の卓越した才能と嵯峨天皇との特別な関係を示す点では共通しています。
実際には、嵯峨天皇が在位中に「嵯峨天皇」と呼ばれることはなく、この逸話が史実そのままであるとは考えにくいのですが、篁の機知と天皇との親密な関係を象徴する物語として広く伝わりました。
白楽天との詩の交流伝説
篁と中国の詩人・白居易(白楽天)との交流をめぐる伝説も興味深いものです。
『江談抄』によれば、嵯峨天皇が秘蔵していた白居易の詩の一部を篁に見せ、その一句を修正するよう求めたところ、篁は白居易の原文通りの修正を提案したといいます。
これにより、篁と白居易が同じ詩的感性を持つことが証明されたとされています。
また、「古老の言い伝え」として、白居易が篁の来訪を待ち望み、「望海楼」という楼閣を建てたという話や、白居易の詩の中に篁の詩と同じ句が三つあったという話も伝わっています。
特に「野蕨人拳手/江藍錐脱嚢」という句は、篁の詩にも類似の表現が見られます。
これらの伝説は、篁の詩才が白居易に匹敵するほど優れていたことを示すために作られたものと考えられます。
白居易は平安時代中期以降、日本の漢詩・漢文の手本として最も尊重された詩人であり、彼と同等の評価を得ることは、最高の栄誉でした。
篁の人物像と歴史的意義
小野篁は、その卓越した才能と多彩な活動によって、平安時代の文化と政治に大きな足跡を残しました。
漢詩人・法律家・官僚としての彼の業績は、当時の日本の知的水準の高さを示すものです。
同時に、篁をめぐる数々の伝説は、彼の人物像が後世の人々にどれほど強い印象を与えたかを物語っています。
特に冥界の裁判官としての伝説は、平安時代以降の日本人の死生観や冥界観に影響を与え、文学や芸術の題材として繰り返し取り上げられてきました。
江戸時代には『小野篁歌字尽』という漢字学習書が篁の名を借りて出版され、ロングセラーとなりました。
これは、機知に富んだ教育者としての篁のイメージが、後世にまで生き続けていたことを示しています。
小野篁という人物は、実在の歴史上の人物でありながら、その才能と業績によって伝説的な存在へと昇華し、日本の文化史に独自の位置を占めるに至ったのです。
彼の生涯と伝説は、平安時代の政治・文化・信仰の諸相を理解する上で、今なお貴重な手がかりを提供してくれます。
小野氏の歴史における篁の位置づけ
海人族の末裔としての小野氏
小野篁が生まれ育った小野氏は、古代日本の氏族の中でも特異な位置を占めていました。
第三章に詳しく書かれていた通りです。
小野氏は和珂(わに)氏から枝分かれした氏族であり、その和珂氏は「海人族(かいじんぞく)」と呼ばれる海の民を起源としていました。
和珂氏の「ワニ」は鮫を意味し、彼らは鮫こそを自らの祖先と見なす一族だったのです。
『新撰姓氏録』によれば、和珂氏の本流は平安時代までに「大春日(おおかすが)」を名乗るようになりましたが、その枝族として小野氏が存在していました。
小野氏の名前の由来は、彼らが近江国滋賀郡小野郷(現在の滋賀県大津市小野)を本拠地としていたことによります。
琵琶湖西岸に位置するこの地は、和珂川下流域に位置し、まさに和珂氏の勢力圏の延長線上にありました。
海人族の末裔である小野氏は、海から湖の民へと転じながらも、その特性を活かして朝廷に仕えていきました。
琵琶湖の湖上輸送を担った彼らは、中国大陸や朝鮮半島からの情報をいち早く入手できる立場にあり、それが外交官としての活躍の基盤となったのです。
篁の祖父である小野永見は征夷副将軍として活躍しましたが、これも単なる武官としてではなく、蝦夷との交渉を担当する外交官としての側面が強かったと考えられます。
また、永見は『凌雲集』に収められた「田家」という漢詩を残しており、小野氏に漢詩人・漢学者としての素養をもたらした人物でもありました。
外交を担う氏族としての伝統
小野氏の歴史を振り返ると、彼らが代々、朝廷の外交を担ってきた氏族であることがわかります。
その始まりは、遣隋使として有名な小野妹子にまで遡ります。
推古天皇十五年(607)、小野妹子は最初の遣隋使として海を渡りました。
妹子の子孫たちも外交官としての伝統を受け継ぎ、小野毛人は遣新羅使、小野田守は遣新羅使と遣渤海大使を務めました。
また、小野石根は遣唐副使として唐に渡り、不運にも帰路で海難事故に遭いましたが、彼の下で遣唐判官を務めた小野滋野は無事に帰国しています。
このような外交を担う氏族としての伝統は、篁にも受け継がれました。
篁は承和元年(834)に遣唐副使に任命されましたが、この任命自体が小野氏の外交官としての伝統に沿ったものだったのです。
しかし、篁は遣唐使の出発を前に、船の割り当てをめぐる問題から渡航を拒否し、隠岐国への流罪という厳しい処分を受けることになります。
これは小野氏の外交官としての伝統からの逸脱とも見えますが、一方で、篁の行動は当時の遣唐使制度の問題点を鋭く指摘するものでもありました。
篁は流罪から復帰した後、刑部大輔や東宮学士など、様々な官職を歴任し、最終的には参議にまで昇進します。
彼は小野氏の中でも最も高い地位に上り詰めた人物となり、小野氏の歴史における頂点を極めたと言えるでしょう。
本書の評価
史実と伝説の丁寧な区別
本書の最大の特徴は、小野篁という人物をめぐる史実と伝説を丁寧に区別しながら、その全体像を描き出そうとする姿勢にあります。
篁は実在の人物でありながら、「冥界の裁判官」という伝説上の人物としての側面も持ち合わせています。
本書では、『日本文徳天皇実録』に収められた篁の麗伝や『続日本後紀』などの一次史料を丹念に読み解き、彼の官歴や政治的活動を詳細に追跡しています。
同時に、『宇治拾遺物語』『十訓抄』などの説話集に見られる伝説的エピソードの形成過程も分析し、なぜ篁がそのような伝説の主人公となったのかを考察しています。
例えば、「無悪善」の高札をめぐる逸話や、冥界の裁判官としての伝説が、どのような歴史的背景のもとで形成されたのかを明らかにしています。
このように史実と伝説を明確に区別することで、篁という人物の実像に迫ることができるのです。
本書は、単なる伝記としてではなく、歴史研究としての小野篁論を展開しているのです。
多面的な小野篁像の提示
本書のもう一つの特徴は、小野篁という人物を多面的に描き出している点です。
篁は漢学者・漢詩人としての側面、法律家としての側面、官僚としての側面、そして伝説上の人物としての側面など、様々な顔を持っていました。
漢学者・漢詩人としての篁は、『経国集』に収められた「雑言秋雲篇示同舎郎」などの優れた漢詩を残し、『令義解』の序文を執筆するなど、当時の文化的発展に寄与しました。
法律家としての篁は、法隆寺僧善愷訴訟事件で明法博士を論破し、不毛な法解釈論議に終止符を打ちました。
官僚としての篁は、巡察弾正から始まり、大内記、式部少丞、蔵人、弾正少弼、刑部大輔、東宮学士などを歴任し、最終的には参議にまで昇進しました。
そして伝説上の人物としての篁は、冥界と現世を行き来し、閻魔王の下で裁判官を務めたとされています。
本書は、これらの多面的な篁像を統合し、一人の人間としての篁の全体像を描き出すことに成功しています。それは、単に事実を羅列するのではなく、篁という人物の内面世界や思想にも迫ろうとする試みなのです。
ネット上の評価:
★★★★☆ 4.5/5
「小野篁の実像に迫る良書」「伝説と史実を丁寧に区別し、多角的に描いている」「平安時代の政治や文化の理解にも役立つ」「読みやすく、興味深い内容」という高評価が多い。
一方で「専門的すぎる部分がある」という指摘も見られる。
総じて高評価となっているのは、著者が一次史料を丹念に読み解き、伝説と史実を明確に区別しながら、小野篁の実像に迫ろうとする姿勢が評価されているためと考えられる。
また、単なる伝記にとどまらず、平安時代の政治や文化の理解にも役立つ内容となっている点も高く評価されている。
筆者の評価:
本書は小野篁の実像を知る上で非常に優れた一冊である。
伝説上の人物というイメージが強かった小野篁だが、本書を読むことで、彼が日本史上まれに見る天才の一人であったことがよく分かる。
特に、十代前半を陸奥で過ごし、勉強よりも馬術に興味を示したというエピソードは興味深い。
また、史実と伝説を丁寧に区別しながら、平安時代の政治や文化についても深く掘り下げており、時代背景の理解にも大いに役立つ内容となっている。
総合的に見て、高く評価できる良書である。(4.7/5点中)
まとめ
小野篁再評価の意義
小野篁は、平安時代の貴族社会において、漢学者・漢詩人・法律家・官僚として多方面で活躍した人物でした。
しかし、後世には「冥界の裁判官」という伝説上の人物として記憶されることが多く、実在の人物としての篁の姿は見えにくくなっていました。
本書は、そうした伝説に埋もれていた実在の篁の姿を掘り起こし、その実像に迫ることを試みています。
それは、単に史実を明らかにするという作業にとどまらず、なぜ篁がそのような伝説の主人公となったのかを考察することでもあります。
篁の再評価は、平安時代の知識人の一人の姿を明らかにするだけでなく、当時の政治・文化・社会の様々な側面を理解する上でも重要な意味を持っています。
篁という一人の人物を通して、平安時代という時代そのものを見つめ直す契機となりました。
また、小野氏という氏族の歴史における篁の位置づけを明確にすることで、古代から平安時代にかけての氏族の変遷や役割の変化についても理解を深めることができます。
海人族を起源とし、外交を担う氏族として発展してきた小野氏の歴史の中で、篁がどのような位置を占めていたのかを考察することは、日本の古代史・中世史研究にとっても意義深いものとなるでしょう。
今後の研究への期待
本書は、小野篁という人物の伝記としては初めての本格的な研究書ですが、篁研究はまだ始まったばかりと言えます。今後の研究によって、さらに多くの史料が発掘され、篁の実像がより鮮明になることを期待します。
特に、篁の漢詩作品や法律家としての活動については、まだ解明されていない部分が多く残されています。
また、篁の子孫とされる人々についても、より詳細な研究が待たれるところです。
さらに、篁をめぐる伝説の形成過程についても、より詳細な研究が必要でしょう。
なぜ篁が「冥界の裁判官」として語り継がれるようになったのか、その背景には平安時代の宗教観や死生観がどのように関わっていたのかなど、考察すべき課題は多く残されています。
本書は、そうした今後の篁研究の出発点となり、平安時代研究の新たな地平を切り開く契機となることでしょう。
小野篁という一人の人物を通して、平安時代の政治・文化・社会の実態に迫る研究が、今後ますます発展していくのではないでしょうか。