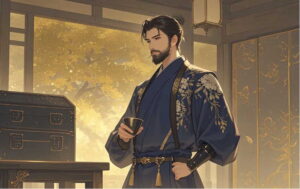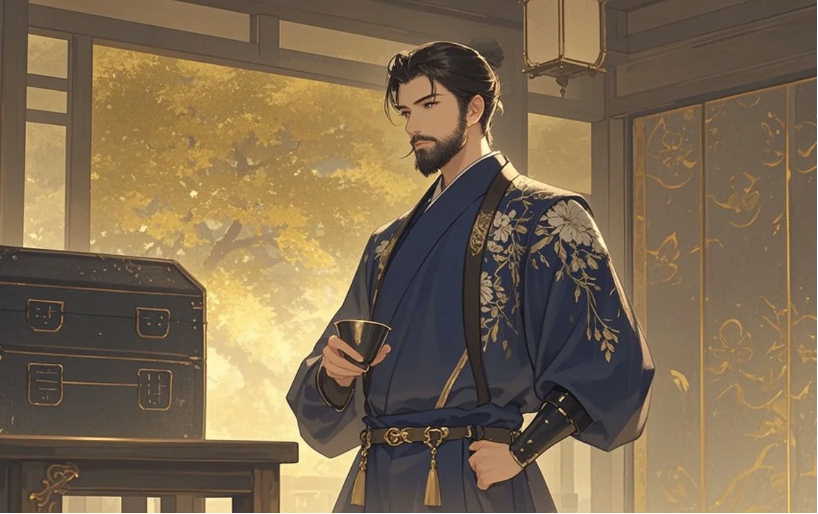
「天皇か貴族か?一 筋縄ではいかない奈良時代の権力闘争の実像に迫る」
1.はじめに:奈良時代における権力構造の謎
教科書では「天皇を頂点とする中央集権国家」と単純化される奈良時代。
しかし実際の政治構造は驚くほど複雑でした。
「畿内政権論」では貴族層が実権を握り天皇を共立したとし、
「専制君主論」では天皇が絶対的権力を持ったとする–
これら相反する学説が示すように、真実は容易に捉えられません。
奈良時代(710~794年)の政治は、表面的な律令制の下に、
旧来の氏族制や人格的な結びつきが複雑に絡み合い、
天皇・貴族・太上天皇・皇太子・キサキなど複数の権力核が相互に影響し合う「多極構造」を形成していました。
本記事では、この時代に起きた7つの政治闘争を通じて、単なる「天皇vs貴族」という二項対立では説明できない、
奈良時代の権力構造の実像に迫ります。
2.奈良時代の国家体制:誰が実権を握っていたのか
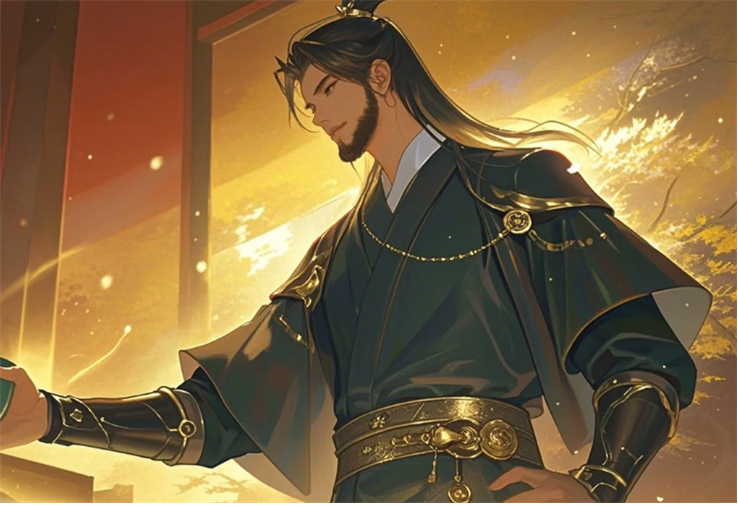
奈良時代の権力構造を理解するうえで重要なポイントは、
表と裏の顔があることです。
表の顔は整然とした律令制度。
裏の顔は複雑な人間関係です。
「強大な権力を手にした天皇を中心に中央集権的国家体制の形成が進んだ」
これが教科書的説明ですが、実際はどうだったのでしょう?
2-1.律令制下の天皇権力の実態
天皇には官職改廃権や軍の指揮権など「建前」上の権力がありました。
しかし実際の政治運営では、太政官という組織が重要な役割を果たしていたのです。
奈良時代の政治は、貴族たちによる合議制が基本。
でも、最終決定権は天皇にありました。
この微妙なバランスが奈良時代の政治闘争の背景にあるんです。
YouTubeでは天皇の歴史的権力について様々な解説動画が公開されていますが、
史料に基づく研究によれば、
奈良時代の天皇は「絶対的」でも「単なる象徴」でもない、
複雑かつ独特の権力構造の中心に位置していたのです。
2-2.議政官と畿内政権論の真実
太政官を頂点とする律令国家の行政機構は、
大化前代の群臣会議を継承していました。
しかし、議政官の地位は天皇による再編成を経たものであり、
貴族たちは天皇の承認によって地位を得ていたという実態を忘れてはいけません。
つまり、奈良時代の七代政治権力の構造は、相互依存関係にあったわけです。
天皇は貴族なしでは統治できず、
貴族は天皇なしでは正統性を得られなかったのです。
歴史系SNSでよく議論されるのは
「奈良時代は貴族と天皇のどちらが強かったのか?」
という問いですが、
これは現代的な「勝ち負け」の発想であり、
当時は両者が複雑に絡み合う統治システムだったと考えるべきでしょう。
3.驚愕の8大政治権力闘争とその真相

奈良時代は約10年ごとに政権交代が起きていました。
この七代政治権力の交代パターンこそ、
奈良時代の政治構造を理解する鍵なのです。
3-1.長屋王の変(729年):藤原氏の陰謀の始まり
聖武天皇の母方の従兄弟だった長屋王。
左大臣として権勢を誇りましたが、
藤原四兄弟による陰謀で自殺に追い込まれました。
この政治闘争は、武力ではなく政治的手段で行われた点が特徴的です。
奈良時代になると、権力闘争の形も変化していったんですね。
藤原氏は聖武天皇に藤原不比等の娘・光明子を皇后として迎えさせることで、
王家との血縁関係を強化していったのです。
平城宮跡資料館や奈良文化財研究所による調査資料によれば、
1986年から始まった長屋王邸の発掘調査では3万点以上の木簡が出土し、
これらは王侯貴族の家政機関や日常生活の実態を明らかにする貴重な資料となっています。
木簡からは長屋王家が畿内の各地に所有していた
「御田(みた)」「御薗(みその)」と呼ばれる私有地から
毎日のように米や野菜を進上されていた実態など、
文献史料だけでは知り得なかった詳細が判明しています。
これらの発見は歴史研究において重要な再評価をもたらし、
長屋王の政治的地位や生活についての関心は現代でも高いままです。
3-2.藤原広嗣の乱(740年):地方からの反乱
大宰少弐(だざいのしょうに)に左遷された藤原広嗣が、僧正・玄昉と吉備真備を弾劾して反乱を起こしました。
この闘争の背景には、中央政界での権力闘争だけでなく、地方統治の問題もあったのです。
広嗣にとって九州への左遷は「大きな屈辱」だったのです。
奈良時代の政治権力は中央だけでなく、地方との関係も重要だったことがわかりますね。
奈良時代では藤原広嗣の乱のような地方からの反乱があったことが知られています。
Twitterでもこうしたテーマについてのツイートが見られます。
中公新書の「奈良時代」に関するツイートでは
「地方から反乱や権力争いも凄い」と言及されており、
奈良時代の政治構造における地方と中央の関係は、今日でも歴史ファンの関心を集めるテーマとなっています。
3-3.橘奈良麻呂の変(757年):権力闘争の熾烈化
藤原仲麻呂の増大する権力に対抗するため、橘奈良麻呂らが謀反を企てました。
しかし密告により計画は頓挫。
「首謀者は拷問で死亡」という悲惨な結末からは、
奈良時代の権力闘争がいかに命がけだったかがわかります。
この事件で反藤原派の勢力はさらに衰え、藤原仲麻呂の権力は絶頂に達しました。
歴史好きの間では「もし橘奈良麻呂の変が成功していたら?」という歴史のIFを考察する記事が人気です。
日本史の分岐点として、現代の政治バランスも大きく変わっていたかもしれません。
3-4.藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱(764年):頂点からの転落
従一位まで上り詰めた藤原仲麻呂。
「道鏡が力を持ち始めたことに不安を感じて反乱を起こしましたが、
称徳天皇は重要な権力の象徴である鈴印を取り戻して、藤原仲麻呂(恵美押勝)の反乱を鎮めました。」
政治闘争において、行政手続きの象徴である鈴印の確保が重視された点は、
制度が浸透した奈良時代ならではの特徴です。
この政治闘争についてもっと詳しく知りたい方には、
『藤原仲麻呂 古代王権を動かした異能の政治家』(中公新書)がおすすめです。
仲麻呂の政治的野心と権力基盤について詳細に分析されています。
3-5.道鏡事件(766-770年):宗教と政治の危うい関係
称徳天皇の寵愛を受けた道鏡は、太政大臣禅師から法王にまで上り詰めました。
僧でありながら朝廷の最高位についた道鏡は、
称徳天皇の厚い信頼を背景に権勢をふるい、仏教を中心とした政治を推し進めたのです。
仏教者でありながら政治の中枢に入り込んだ道鏡の存在は、
天皇との個人的なつながりが権力獲得の道になりうることを示す象徴的事例です。
彼は政界・仏教界の両方でトップとなり、
家族も高い地位に就き、各地に大寺院を建立するなど、
仏教と政治が究極的に近づいた時代を創り出したのです。
この奈良時代の政治権力闘争の中でも、宗教者による政治介入という特殊なケースだったのです。
道鏡事件の影響は大きく、「天皇は皇族であるべき」という考えが強まり、
「仏教が政治に関与しすぎると問題が起こる」という教訓を残しました。
一般的には権力欲に溺れた悪僧とされてきた道鏡ですが、
近年では学識ある優れた僧侶だったとする見方や、
民衆に配慮した政策を行ったとする再評価も進んでいます。
宗教と政治の関係性は現代でも普遍的なテーマであり、道鏡の事例は今日の視点からも考察され続けています。

3-6.光明子と藤原氏の台頭:血縁政治の実態
聖武天皇の皇后となった光明子は、
藤原不比等の娘として藤原氏と天皇家をつなぐ重要な役割を果たしました。
「天に日月があるように」と聖武が並び立つ存在として位置づけたほど、
光明子の影響力は絶大でした。
藤原氏は彼女を核に結集して天皇家産との関わりを持つことで、
政治的影響力を確保していったのです。
この時代の婚姻政治についてさらに学びたい方には、
『女帝の世紀 皇位継承と政争』(KADOKAWA/角川学芸出版)が参考になります。
この書籍では「なぜ光明子の立后は必要だったのか」という視点から、
奈良時代の政治構造における婚姻の役割が分析されています。
光明子が藤原氏と天皇家をつなぐ重要な架け橋となり、
政治的影響力を発揮した実態を理解する上で貴重な資料となるでしょう。
3-7.淳仁天皇と孝謙太上天皇の権力闘争:不安定な両天皇体制
淳仁天皇の即位によって新しい太政官体制が構築されましたが、
孝謙太上天皇との間に軋轢が生じました。
実際には淳仁天皇は藤原仲麻呂の「操り人形」に過ぎず、実権は藤原仲麻呂が握っていたのです。
この権力闘争は道鏡の台頭と密接に関係しています。
孝謙太上天皇が道鏡を寵愛して政治にも関与させるようになると、
藤原仲麻呂はこれに反発。
さらに孝謙太上天皇は「皇権も国家の大事と賞罰は上皇が掌握し、天皇はただ小事と常祀を行うだけ」と宣言し、
実質的な権力を掌握しました。
この対立は藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱につながり、
最終的に淳仁天皇は廃帝となって淡路に流されたのです。
流罪地の淡路で淳仁天皇は謎の死を遂げることになります。
公式記録では脱走を試みた翌日に病死したとされていますが、
その不自然さから実際には
復権の動きを恐れた孝謙上皇側によって殺された
という説が主流となっています。
この事件は、律令制下における太上天皇と現天皇の権限の不明確さが招いた悲劇といえるでしょう。
天皇と太上天皇という二重権力構造の危うさを示す歴史的事例として、現代にも重要な示唆を与えています。
3-8.藤原百川の台頭:藤原氏の復権と皇統の転換

藤原百川は奈良時代の終わり頃(732年〜779年)に活躍した政治家で、
藤原不比等の孫にあたります。
彼は藤原式家の祖である宇合の8番目の息子として生まれ、初めは「雄田麻呂」と名乗っていました。
百川の政治手腕がとりわけ光ったのは、称徳天皇の時代です。
表向きは「内豎大輔」という宮中の役職で称徳天皇と道鏡に仕えながら、
裏では道鏡が天皇になるのを阻止するために動いていたのです。
769年の「宇佐八幡宮神託事件」では、道鏡の皇位継承に反対した和気清麻呂が配流された後も、
密かに食料や生活必需品を送り続けるなど、危険を冒しながらも着実に自分の信念を貫いていました。
称徳天皇が770年に後継者を決めないまま亡くなると、
天智天皇の孫である白壁王(後の光仁天皇)を次の天皇に推しました。
このとき、反対派の右大臣・吉備真備らを巧みに出し抜く政治的手腕を発揮したのです。
これにより、それまでの天武系から天智系への皇統の転換が実現しました。
光仁天皇からの信頼は非常に厚く、百川は次々と昇進していきます。
彼は「天皇の腹心」として政治の中心に立ち、内外のあらゆる重要事項に関わるようになりました。
772年には井上内親王(称徳天皇の妹)の皇后の地位を剥奪し、
その子である他戸親王(おさべしんのう)の皇太子の地位も奪う政治的決断に関わります。
翌773年には、百川の建議により山部親王(後の桓武天皇)が皇太子に立てられました。
母親が百済渡来人系の高野新笠という出自だった山部親王にとって、これは予想外の大抜擢だったでしょう。
百川はこの若き皇太子の才能を見込み、彼が病に倒れた際には医薬と祈祷に心力を尽くすほど献身的に支えました。
藤原百川は、藤原仲麻呂の乱以降低下していた藤原氏の権力を回復させただけでなく、
奈良時代から平安時代への移行期において重要な役割を果たたのです。
779年、48歳で亡くなった百川は、山部親王の即位(桓武天皇)を見ることはできませんでしたが、
その後、桓武天皇は百川の娘・旅子を夫人とし、
その間に生まれた淳和天皇の時代に百川は正一位・太政大臣を追贈されました。
激動の時代に政治家として絶妙のバランス感覚を保ち、
決して失脚することなく重要ポストを務め続けた百川は、
「知略に富み平安時代の創始を導いた政治家」と評価されているのです。
4.権力闘争から見える奈良時代の政治の実像

4-1.多極的な権力構造の真実
奈良時代の権力構造は、単に天皇と貴族の二項対立ではありませんでした。
太上天皇・皇后・皇太子など複数の権力核が存在する多極的なものだったのです。
『日本古代王権と貴族社会』(八木書店)によれば、
奈良時代における天皇は単独での権威が不十分であり、
「王権の多極構造を構成することが肝要であった」と指摘されています。
ただし、太上天皇の役割については新たな研究で見直しが進んでいます。
従来は対立的に捉えられがちでしたが、実際には
「奈良時代の太上天皇や皇后・皇太后は天皇の政治を支える立場にあり、決して二重権力のような存在ではなかった」という見解も示されているのです。
この複雑な権力バランスの中で、「天皇」という存在を核とした結集力が国家運営の鍵を握っていたといえるでしょう。
現代の組織と比較する視点も研究されており、
古代王権の「多極構造」という枠組みの有効性は、
現代の組織研究にも示唆を与える可能性があります。
奈良時代の多極的権力構造の研究は今も続いており、
考古学的発見や文献研究の進展によって、より詳細な実態解明が進んでいます。
4-2.天皇の財産と権力の関係
奈良時代には、天皇の個人的な財産である「天皇家産」(てんのうけさん)がありました。
これは単なる私的な財産というだけでなく、政治的に重要な意味を持っていたのです。
「天皇家産」とは、天皇の私有財産や私的組織を指し、
現代の言葉で言えば「皇室の個人資産」のようなものです。
このお金や品物は国の公的な財産とは区別されていました。
特に「内蔵寮」(ないくらりょう)という組織は、天皇の私財を管理する重要な部署でした。
通常、国の財産を使う場合は複雑な役所の手続きが必要でしたが、
内蔵寮からのものは天皇が直接「これを使って」と命令できました。
これにより、天皇は気に入った人に直接褒美を与えることができたのです。
聖武天皇の皇后となった光明子(こうみょうし)は、藤原不比等(ふじわらのふひと)の娘です。
彼女は単なる皇后としてだけでなく、政治的にも大きな影響力を持っていたのです。
例えば、彼女が関わった「金光明寺写経所」(きんこうみょうじしゃきょうじょ)では、
彼女の影響下にある皇后宮職(こうごうぐうしき:皇后の事務所)の人々が働いていました。
藤原氏は光明子を通じて天皇家と密接な関係を築き、
天皇の私的な財産や組織に関わることで政治的な力を得ていったのです。
これは単なる政略結婚ではなく、天皇との人間関係を通じて政治的影響力を持つための重要な戦略だったのです。
奈良時代の財産と権力の関係についての研究は今も続いています。
正倉院文書(しょうそういんもんじょ:奈良時代の重要な記録文書)や
近年発掘された木簡からは、従来の歴史書だけでは知り得なかった新しい情報が発見され、
私たちの奈良時代理解は少しずつ更新されているのです。
5.現代に通じる権力の本質:奈良時代から学ぶこと

奈良時代に起きた権力争いは、遠い昔の出来事ではありますが、
今の政治を考える上でも参考になることがたくさんあります。
奈良時代には、藤原不比等から始まり、長屋王、藤原四子、橘諸兄、藤原仲麻呂、道鏡、藤原百川と、
約10年ごとに実権が移っていきました。
こうした政治の移り変わりは現代でも見られる政権交代と似ているところがあります。
律令制という立派な制度があったのに、実際には貴族たちの間での激しい権力争いがあったり、
僧侶が政治に深く関わるなど、決まりごとと実際の政治運営の間には大きな差がありました。
これは今の社会でも、制度と運用が必ずしも一致しないことと似ています。
また、奈良時代の後半には、桓武天皇が「天皇による政治を取り戻そう」として平安時代を開きましたが、
これは制度を正しく運用して国を立て直そうという試みだったのです。
奈良時代の出来事を学ぶことで、どんな時代でも権力をめぐる争いがあること、
制度だけでなく人間関係も政治に大きく影響することがわかります。
こうした歴史の教訓は、今の社会や政治を見るときにも役立ちます。
6.奈良から平安へ:藤原摂関政治への道
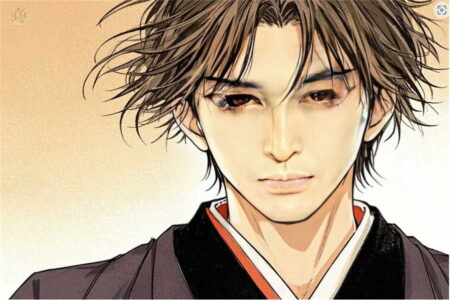
奈良時代の政治権力闘争は、その後の日本政治史に大きな影響を与えました。
特に藤原氏の台頭は、平安時代の藤原摂関政治の基盤となりました。
794年、桓武天皇は仏教勢力の政治介入を抑えるために平安京へ遷都します。
桓武天皇は強い支配力を発揮し、当初は藤原氏の影響力を抑えていましたが、
その後の平安時代初期において、藤原北家は着々と天皇家との結びつきを強めていきました。
特に藤原冬嗣は嵯峨天皇から全幅の信頼を得て蔵人頭に就任し、
皇室との姻戚関係を築くことに成功します。
その子・藤原良房の代になると、866年に起きた応天門の変で政敵の伴善男らを追放し、
臣下として初めて摂政に就任。
摂関政治の基礎を確立したのです。
平安前期は奈良時代からの中央集権的な律令政治を基本的に継承しつつも
部分的な修正を加えており、
奈良時代から平安時代への移行は
政治制度の連続性と進化の過程だったといえます。
藤原氏が築いた「天皇の外戚となって権力を握る」という戦略は、
平安時代になると「摂政・関白として天皇の代わりに政治を行う」形に発展し、
10世紀末の藤原道長の時代に安定期を迎えます。
摂政は天皇が幼い時に、関白は天皇が成長した後にその補佐をする役職であり、
これによって藤原氏は実質的に政治権力を掌握しました。
このように奈良時代の政治闘争と藤原氏の台頭は、平安時代の政治体制を形作る重要な基盤となったのです。
7.現代の天皇制と奈良時代の連続性と断絶

現代の象徴天皇制と奈良時代の天皇制は、表面的には大きく異なりますが、連続性も見出せます。
例えば、天皇が政治的実権を持たず、象徴的存在でありながらも国民統合の核となる点は、
奈良時代の「多極構造の中での結集核」という役割と類似しています。
一方で、現代の天皇制が憲法に基づく明確な法的位置づけを持つのに対し、
奈良時代の天皇は律令で明確な規定がなかった点は大きな違いです。
このような連続性と断絶を意識することで、
日本の政治文化に通底する特質を理解することができるでしょう。
8.未解決の謎と最新研究:奈良時代研究の最前線
奈良時代の研究は今も続いています。この時代の権力構造にはまだ解明されていない部分がたくさんあります。
例えば:
・道鏡はどこまで政治的影響力を持っていたのか?
・藤原氏はなぜ他の豪族より長く権力を保てたのか?
・光明子は実際にどのような政治的役割を果たしていたのか?
最近でも、平城宮跡からは新しい木簡が見つかっています。
2024年3月には聖武天皇の即位時(724年)の大嘗祭に関連する「大嘗分」と書かれた木簡が発見されました。
こうした新発見が奈良時代の理解を少しずつ深めています。
奈良時代の政治闘争は表面的には藤原氏対その他勢力の争いに見えますが、
実際はもっと複雑でした。
約10年ごとに「藤原氏→それ以外→藤原氏→それ以外」と政権が交代するパターンの背後には、
天皇を中心とした複雑な権力構造があったのです。
奈良時代は約10年ごとに次の順序で政権担当者が交代
- 藤原不比等(710年代):中臣鎌足の息子で、藤原氏が外戚となる基盤を作りました
- 長屋王(720年代):天武天皇の孫で、皇族として権勢を誇りましたが藤原氏の策略で自殺に追い込まれました
- 藤原四子(730年代):藤原武智麻呂・房前・宇合・麻呂の四兄弟が政権を担当しましたが次々と天然痘で亡くなりました
- 橘諸兄(740年代):長屋王の娘婿で、元昉や吉備真備を登用し政治を担いました
- 藤原仲麻呂(750年代):光明皇后の信頼を得て権力を握り、恵美押勝の名を賜りましたが後に反乱を起こして滅びました
- 道鏡(760年代):僧侶でありながら称徳天皇の信任を得て法王にまで上り詰めた異色の存在です
- 藤原百川(770年代):藤原不比等の孫で、天武系から天智系への皇統転換に貢献し、藤原氏の権力を回復させました
この時代に政治闘争の形が、武力での解決から制度を使った解決へと変わっていったことは、
律令国家が成熟していった証拠の一つと言えるでしょう。
奈良時代の政治のあり方を学ぶことは、現代の政治や社会を理解する上でも役立ちます。
どんな時代でも権力争いはあり、制度だけでなく人間関係も重要な要素だということは、
今も変わらない真理なのです。