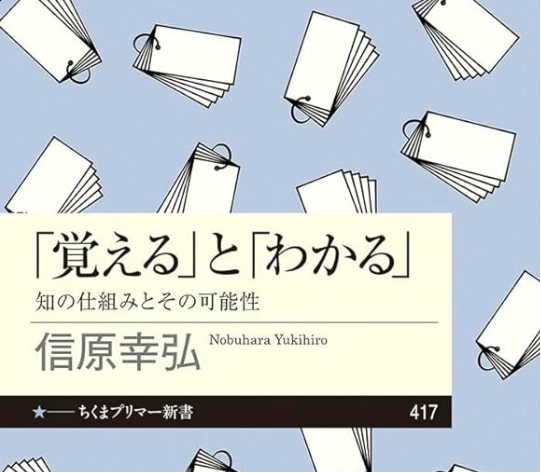
著者紹介
信原幸弘(のぶはら ゆきひろ)氏は、1954年生まれの哲学者で、東京大学名誉教授。専門は心の哲学であり、特に「心の理論」や「意識の哲学」に関する研究で知られています。
東京大学大学院総合文化研究科で教鞭を執り、多くの学生を指導するとともに、哲学と認知科学を結びつけた先駆的な研究を展開してきました。
著書には『心の哲学』や『クオリアと心の哲学』などがあり、国内外で高い評価を受けています。
家庭では読書好きな家族に囲まれ、日常の会話から新たな哲学的洞察を得ることもあるそうです。
覚えるとわかるの違いが未来を変える
「覚える」と「わかる」は、私たちが知識を獲得し活用する上で欠かせない2つのプロセスです。
本書『「覚える」と「わかる」 知の仕組みとその可能性』では、この2つの違いを哲学的・科学的に分析し、AI時代における学び方の未来を示唆しています。
この記事では、「覚える」と「わかる」の本質的な違いを解説し、それぞれがどのように私たちの生活や学びに役立つのかを掘り下げます。
また、AI技術が進化する中で、人間ならではの学び方がどんな可能性を秘めているのかも考察します。
主訴:「覚える」と「わかる」の本質と未来への可能性
本書『「覚える」と「わかる」 知の仕組みとその可能性』の主訴は、
「覚える」と「わかる」という人間の知識プロセスを多面的に分析し、それらがどのように相互補完的に働き、未来の知識社会やAI時代においてどのような可能性を秘めているかを探る点にあります。
著者の信原幸弘氏は、まず「覚える」ことを丸暗記や身体での習得、模倣など多様な形で捉え、それが基礎知識として応用力や創造力の土台となる重要性を強調します。
一方で、「わかる」ことは、情報に意味を与え、因果関係や背景を理解するプロセスとして定義されます。
これら二つは独立しているようでありながら、実際には相互に補完し合い、深い学びや批判的思考力を生み出すと説かれています。
さらに本書では、AI技術との対比を通じて、人間特有の知能が持つ「情動」や「知的徳」の重要性が語られます。
AIが膨大な情報処理能力を持つ一方で、人間が持つ文脈理解や批判的思考力、創造性は依然として代替不可能なものであることが示されています。
この視点から、本書は未来社会における人間の学び方や知識活用法について新たな方向性を提案しています。
読者は、「覚える」と「わかる」の違いを理解することで、自身の学び方を見直し、より深い知識獲得への道筋を見出すことができるでしょう。
【内容を詳しく知りたい方は、次ページをお読みください。】
