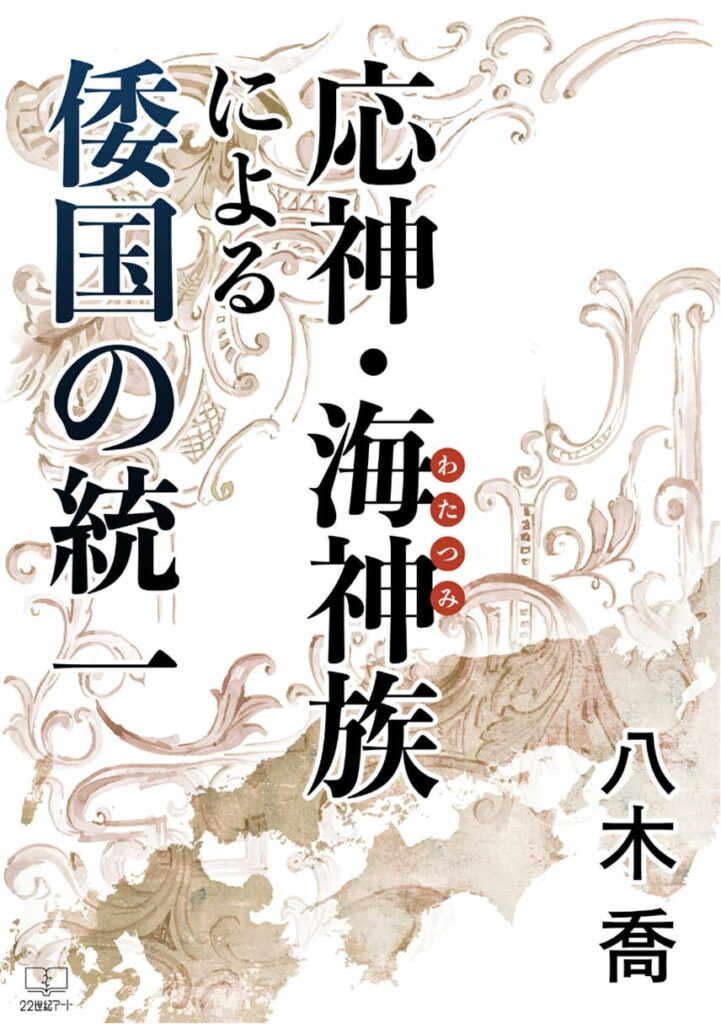
著者 八木喬氏について
八木喬氏は、技術分野と人文科学の両方で活躍する稀有な著作家です。
彼のキャリアは技術解説書の執筆から始まり、日刊工業新聞社から出版された『図解 産業用ロボット導入実践ガイド』などの工学系実用書を多数手がけてきました。
これらの著作では、複雑な技術概念を一般読者にわかりやすく伝える能力の高さが特徴的です。
2010年代半ば以降、八木氏の関心は次第に人文科学へとシフトし、2015年に『大伴家持と万葉の歌魂』を刊行。この著作では、万葉集編纂に果たした大伴家持の役割を再検証し、従来の文学史観を補完する新解釈を提示しました。技術者として培った論理的思考を歴史分析に応用する手法が注目を集めています。
2024年の主著『応神・海神族による倭国の統一』では、日本古代史の「空白の4世紀」に光を当てる野心的な試みがなされています。
今では、ほぼ否定されている騎馬民族王朝説の問題点を指摘しつつ、海を媒介とした文化交流が倭国統一に及ぼした影響を詳細に論証しています。
特に『魏志倭人伝』の記述を再解釈し、朝鮮半島南部と日本列島を結ぶ海上ネットワークの存在を浮き彫りにした点が画期的です。
本書の概要
本書「応神・海神族による倭国の統一」は、日本史における「空白の四世紀」に焦点を当てた歴史小説です。
三世紀の邪馬台国と五世紀の「倭の五王」の間に位置するこの時代は、記録が乏しいものの、近年の発掘調査から日本が神話時代から歴史時代へ移行し、天皇制の萌芽が現れた重要な時期だと考えられています。
著者は江上波夫の「騎馬民族王朝説」に着想を得つつも、考古学的に批判されている点を修正し、「海神族(わたつみぞく)」という新たな概念を提示しています。
これは朝鮮海峡を船で往来する倭集団のことで、彼らが倭国統一と天皇制成立の担い手になったという仮説です。
具体的には、四世紀頃に朝鮮半島南東端の任那に住み、九州・西日本との間を船で往来していた人々が、ホムダワケ(後の応神天皇)を擁する一団となって列島に渡り、難波・河内に拠点を置いて先進的な製鉄技術や農地造成技術を広め、任那との絆を強めながら統一ヤマト王朝を形成していったとしています。
応神天皇(ホムダワケ)の実在性について
本書では、ホムダワケ(応神天皇)が百済で育ったという衝撃的な設定が描かれていますが、これは歴史的事実というよりは著者の創作と考えるべきでしょう。
実際の学術界では、応神天皇の実在性についてはいまだに議論が分かれています。
歴史学者の井上光貞は応神天皇を「確実に実在をたしかめられる最初の天皇」と位置づけ、『記紀』に記された事跡の具体性や朝鮮の史書との一致を根拠としています。
吉村武彦も応神天皇の実在性を支持し、新羅や百済を含む広範な領土支配の可能性を強調しています。
一方で、岡田英弘や直木孝次郎らは応神天皇を神格化された存在とみなし、実在を否定しています。
岡田は『日本書紀』の応神天皇紀を分析し、すべての説話で応神が主役ではなく脇役でしかないことから、元々あった説話に架空人物の応神をはめ込んだと主張しています。
近年の考古学の進展、特に年輪年代学の発達により、応神天皇陵とされる誉田御廟山古墳から出土した木材や埴輪の年代が5世紀第一四半期(401年頃、前後60年の誤差あり)と判明しました。
これは応神天皇の推定年代と一致するため、考古学者の白石太一郎は応神天皇の実在性を支持しています。
また「応神新王朝説」という見方もあり、特殊な出生伝承や前代の仲哀天皇の実在可能性の低さから、応神天皇をそれ以前の皇統とは無関係な人物と考え、新たに興った王朝の創始者とする説があります。
この王朝は河内に宮や陵を多く築いていることから「河内王朝」、また「ワケ」の名がついた天皇が多いことから「ワケ王朝」などと呼ばれています。
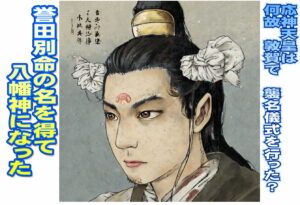
百済との関係
本書では、ホムダワケ(応神天皇)が百済で育ったという設定が描かれていますが、これは史実というよりも著者の創作です。
しかし、実際の歴史資料からも応神天皇と百済の密接な関係は確認できます。
『日本書紀』によれば、応神天皇の治世に百済から王子・直支(のちの腆支王(てんしおう)が人質として倭に派遣されたとされています。
また、百済からは絹衣工女や阿直伎(あちき)、王仁(わに)といった技術者も派遣され、先端技術や文化の伝来に貢献したとされています。
『三国史記』や『広開土王碑』によれば、4世紀末から5世紀初頭にかけて、百済と倭は同盟関係にあり、高句麗に対抗するために共同で軍事行動を行っていたことが記されています。
特に397年には、百済が内密に倭との連携を深めるため、太子・直支を人質として倭に派遣したとされています。
これらの史料から、応神天皇の時代に百済と倭の間に密接な関係があったことは確かですが、応神天皇自身が百済で育ったという記録は残されていません。
本書の設定は、この歴史的背景をもとに著者が創作した物語と考えるべきでしょう。
著者は近年の考古学的発掘成果と朝鮮半島の動向を組み合わせ、従来とは異なる歴史の流れを描き出そうとしています。
また、登場人物の呼称については、天皇号などを使うと予定調和的な話になるため、適当な時期まで通称(ホムダワケなど)を用いる工夫をしています。
本書は空想の羽を広げつつも、実証的な研究成果に基づいた新たな古代史像の構築を試みる挑戦の書です。
第一部:百済で成長する若き人質ホムダワケ
本書の第一部では、任那の王子ホムダワケ(後の応神天皇)が百済に人質として送られ、そこで成長していく物語が展開されています。
この設定自体が非常に斬新で、教科書では決して語られることのない応神天皇像が描かれています。
物語は、朝鮮半島南部の小国・任那の王子ホムダワケが、父ナカツヒコ王に連れられて百済へ向かうところから始まります。
実は
この書では百済と任那の同盟関係において、任那が百済から鉄鋌(てってい:短冊形の鉄素材)を得る代わりに、ホムダワケを人質として差し出す密約が結ばれていたのです。
当時の「人質」は現代のイメージとは異なり、国家間の信頼関係を築くための外交手段であり、王族の子どもが相手国で高度な教育を受けながら育つという側面もありました。
百済に着いたホムダワケは、高興博士という学者から教育を受けることになります。
博士は「魏志倭人伝」という中国の歴史書を教材に、倭国(日本の古称)の歴史や地理を教え、これがホムダワケにとって自分のルーツを知る重要な機会となります。
物語が進むと、ホムダワケは百済の皇太子に招かれて鷹狩りに参加し、そこで皇太子の妹ジミレ王女と出会い、互いに好意を抱き始めます。
その後、ホムダワケは谷那鉱山の再開事業に関わることになります。
百済と任那の協定で、百済は任那に鉄鋌を供給することになっていましたが、鉱山の操業がうまくいかなくなっていました。
ホムダワケは任那から鉄の専門家カラノヒボコを招き、製鉄技術の問題点を改善していきます。
物語のクライマックスでは、ホムダワケとジミレ王女の結婚が認められ、盛大な祝宴が開かれます。
百済王から任那王への贈り物として七支刀(しちしとう)が贈られ、両国の同盟関係が強化されます。
この七支刀は実際に日本に現存する国宝で、百済から贈られたものと考えられており、当時の日本と朝鮮半島の関係を示す重要な歴史的証拠です。
結婚後、ホムダワケは妊娠したジミレ王女と共に任那へ帰国することになります。
百済での経験と学びを胸に、新たな使命感を持って故郷へ戻るのです。
第一部を通して、ホムダワケが百済で様々な経験を積み、知識を身につけ、人間的にも成長していく姿が描かれています。
特に高興博士から学んだ中国の政治や文化、カラノヒボコから学んだ製鉄技術などは、後に彼が日本で国づくりをする際に大いに役立つことになります。
また、百済と任那の同盟関係や、朝鮮半島の複雑な国際情勢も描かれており、当時の東アジアの状況がよくわかる内容となっています。
ちなみに、応神天皇(ホムダワケ)が百済から妃を迎えたという記録は、『日本書紀』や『古事記』には記されていません。
応神天皇の妃については、仲姫命(なかつひめのみこと)を皇后として立てたことが知られていますが、彼女は景行天皇の曾孫であり、百済とは関係ありません。
妃はほかにも数人いましたが、どの方も百済出身の姫はいませんでした。
第二部:倭の拠点・難波の開発
第二部では、ホムダワケが任那から倭(日本)へ渡り、難波(現在の大阪)を拠点として国づくりを進めていく物語が展開されます。
まず、ホムダワケ一行は玄界灘(げんかいなだ)を越えて倭へ向かいます。
キビツヒコ(吉備氏の祖)という人物が新型船を開発し、狗弥国の勢力圏を避けて北九州の岡ノ湊へ直接行ける航路を開拓しました。
玄界灘は九州の北側にある海域で、昔から海が荒れることで知られており、船での航海は命がけでした。
途中、洞ノ海(とのうみ)沿いに狗弥国が新羅から馬を運び牧を作っていることを知ります。
これは後の物語で重要な意味を持ってきます。
牧は馬を育てる場所で、馬を持つことは軍事力を高める重要な要素だとしています。
難波に到着したホムダワケは、葛城ソツヒコと一緒に葛城へ向かい、各地から集まった若者たちと難波での国づくりについて話し合います。
物部麦入は物部氏の神事における役割を、尾張尾綱根は尾張の歴史と洪水対策の必要性を語ります。
物部氏は古代日本の有力氏族で、神事(神様に関する儀式)を担当していました。
土師兎(はじのうさぎ)は洪水対策と干拓技術について説明しますが、これが難波の国づくりの核心部分となります。
干拓とは、湿地や浅い海を埋め立てて陸地にする技術のことで、当時の土木技術の中でも高度なものでした。
また、日向(ひゅうが・今の宮崎県)の諸県君は海人族(あまぞく・海で暮らす人々)の立場から協力を申し出ます。
ホムダワケは日向へ行き、諸県君の娘・泉長媛と結婚することになります。
難波での堀江(ほりえ)開削工事が始まると、秦理成と土師八嶋が測量を担当し、大伴武以と秦頼直が掘削工事を指揮します。
堀江とは、河内湖(かわちこ・今の大阪平野にあった湖)と海をつなぐ運河のことで、洪水対策と船の通行路として重要でした。
そんな中、オオサザキ(後の仁徳天皇)が工事現場で働き始めますが、突然の大洪水で工事が中断してしまいます。
秦理成は淀川から河内湖への流入を止める「茨田の大堤」(まんだのおおつつみ)工事を優先すべきと提案します。
オオサザキは人柱として武蔵の強頸(むさしのこわくび)と河内の茨田連衫子(まんだのむらじころもこ)を立てることで工事を進めます。
これは当時の人々の信仰心を表す重要なエピソードです。
人柱とは、工事がうまくいくように人を生贄にする古代の風習で、実際にあったかどうかは議論がありますが、当時の人々の自然に対する畏怖の念を示しています。
堀江が完成すると、河内湖の水面が下がって広大な土地が生まれます。
オオサザキは民が豊かになるまで宮殿を建てず、簡素な望楼を建てるという質素な姿勢を見せます。
そんな中、ホムダワケは突然の呼び出しを受けて任那へ戻ることになります。
任那では皇太子が死去し、その子オオヤマモリが自害したため、ナカツヒコ王は引退してホムダワケに王位を譲ろうとしていたのです。
ホムダワケは難波の事業をオオサザキに任せて、任那へ戻って王位を継ぐことになります。
大胆な発想力ですね。
第二部では、難波での国づくりの過程と、そこに関わる様々な人物の役割が描かれています。
特に洪水対策や土地開発といった土木事業が中心となっており、当時の人々がどうやって自然と向き合い、住みやすい環境を作っていったのかがよくわかります。
また、オオサザキの登場によって、後の物語の展開も予感させる構成となっています。
この物語を通して、古代日本と朝鮮半島の関係がとても密接だったことがわかりますし、今の大阪がどうやって発展してきたのかも想像できます。
歴史の教科書ではあまり詳しく教えてくれない部分ですが、実は日本の国の成り立ちを考える上でとても重要な時代なのです。
第三部:海神族による統一倭国家
第三部では、朝鮮半島での苦難を経て倭へ渡った蘇我満智の活躍から始まり、オホサザキ(仁徳天皇)から雄略天皇の時代を経て、継体天皇による統一ヤマト王朝の成立までが描かれています。
蘇我満智は百済の役人として高句麗との戦いに参加し捕虜となりますが、奇妙な巡り合わせで「倭の遣使」として東晋へ派遣されるという経験をします。
その後、任那へ移り住み、やがて倭へ渡って新たな生活を始めます。
満智は渡来人の組織化に尽力し、「今来の人」と呼ばれる新たな渡来人を旧来の渡来人集団の上に立たせ、朝廷との窓口として機能させました。
一方、オホサザキ王は和邇博士から中国の始皇帝について学び、倭の統一を目指します。
難波の堀江工事が完成し、河内湖の水面が下がって広大な土地が生まれました。
オホサザキは民が豊かになるまで宮殿を建てず、簡素な望楼を建てるという質素な姿勢を見せました。
オホサザキの子ワカタケル(雄略天皇)は、父の死後、皇位継承をめぐって争いを起こし、多くの皇族を殺害します。
雄略は高句麗の南下に対抗するため、宋へ遣使して支援を求めました。
宋の順帝に送った上表文は見事な漢文で書かれ、倭が朝鮮半島の諸国を征服したと誇示しました。
480年、雄略は葛城山で一言主神と出会い、その後亡くなります。
死の直前、草香幡杼皇后(くさかのはたびのひめみこ)、白髪皇子(清寧天皇)、物部荒甲(麁鹿火)、大伴金村に後事を託しました。
大伴金村は吉備の稚妃と星川皇子を殺害し、吉備へ兵を送って完全に制圧しました。
吉備は備前・備中など小国に分割されました。
白髪皇子は病弱で子を持たず、履中天皇の血筋である市辺忍歯皇子の子・億計王(仁賢天皇)が雄略の娘・春日大娘と結婚し、仁賢天皇として即位しました。
物部荒甲は出雲を戦わずに配下に収めるため、白髪王の考えた「倭全体が共有できる神」の構想を携えて出雲を訪問しました。
スサノオとアマテラスを中心とする神話体系を提示し、出雲を説得することに成功しました。
大伴金村は近江のヲホド王(継体天皇)を見出し、仁賢天皇の後継者として擁立します。
ヲホド王(継体天皇)は各地の豪族を従え、磐井の乱(527年~528年)を鎮圧して九州を制圧しました。
朝鮮半島では百済が高句麗に敗れて漢城を失い、熊津へ遷都します。
継体天皇は百済の要請を受けて任那の一部を割譲することを承認しました。
百済はその見返りとして仏教を倭に伝え、経典や仏像を送りました。
継体天皇の死後、朝鮮半島の権益損失の責任を巡って大伴氏が追放され、物部氏と蘇我氏の間で宗教戦争が勃発します。
最終的に蘇我氏が勝利し、仏教の国教化が進められました。
こうして応神天皇から継体天皇に至る過程で、倭の統一が実現したのです。
本書は、海を媒介とした文化交流が倭国統一に及ぼした影響を詳細に論証しています。
特に「海神族」という概念を提示し、朝鮮海峡を船で往来する倭集団が倭国統一と天皇制成立の担い手になったという仮説は、従来の陸路中心史観を転換する試みとして注目に値します。
また、朝鮮半島と日本列島の関係が今よりもずっと密接であったことを示し、日本の国家形成過程について新たな視点を提供しました。
本書の評価
私自身の評価
本書『応神・海神族による倭国の統一』は、歴史小説としての魅力と歴史書としての限界を併せ持つ作品です。
物語としての魅力については、古代日本と朝鮮半島の関係を生き生きと描き出している点が特筆に値します。
ホムダワケ(応神天皇)が百済で育ったという斬新な設定から始まり、難波の開発、海を通じた交流など、教科書では語られない古代史の姿を臨場感たっぷりに描いています。
特に、登場人物たちの人間関係や心情描写が丁寧で、古代という遠い時代を身近に感じさせる力があります。
また、堀江の開削工事や茨田の堤の建設など、古代の土木事業の様子も具体的に描かれており、当時の技術や人々の暮らしぶりを想像する手がかりになります。
物語の展開も、ホムダワケから始まり、オオサザキ、雄略、そして継体天皇へと続く長い時間軸の中で、日本の国家形成過程を壮大なスケールで描いています。
しかし史実との整合性という点では、残念ながら評価は低くならざるを得ません。
応神天皇が百済で育ったという説は、学術的には全く支持されていません。
また「海神族」が倭を統一したという概念も著者の創作であり、史料的根拠に乏しいものです。
騎馬民族王朝説の亜流とも言える本書の歴史観は、考古学的な裏付けが不十分であり、歴史書としては2〜2.5点程度の評価が妥当でしょう。
一方で独自性と創造性については高く評価できます。
「空白の4世紀」に光を当て、海を媒介とした文化交流という視点から日本の国家形成を描こうとする試みは斬新で面白かったです。
特に、従来の陸路中心の歴史観を転換し、海上ネットワークの重要性を強調する点は、今後の古代史研究にも一石を投じる可能性を秘めています。
ネット上の評価
ネット上には、残念ながら評価が見当たりませんでした。
アマゾンの書評でも、評価者は2人で、5点と3点で、総合4点。
このお二人の評価から考えると、学術的観点からは、本書はやはり厳しい評価を受けたようです。
歴史学者や考古学者からは「史料批判が不十分」「考古学的証拠との整合性に欠ける」といった批判が予想されます。
特に応神天皇の百済育ち説は、学術的な裏付けがなく、朝鮮半島との関係を過度に強調しているという指摘を受けるでしょう。
一方で、「日本と朝鮮半島の関係を再考する契機になる」「従来の歴史観に挑戦する姿勢は評価できる」といった肯定的な意見もあるかもしれません。
ただし全体としては、学術書としての評価は低くなると思われます。
一方、小説として本書を見るなら、「読みやすく面白い」「古代史に興味を持つきっかけになった」といった好意的な声が多いのではないでしょうか。
歴史に詳しくないという読者にとっては、物語として楽しめる要素が多く、古代の日本と朝鮮半島の関係を想像する手がかりになるでしょう。
小説として読むなら4点から4.5点くらいの評価は得られるのではないでしょうか。
また「朝鮮半島との関係をこれほど密接に描いた点が新鮮」「難波の開発や古代の土木事業の描写が興味深い」といった点も、読者に評価されるでしょう。
総じて言えば、本書は歴史書としてよりも歴史小説として読むべき作品です。
史実との整合性には疑問が残りますが、古代日本の国家形成過程を想像力豊かに描いた点は評価できます。
歴史的小説としては史実を丁寧に取り入れ、そこからの発想力を生かした独自の視点を盛り込んでいて、確かに斬新で面白かったです。

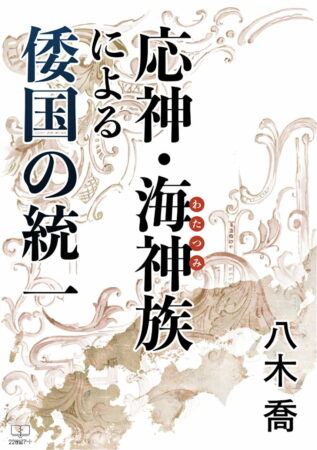

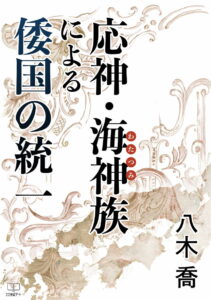
コメント