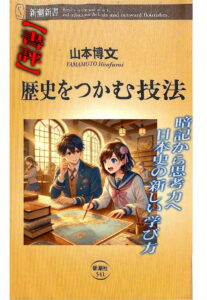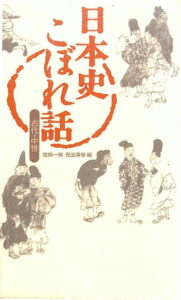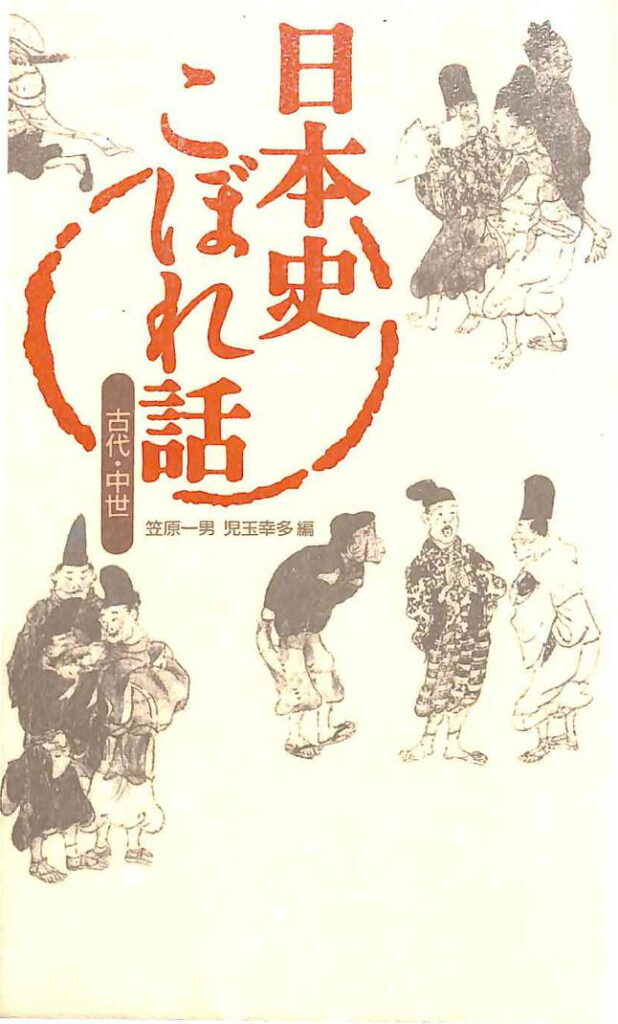
1. 著者紹介
笠原一男(かさはら かずお)
1916年6月2日長野県南佐久郡北牧村(現小海町)生まれ、2006年8月19日没(90歳)。
旧制千葉県立東葛飾中学校、旧制新潟高等学校を経て、1941年東京帝国大学文学部国史学科卒業。
東京帝国大学史料編纂所に勤務し、1960年助教授、1966年教授に就任。
1977年定年退官後は放送大学教授(1990年退任)、日本文化研究所長などを歴任。
1962年「一向一揆の研究」で文学博士号取得。
専門は日本中世宗教史(鎌倉仏教)。
『親鸞と東国農民』『一向一揆の研究』『蓮如』『女人往生思想の系譜』『親鸞と蓮如』など多数の著書がある。
一向一揆研究では宗教運動と社会経済的背景の関連を体系的に分析し、中世史研究に大きな影響を与えた。
児玉幸多(こだま こうた)
1909年12月8日長野県更級郡稲荷山町(現千曲市稲荷山)生まれ、2007年7月4日東京都武蔵野市没(97歳)。
旧制東京府立第二中学、旧制成蹊高等学校を経て、1932年東京帝国大学文学部国史学科卒業、同大学院に進学。学習院大学教授として長年勤め、学習院大学学長・学習院女子短期大学学長を歴任。
品川区立品川歴史館名誉館長、千曲市名誉市民の称号を授与された。
「日本近世農村・交通史の泰斗(第一人者の意)」と称され、近世史研究、特に農村史と交通史の分野で顕著な業績を残した。
生まれ故郷が北国街道と北国西街道の合流点という交通の要衝だったことが、交通史研究への関心に影響したとされる。
両氏は共著として『日本史こぼれ話(古代・中世)』(1993年3月、山川出版社)を出版。このシリーズは続編・続々編・final版と展開され、歴史教育に大きく貢献している。
2. 本の要約と特徴
本書『日本史こぼれ話』は、古代から近世にかけての日本史に関する興味深いエピソードや逸話を集めた一冊です。
全20章から構成され、各章では特定のテーマや時代に焦点を当てて、通常の歴史教科書では触れられないような細部にまで踏み込んだ解説が展開されています。
本書の内容を大まかに要約すると以下のようになります:
- 古代:縄文時代から平安時代までの話題を取り上げ、考古学的発見や神話・伝承の解釈、貴族社会の実態などを紹介しています。
◇ - 中世:鎌倉時代から室町時代にかけての武士社会の成立と発展、宗教の役割、庶民の生活などについて述べられています。
◇ - 近世:江戸時代の政治・経済・文化に関する様々な逸話が紹介され、幕藩体制下での社会の実態に迫っています。
◇ - 文化史:各時代を通じての文化や芸術の発展、庶民の娯楽、食文化などにも焦点が当てられています。
◇ - 人物史:歴史上の著名人物だけでなく、一般庶民の生活や思想にも光を当て、多角的な視点から歴史を描き出しています。
本書の特徴として、以下の点が挙げられます:
1 豊富な史料と最新の研究成果に基づいた記述:
著者らの長年の研究蓄積を活かし、一次史料の丁寧な解読と最新の研究成果を反映した内容となっています。これにより、従来の通説を覆すような新しい歴史解釈も随所に提示されています。
例えば、銅鐸の絵画(香川県出土)について、従来の単なる祭器としての解釈を超え、横帯の区切りを水として上下に描かれた絵を解釈し、銅鐸が当時の人々の世界観を表現したメディアであったという新しい視点を提示しています。
また、飛鳥寺の本尊に関しても、『日本書紀』の記述を考古学的発掘調査の結果と照らし合わせて批判的に検討しています。
2 わかりやすい文体と構成:
専門的な内容でありながら、平易な文体で書かれており、一般読者にも理解しやすい構成となっています。各章の冒頭には導入的な説明があり、徐々に深い内容へと進んでいくため、歴史に詳しくない読者でも無理なく読み進められます。
3 多角的な視点からの歴史叙述:
政治史や軍事史だけでなく、社会史、文化史、経済史など多様な側面から歴史を描き出しています。また、支配者層だけでなく庶民の視点も取り入れることで、立体的な歴史像を提示しています。
例えば、飛鳥寺の建設に関する記述では、貴族の政治的背景だけでなく、当時の庶民がどのように寺院建設に関与したかを考古学的発見と文献を基に描いています。
また、鎌倉材木座から発見された人骨の分析を通じて、新田義貞の鎌倉攻めという軍事的事件だけでなく、戦闘が庶民の日常生活に与えた影響にも言及しています。
このように、多様な視点から歴史を描き出すことで、立体的で奥行きのある歴史像を提示しています。
4 興味深いエピソードの紹介:
タイトルの通り「こぼれ話」的な逸話や裏話を多数紹介しており、読者の興味を引きつける工夫がなされています。これらのエピソードは単なる娯楽に留まらず、その時代の社会や文化を理解する上で重要な示唆を与えてくれます。
例えば、飛鳥寺の仏像搬入時のエピソードでは、丈六の仏像が金堂の扉を通らず困った際、鞍作止利が扉を壊さずに搬入する方法を工夫したという話が紹介されています。
これは当時の技術力や工人の知恵を示す逸話として興味深いです。
また、平清盛が白河法皇の皇胤である可能性についても触れられています。
滋賀県胡宮神社で発見された系図を根拠に、清盛の異例の出世が貴族社会で認知されていた背景を解説し、歴史的な真相に迫っています。
このようなエピソードは、単なる娯楽に留まらず、その時代の社会や文化を理解する手がかりを提供しています。
5 図版・写真の効果的な使用:
本文の理解を助けるために、関連する絵画資料や考古学的出土品の写真、地図などが適切に配置されています。これにより、読者はより具体的にその時代の様子をイメージすることができます。
6 現代との接点の提示:
過去の出来事と現代社会とのつながりにも言及しており、歴史を学ぶ意義を読者に感じさせる工夫がなされています。現代の慣習や言葉遣いの起源を古代・中世に遡って解説するなど、読者の日常生活と歴史との接点を示しています。
例えば、「左遷」という言葉について、中国の古代思想における「左は軽んじられる」という価値観が日本にも伝わり、役職を下げたり地方に転任させることを意味するようになった経緯を説明しています。
また、「元号」の制度についても、大化から令和まで続く元号の歴史を通じて、現代日本が唯一この制度を維持している背景を紹介し、文化的連続性を示しています。
このような記述は、日常生活に根付いた慣習や言葉の由来を理解する手助けとなり、歴史が現代に与えた影響を実感させます。
7 神話や伝承の再解釈:
従来は史実として扱われてこなかった神話や伝承についても、その背景にある歴史的事実や社会状況を丁寧に分析しています。これにより、神話や伝承の新たな解釈の可能性を提示しています。
8 地域史の重視:
中央の動向だけでなく、各地方の歴史にも目配りしており、地域ごとの特色ある歴史の展開を描き出しています。これにより、日本史の多様性と豊かさを浮き彫りにしています。
9 女性史への着目:
従来の歴史書では軽視されがちだった女性の役割や地位について、各時代を通じて丁寧に解説しています。これにより、より包括的な歴史像を提示することに成功しています。
10 歴史の連続性と断絶性の指摘:
各時代の特徴を明確に示しつつ、時代を超えて連続する要素にも注目しています。これにより、日本史の全体像をつかむ手がかりを読者に与えています。
これらの特徴により、本書は単なる歴史の概説書を超えて、読者に新たな歴史観を提示し、歴史を学ぶ楽しさを伝える役割を果たしています。
3. 本書の評価
★★★★☆(4つ星)
本書『日本史こぼれ話』は、古代から近世にかけての興味深いエピソードを豊富に収録した良書です。
児玉幸多・玉原司両氏の深い学識に基づき、教科書には載らない逸話や裏話を通じて日本史の多面的な理解を促しています。
特に図版や写真が効果的に使用され、読者の理解を助けています。
ただし、一部の時代に記述が偏っている点や、学説の対立についての言及が少ない点が惜しまれます。それでも歴史を学ぶ楽しさを伝える優れた一冊といえるでしょう。
これらの点を考慮しても、本書は総合的に見て非常に優れた歴史書であると評価できます。
学術的な価値と一般読者への啓蒙的価値を両立させた点、多角的な視点から日本史を描き出している点、そして何より歴史を学ぶ楽しさを伝えている点において、高く評価されるべき一冊です。
歴史に関心のある一般読者はもちろん、歴史教育に携わる教員、さらには歴史研究者にとっても、新たな視点や発見を与えてくれる貴重な著作であると言えるでしょう。
本書を通じて、読者が日本の歴史に対する理解を深め、さらなる探究心を喚起されることを期待します。