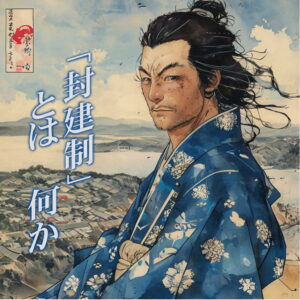著者紹介
『封建制の再編と日本的社会の確立』の著者、水林彪(みずばやし たけし)氏は、日本法制史を専門とする歴史学者です。
1947年生まれで、東京都立大学名誉教授および早稲田大学名誉教授を務めました。
日本中世から近世にかけての法制度や社会構造の研究において高い評価を受けており、著書には本書をはじめ多くの重要な研究成果が含まれています。
本全体の概要
本書は、16世紀戦国時代から19世紀中葉の明治維新直前までの約400年間を対象に、日本社会の変遷を「封建制の再編」と「日本的社会の確立」という二つの視点から描き出しています。
「封建制の再編」では、戦国大名権力の形成から始まり、織田信長や豊臣秀吉による統一権力を経て、徳川幕府による幕藩体制が確立される過程が詳述されています。
この過程では、封建的土地所有制度や兵農分離といった政策が社会構造にどのような影響を与えたかが分析されています。
「日本的社会の確立」では、西欧や中国とは異なる独自の社会構造が形成され、日本的な法観念や国家観が発展したことが議論されています。
特に、村落共同体や「イエ」の制度が近代日本社会に与えた影響についても触れられています。
本書は、政治・経済だけでなく、文化・宗教・法制度など多様な側面から歴史を分析し、新しい近世史像を提示するものです。
本書が示した「新しい近世史像」とは
「新しい近世史像」とは、従来の歴史学の枠組みを超え、近世日本の社会とその変遷を多面的かつ総合的に捉え直す視点を指します。
具体的には以下のような特徴が挙げられます。
1. 封建制の再編
本書では、戦国時代から幕藩体制に至る過程を「封建制の再編」として位置づけています。
この再編には二つの側面があります:
- 戦国大名から幕藩体制への転換
戦国大名権力が織田信長や豊臣秀吉の統一権力を経て、徳川幕府による中央集権的な幕藩体制に再編される過程が描かれています。この過程では、「兵農分離」や「石高制」の導入など、封建制を強化する政策が実施されました。
◇ - 封建制の質的変化
幕藩体制下での封建制は、中世的な地域分権型から、より中央集権的で統一的な形態へと変容しました。これにより、農村や都市社会が再編成され、新たな社会秩序が形成されました。
2. 日本的社会の確立
本書は、西欧や中国と比較しながら、日本独自の社会構造が形成されたことを強調しています。
この「日本的社会」とは以下を指します。
- 村落共同体と「イエ」制度
村落共同体や「イエ」(家)という基盤的な社会単位が形成され、これが近代日本社会にまで影響を及ぼしました。これらは農業生産や地域社会の安定に寄与すると同時に、個人よりも集団を重視する価値観を育んだとされています。
◇ - 法観念と国家観
幕藩体制下で形成された法観念(例:国家による命令としての法)や国家観(中間団体を介した統治構造)は、近代日本にも引き継がれました。

今でも、日本人の魂の、根っこの部分に
残っていると思う。
3. 多面的・総合的な視点
従来の近世史研究では、政治・経済・文化など各分野が分断して論じられることが多かった一方、本書ではこれらを統合し、一貫性ある歴史像を提示しています。その際、以下のような要素が重視されています。
- 地域ごとの多様性
畿内近国(京都・大阪周辺)など先進地域と、それ以外の周辺地域との発展段階の差異が詳細に分析されています。
◇ - 民衆の視点
支配層だけでなく、農民や町人など一般民衆の日常生活や文化も重視されており、彼らが歴史に果たした役割が評価されています。
◇ - 比較史的アプローチ
西欧や中国との比較を通じて、日本独自の発展モデルやその特質が浮き彫りにされています。
4. 現代への示唆
本書は単なる歴史記述に留まらず、現代日本社会の特質(例:集団主義、中間団体依存型の国家運営)の歴史的起源を解明する試みでもあります。
このような視点は、日本社会を理解するうえで重要な示唆を与えています。
以上のように、「新しい近世史像」とは、日本近世史を従来以上に多面的かつ総合的に捉え直し、その独自性と現代への連続性を明らかにする試みであると言えます。
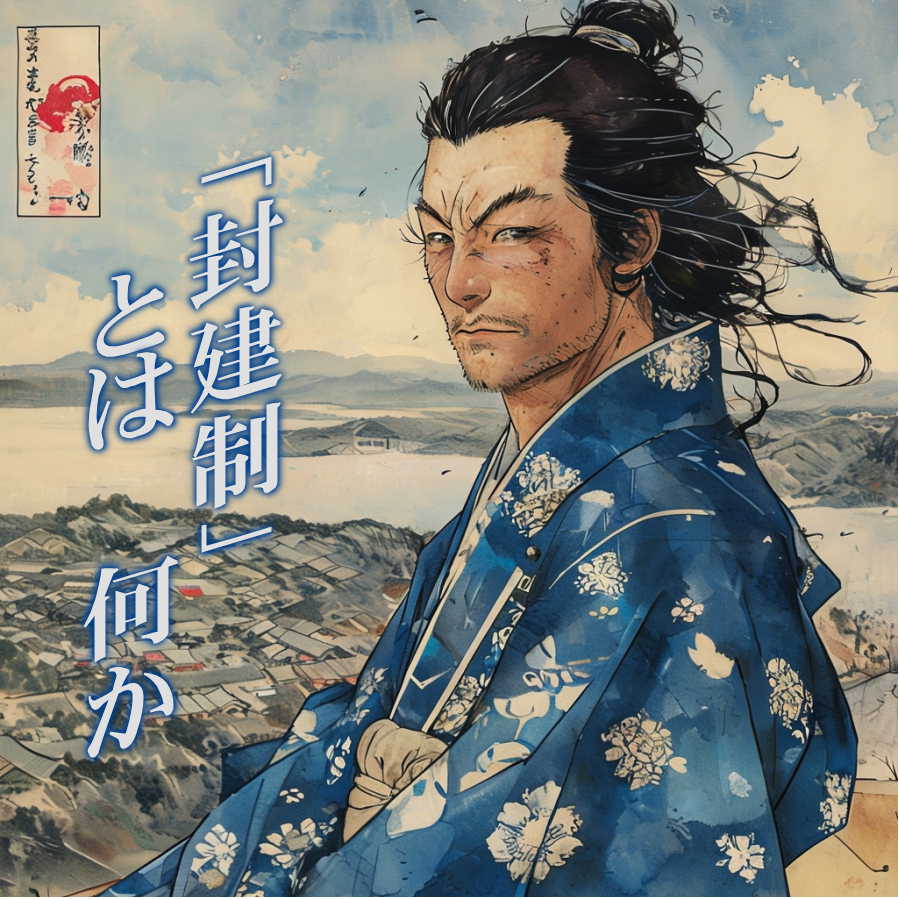
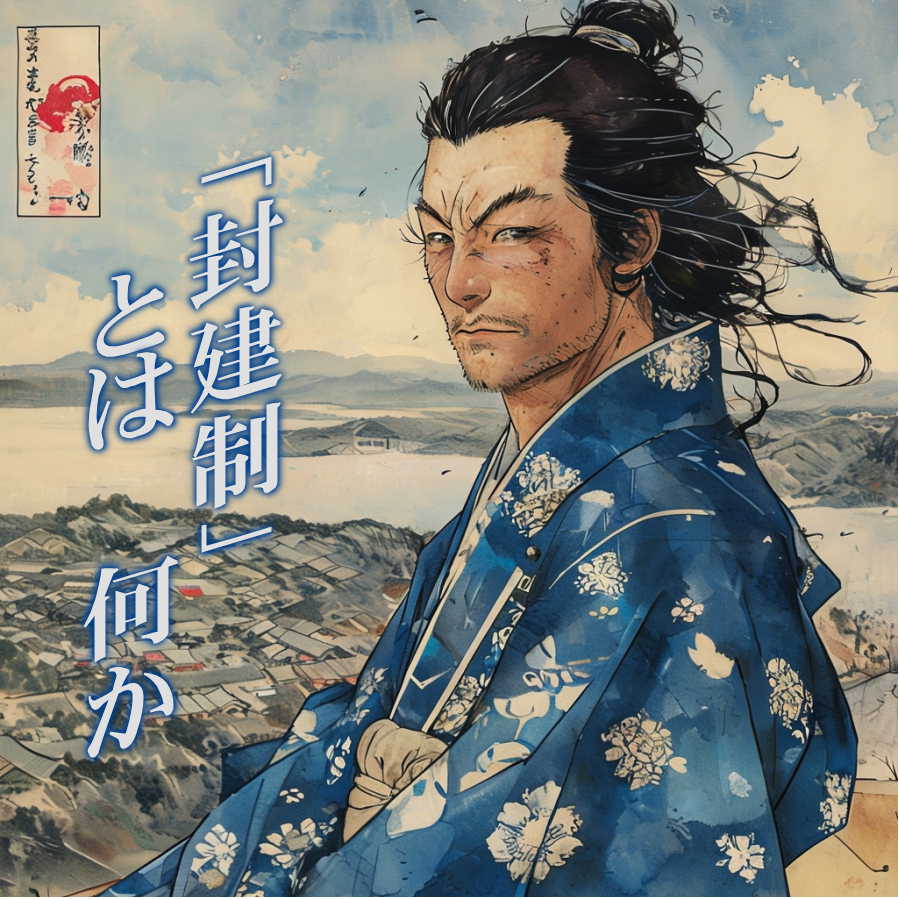
まとめ:封建制がどのように再編されたのか
以前の日本の封建制の認識
- ヨーロッパ史との比較
日本の封建制は、ヨーロッパ中世の封建制(feudalism)と類似点を持つとされ、土地を基盤とした主従関係や荘園制がその特徴とされた。
◇ - マルクス主義的視点
マルクス主義歴史学では、封建制を「経済外的強制」による農奴制と捉え、日本の江戸時代までを封建社会と位置づけた。
◇ - 中世史と近世史の対立
鎌倉・室町時代を封建制とする中世史学の通説と、織田信長や豊臣秀吉以降に封建制が成立したとする近世史学が対立していた。
本書による「封建制の認識」の再編
- 再編成の視点
戦国大名権力から幕藩体制への移行を「封建制の再編」と位置づけ、単なる継続ではなく質的な変化として捉えた。
◇ - 日本独自の封建制
西欧や中国とは異なる、日本独自の封建的社会構造(兵農分離や村落共同体)を強調し、その特質を解明した。
◇ - 多面的な分析
封建制を政治・経済だけでなく、文化・宗教・法制度など多角的に分析し、従来の単線的な歴史観を超えた。
◇ - 近世史像の再構築
封建制を中世から近世への移行過程として捉え直し、戦国期から幕末まで一貫した社会変動として描いた。



現場の教師は、この点で混乱する。
学習指導要領上では、戦国大名権力が織田信長や豊臣秀吉の統一権力成立から
江戸幕府までの、16世紀から19世紀までがひとかたまりとして示されている。
でも、教科書では、「統一権力成立期の項目」と、「江戸時代」の項目は、分かれている。
そこに、混乱が生じる。



歴史学的(文科省的)には、統一権力成立期の封建制と
江戸時代期の封建制は、質的に変質するけど、
「封建制を基盤とした時期」だということを踏まえてほしいと、意図している。



だけど、教科書では、統一権力成立期と江戸時代が、別項目になっているので、
多くの教師は、その意図に気づけないよ。
封建制《時代区分も含めて)については、まだまだ議論が続くのだろうと思います。
しかし、現時点では、この本の解釈が有力説のようです。
大変に参考になる本でした。



社会科教師は、一読を是非お勧め!!!