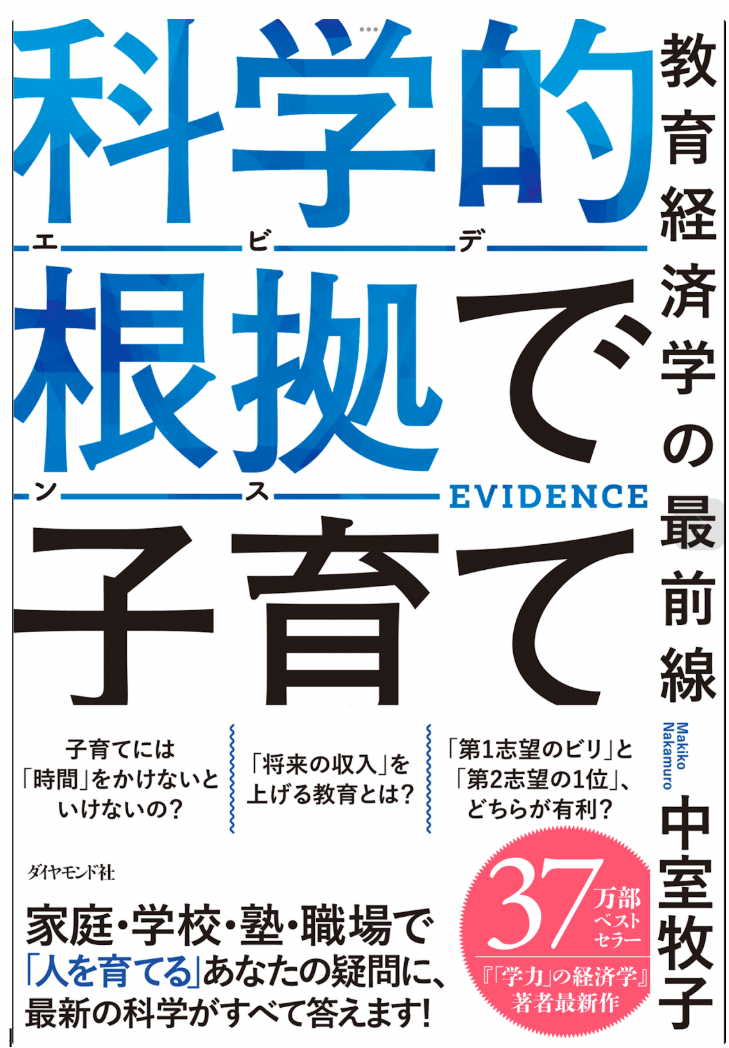
中室牧子氏の著書『科学的根拠で子育て』は、教育経済学の視点から、エビデンスに基づいた子育てや教育の実践方法を提案する一冊です。
筆者は、教育や子育ての成果を科学的データで分析し、短期的な学力向上だけでなく、長期的な成果や非認知能力(忍耐力、自制心、やり抜く力など)の重要性を強調しています。
特に、スポーツやリーダーシップ経験が将来の収入や幸福感に与える影響を具体例とともに解説し、「学校内での成功」よりも「卒業後の人生で役立つ力」を育てることが大切だと述べています。
また、親の時間投資や教育環境の質が子どもの成長に与える影響についても触れ、幼少期には親が積極的に関与し、その後は子ども自身の努力が重要になると指摘。
さらに、日本の教育政策にも言及し、「幼児教育無償化」や「1人1台端末政策」などの課題を挙げつつ、エビデンスに基づいた政策形成(EBPM)の必要性を訴えています。
本書は、「エビデンス」の活用方法について注意点を示しながら、科学的根拠をもとにした柔軟な子育て・教育の実践を提案している良書です。
親や教育者が直面する課題への理解を深めるとともに、より良い意思決定を行うためのヒントが満載です。
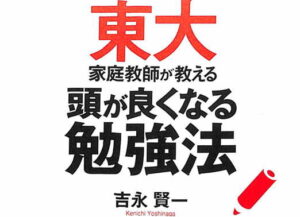
第1章: 将来の収入を上げるために、子どもの頃に何をすべきなのか?(概要)

筆者は、子どもの将来の収入を向上させるために、幼少期に行うべき3つの重要な活動として「スポーツ」「リーダー経験」「非認知能力の向上」を挙げています。
これらは、長期的なキャリア形成や収入増加に寄与する科学的エビデンスに基づいています。
主な内容・主訴のポイント
- スポーツの重要性
スポーツ経験が将来の収入や社会的スキル向上に寄与する。忍耐力やリーダーシップが育まれる点が強調されています。 - リーダー経験の価値
高校時代などでのリーダー経験は、管理職への昇進や収入増加に結びつく。 - 偏差値と収入の関係
偏差値の高い学校への進学が必ずしも将来の収入向上に直結しないことが示されています。
詳しく解説を読みたい方はこちら
スポーツの重要性
スポーツ経験が将来の収入や社会的スキル向上に寄与する理由は、忍耐力やリーダーシップ、責任感といった非認知能力を育む点にあります。
例えば、アメリカの研究では、高校でスポーツ部活動をしていた男子生徒は、卒業後の収入が21.4%高いことが示されています。
これはスポーツ経験が採用時に有利に働き、また体力や精神的な強さを評価されるためです。
具体的には、スポーツを通じて学ぶ自己管理能力や集中力は、仕事の場面でも役立ちます。
例えば、競技中の目標設定や計画的な練習は、職場でのプロジェクト管理や目標達成能力に通じます。
また、チームスポーツではコミュニケーション能力や協調性が養われるため、組織内での円滑な人間関係構築にも寄与することが強調されています。
リーダー経験の価値
高校時代のリーダー経験が特に重視される理由は、この時期に得られるリーダーシップスキルがキャリア初期から中期にかけて大きな影響を及ぼすためです。
例えば、高校で部活動のキャプテンや生徒会長を務めた経験がある人は、卒業後11年後の収入が最大33%高くなるという研究結果があります。
この効果は、小学校や中学校よりも高校時代のリーダー経験が重要視される点に特徴があります。
高校時代は人格形成や社会性の発達が進む時期であり、この時期にリーダーとして他者をまとめたり意思決定を行う経験が、その後の管理職への昇進や収入増加につながりやすいとされています。
また、このリーダーシップスキルは「才能」ではなく「習得可能なスキル」として捉えられています。
偏差値と収入の関係
偏差値の高い学校への進学が将来の収入向上に必ずしも直結しない理由には、「学校そのもの」よりも「個人の能力」が収入に影響するという点があります。
研究によれば、高偏差値大学卒業生と中堅大学卒業生で同じ学力水準の場合、収入にはほとんど差が見られませんでした。
これは、偏差値よりも学内順位や自己効力感(自分なら成功できるという感覚)が将来に与える影響が大きいためです。
たとえば、小学校で学内順位が高かった生徒は、中学校以降も学力テストで良好な成績を維持しやすく、それが最終的な収入にも影響することが示されています。
この現象は「井の中の蛙効果」として知られ、自信喪失を防ぐ環境作りが重要だとされています。
補足説明
- スポーツ経験: 競技レベル(地域大会出場程度でも可)よりも、その過程で得た忍耐力や目標達成能力などが評価されます。
- リーダー経験: 高校時代の部活動キャプテン、生徒会役員など具体的な役割を挙げることが重要です。
- 偏差値と収入: 偏差値だけではなく、自分に合った環境で順位を維持することが長期的な成功につながります。
これらの要素から、本書では「科学的根拠」に基づいた教育・子育て戦略を提案しています。
第2章: 学力テストでは測れない「非認知能力」とは何なのか?
学力テストやIQテストでは測定できない「非認知能力」が、将来の収入や幸福感、健康などに大きな影響を与えるとされています。
具体的には忍耐力、自制心、やり抜く力などが挙げられます。
主な内容・主訴のポイント
- 非認知能力の定義と重要性
忍耐力や自制心などは、学力以上に将来の成功を予測する要因となる。 - 非認知能力と長期的成果
非認知能力は中年以降にも重要であり、寿命や結婚生活にも影響を与える。 - 教育投資との関係
幼少期から適切な教育投資を行うことで非認知能力が育まれる。
詳しく解説を読みたい方はこちら
非認知能力の定義と重要性
非認知能力とは、学力テストやIQテストで測れない「忍耐力」「自制心」「やり抜く力」などのスキルを指します。
これらは、計算力や語学力といった認知能力とは異なり、数値化が難しいものの、将来の成功や幸福感に大きく寄与することが多くの研究で示されています。
たとえば、忍耐力は高い学歴や収入に結びつき、自制心は健康や経済的安定に関連し、やり抜く力は仕事や結婚生活の安定をもたらすとされています。
忍耐力・自制心・やり抜く力
- 忍耐力: 目標達成に向けて困難を乗り越える能力であり、学業成績や貯蓄行動、健康的な生活習慣に影響を与えます。
- 自制心: 衝動を抑え、自分の行動をコントロールする能力。薬物依存や借金などのリスクを低減します。
- やり抜く力: 困難に直面しても諦めず努力を続ける能力で、学歴や収入、長期的な成功に直結します[1][3]。
非認知能力と長期的成果
非認知能力は、中年以降にもその重要性が増すことが明らかになっています。
たとえば、「勤勉性」や「外向性」が高い人は、生涯収入が大幅に高くなるだけでなく、寿命も延びる傾向があります。
また、非認知能力は結婚生活の安定や子どもとの良好な関係にも寄与するため、個人だけでなく社会全体にプラスの影響をもたらします。
健康・寿命・家族関係
- 健康: 自制心が高い人は肥満率が低く、飲酒量も少ない。
- 寿命: 勤勉性が高い人は長生きする可能性が高い。
- 家族関係: 非認知能力が高い人は結婚生活が安定し、子どもとの関係も良好です。
教育投資との関係
非認知能力は幼少期から適切な教育投資によって育成可能です。
特に幼児期は「スキルがスキルを生む」という複利的な効果があるため、この時期に投資することで後々の学力や非認知能力の向上につながります。
たとえば、自制心を高めるトレーニングを受けた子どもたちは、その後の学業成績や収入が向上したという研究結果があります。
幼少期の教育投資
- 早期介入: 幼児期における教育投資は、その後の人生全般にわたり大きなリターンを生む。
- 具体例: カナダで行われたトレーニングでは、自制心を高めることで平均年収が20%向上したという結果があります。
補足説明
非認知能力は単なる「性格」ではなく、「育成可能なスキル」として捉えられています。
そのため、家庭環境だけでなく学校教育や社会的プログラムによっても伸ばすことが可能です。
また、日本では埼玉県などで非認知能力を測定する取り組みが進んでおり、この分野への関心が高まっています。
第3章: 非認知能力はどうしたら伸ばせるのか?
音楽、美術、スポーツなど多様な活動が非認知能力を伸ばす効果があるとされています。また、教師や親の影響も大きいことが指摘されています。
主な内容・主訴のポイント
- 学校での取り組み
好奇心を刺激する授業や思いやりを育む教育プログラムが効果的。 - 親と教師の役割
親や教師が子どもとの関わり方を工夫することで、非認知能力を伸ばせる。 - 具体的なプログラム例
トルコで行われた教育プログラムが好奇心と学力向上につながった事例を紹介。
詳しく解説を読みたい方はこちら
学校での取り組み
学校で非認知能力を伸ばすためには、好奇心を刺激する授業や思いやりを育む教育プログラムが効果的です。
非認知能力は学力テストでは測れないものの、将来の成功や幸福感に大きく寄与します。
特に、子どもたちの「好奇心」を引き出す授業や、他者への「思いやり」を育む活動は、学力向上や社会的スキルの発展に寄与します。
好奇心を刺激する授業
- 教材とアクティビティ
例えば、トルコで行われたプログラムでは、「太陽系」について学ぶ際にミステリー調の映像を見せるなど、子どもたちの興味を引き出す工夫が施されました。
これにより、子どもたちは自ら質問し、答えを探す姿勢を養います。 - 効果
このような授業で好奇心が高まった子どもたちは、知識の定着が進み、理科の学力テストで偏差値が約0.8ポイント上昇しました。
この効果は3年後も持続しており、長期的な学力向上に繋がっています。

茨城の教師たち、私の仲間たちが取り組んでいた授業も、まさにこれでした。
親と教師の役割
親や教師が子どもとの関わり方を工夫することで、非認知能力を大きく伸ばせます。
特に、親と教師は子どもたちの日常生活や教育環境において重要な影響力を持っています。
親の役割
- 家庭での習慣作り
親が読み聞かせや家庭内での会話を通じて「好奇心」や「自制心」を育むことができます。 - 例えば、デンマークの研究では、親が子どもの読書習慣を促すことで国語の学力が向上したことが示されています。
教師の役割
- 非認知能力を伸ばせる教師
教員が生徒の「非認知能力」に働きかけることで、高校卒業率や大学進学意欲が向上することが確認されています。 - 特に、生徒との信頼関係を構築し、一人ひとりに適切なフィードバックを行うことが効果的です。
具体的なプログラム例
トルコで行われた教育プログラムは、非認知能力向上の成功例として注目されています。
このプログラムでは、「好奇心」を中心に据えた授業設計が行われました。
トルコのプログラム
- 教材設計
子どもたちに興味を持たせるため、「火星の夜明けは青い」など驚きの情報を含むパンフレットを使用しました。 - これらはトークン(おもちゃ通貨)と交換できる仕組みで、子どもの興味度合い(支払意思額)を測定しました。
- 成果
プログラム実施後、対象校(処置群)の子どもたちは対照群よりも好奇心指数が高まりました。 - また、その結果として理科テストでも偏差値0.8ポイント高い成果を示しました。
補足説明
- 好奇心と学力向上: 好奇心は単なる興味ではなく、新しい知識への探求心として学力向上にも直結します。
トルコでの事例では、この「好奇心」が知識定着と長期的な学力向上に寄与しました。 - 親と教師の協働: 家庭と学校双方から働きかけることで、非認知能力はより効果的に育成されます。
親と教師が連携し、それぞれ異なる角度から子どもたちを支えることが重要です。
第4章: 親は子育てに時間を割くべきなのか?
親による時間投資は子どもの成長に大きな影響を与えます。特に幼少期には時間投資が効果的であり、その質も重要です。
主な内容・主訴のポイント
- 時間投資と年齢
幼少期には親からの時間投資が重要だが、成長するにつれて子ども自身の時間投資が鍵となる。 - 祖父母との同居効果
孫との同居はコミュニケーション力や学力向上につながる場合もある。 - 質と量のバランス
時間の質を高めることで限られた時間でも効果的な教育が可能になる。
詳しく解説を読みたい方はこちら
第4章では、親の時間投資が子どもの成長に与える影響について考察されています。
特に幼少期の時間投資の重要性と、その質が学力や非認知能力の向上にどのように寄与するかが議論されています。
また、祖父母との同居や時間の質と量のバランスについても触れられています。
時間投資と年齢
親による時間投資は、子どもの年齢によってその効果が異なります。
幼少期には親からの時間投資が特に重要で、学力や非認知能力(忍耐力や自制心など)の向上に大きく寄与します。
一方、子どもが成長するにつれて、自分自身で行う時間投資が重要性を増し、親の役割は徐々にサポート的なものへと移行します。
- 幼少期の効果: 3歳時点での親の時間投資は、5歳や7歳時点での認知能力や非認知能力を高める基盤となります。
この効果は持続性が高く、特に非認知能力への影響は70~90%程度持続します。 - 成長後の変化: 11~15歳頃になると、子ども自身の時間投資が学力に与える効果は親を上回るようになります。
また、この時期にはお金による教育投資(塾や家庭教師)が効果を発揮し始めます。
祖父母との同居効果
祖父母との同居は、孫のコミュニケーション力や学力向上にプラスの影響を与える場合があります。
特に祖父母と長期間一緒に過ごすことが学歴向上につながるという研究結果もあります。
- 具体例: フィンランドでは、祖父母と10年間一緒に過ごすことで、高校卒業率が7ポイント上昇することが示されています。
- 注意点: 一方で、祖父母による甘やかしや保育所の代替として利用することには限界があります。保育所や幼稚園と比べて教育的な質が低い場合もあるため、バランスが重要です。
質と量のバランス
親が子どもと過ごす時間は、その「質」が重要です。
単なる受動的な時間(テレビを見るなど)ではなく、本の読み聞かせや会話など能動的な活動が効果的です。
- 質を高める方法: デンマークで行われた実験では、親に「読み聞かせ」の重要性を伝えるパンフレットを配布したところ、子どもの国語テスト偏差値が2.6ポイント上昇しました。
この結果は7か月後も持続しており、時間の質を高めることで短い時間でも効果的な教育が可能であることを示しています。
補足説明
- 幼少期の集中投資: 幼少期には親による能動的な関わり(読み聞かせや遊び)が最も効果的です。この時期に形成された非認知能力は、その後の学力や社会性にも影響を与えます。
- 祖父母との役割分担: 祖父母は親を補完する存在として有効ですが、保育所や幼稚園と同等以上の教育環境を提供することは難しい場合があります。
- 働き方との両立: 共働き世帯では「時間貧困」が課題となりますが、限られた時間でも質を重視した関わり方で十分な成果を得られる可能性があります。
本章では、「量」だけでなく「質」を重視した親の関わり方が子どもの成長においていかに重要であるかを具体例とともに示しています。
第5章: 勉強できない子をできる子に変えられるのか?


勉強習慣を身につけさせるためには、「目標設定」「習慣化」「チームで取り組む」といった戦略が有効です。
主な内容・主訴のポイント
- 目標設定
自分で達成可能な目標を設定することでモチベーションが向上する。 - 習慣化
小さな成功体験を積み重ねて学習習慣を形成する。 - チーム学習
チームで学ぶことで互いに刺激し合い、学習効果が高まる。
詳しく解説を読みたい方はこちら
第5章では、勉強が苦手な子どもが「できる子」になるための具体的な方法として、「目標設定」「習慣化」「チームで取り組む」の3つの戦略が紹介されています。
これらは、学習意欲を高め、持続可能な勉強習慣を形成するために有効であることが科学的エビデンスによって示されています。
目標設定
達成可能な目標を設定することで、モチベーションを向上させる方法
目標設定は、子どもが勉強に取り組む際に重要な役割を果たします。
特に、達成可能な目標を自分で設定することで、学習へのコミットメントが高まり、先延ばし癖(現在バイアス)を克服する助けとなります。
例えば、カナダのマギル大学で行われた実験では、学生たちが自分の理想の将来像を描き、それに基づいた具体的な目標を設定した結果、成績(GPA)が大幅に改善しました。
重要なのは、自分でコントロールできる「インプット」(例:1日2時間勉強する)に目標を置くことであり、「試験で80点取る」といったアウトプット型の目標より効果的であることが示されています。
習慣化
小さな成功体験を積み重ねて学習習慣を形成する方法
勉強を習慣化するには、初期の抵抗感を和らげ、定期的に繰り返すことが重要です。
アメリカの大学生を対象とした実験では、最初に金銭的インセンティブ(報酬)を与え、その後4週間で8回以上スポーツジムに通わせたグループが、その後も継続して通い続けるようになりました。
この結果から、「きっかけ作り」と「繰り返し」が習慣形成の鍵であることがわかります。
同様に、子どもたちにも最初はご褒美や小さな達成感を与えることで、勉強への抵抗感を減らし、その後自然と継続できる環境を整えることが有効です。
チーム学習
友人とチームを組むことで互いに刺激し合い、学習効果を高める方法
チームで学ぶことは、ピア効果(仲間からの影響)によって学習量や意欲を向上させます。
カリフォルニア大学サンタバーバラ校で行われた実験では、個人報酬よりもチーム報酬の方が自習室への参加率が20%増加しました。
また、知り合い同士でチームを組んだ場合には特に効果が大きくなることが確認されています。
このような環境では、生徒同士が互いに教え合うことで理解が深まり、教える側も自身の知識を整理する機会となり得ます。
補足説明
- 目標設定のポイント: 目標は「自分で達成可能」と感じる範囲内で設定し、自分自身で決定することが重要です。
他者から押し付けられた高すぎる目標は逆効果になる可能性があります。 - 報酬と習慣化: 金銭的インセンティブは、新しい行動を始める際には効果的ですが、すでに行動している場合には内発的動機づけ(興味や好奇心)を損なう可能性があります。
そのため、新しい行動形成時のみ活用するべきです。 - チーム学習の利点: チーム内で教え合うことで、「教えることは最良の学び」という原則が働きます。
これによって教える側も学び直しや理解深化につながります。
これら3つの戦略は、それぞれ異なるアプローチですが、一貫して「自主性」と「持続性」を重視しており、多くの場面で応用可能です。
本章では、これらの方法論が具体例とともに解説されており、家庭や学校現場でも実践しやすい内容となっています。
第6章: 「第1志望のビリ」と「第2志望の1位」、どちらが有利なのか?
偏差値よりも学内順位が将来に与える影響が大きいことが示されています。
「井の中の蛙効果」によって自信喪失を防ぐことが重要です。
主な内容・主訴のポイント
- 順位と自己評価
学内順位は自己効力感や進学意欲に影響する。 - 深海魚問題
学内順位が低い生徒が自信喪失し努力を諦めてしまう現象への対策。 - 学校選びへの示唆
偏差値だけでなく個々に合った学校選びが重要。
詳しく解説を読みたい方はこちら
第6章では、偏差値の高い学校に進学することが必ずしも子どもの将来に良い影響を与えるわけではないという点と、
学内順位が自己評価や将来の成果に大きな影響を与えることを示しています。
特に、「井の中の蛙効果」による自己効力感(自分ならうまくやれるという感覚)の低下が、学力や進学意欲に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。
順位と自己評価
学内順位は自己効力感や進学意欲に大きな影響を与える
研究によれば、同じ点数を取ったとしても、学校内での順位が高い生徒ほど自己効力感が高まり、努力を続ける傾向があります。
たとえば、小学校で学内順位が上位だった生徒は、中学校以降でも学力テストの偏差値が高くなることが確認されています。
これは、自分の能力に対する肯定的な評価が、次の挑戦へのモチベーションを高めるためです。
深海魚問題
順位が低いことで自信喪失し、努力を諦める現象
「深海魚」とは、偏差値の高い学校に進学したものの、学内順位が低いために自信を失い、その後も成績が伸び悩む生徒を指します。
たとえば、ギリシャの高校生を対象とした研究では、最初のテストで順位が低かった生徒は、その後の努力を怠り成績がさらに悪化する傾向がありました。
このような負のスパイラルは、「自分には無理だ」という思い込みから生じます。
学校選びへの示唆
偏差値だけでなく個々に合った学校選びが重要
本章では、「鶏口となるも牛後となるなかれ」という格言が示唆するように、偏差値よりも学内で上位に位置できる環境を選ぶことの重要性が強調されています。
たとえば、小学校時点で同じ点数だった生徒でも、学内順位が高かった生徒は中学校以降も学力や進学率で有利になることが確認されています。
また、アメリカや中国など複数国でも同様の結果が得られており、この現象は普遍的なものと考えられます。
補足説明
- 井の中の蛙効果: 周囲との比較によって、自分の能力を過小評価してしまう現象。
これにより、自信喪失や努力放棄につながります。 - 親や教員の役割: 順位そのものではなく、「前回よりどれだけ伸びたか」を伝えることで、生徒のモチベーションを維持する方法も提案されています。
- 長期的影響: 学内順位は短期的な成績だけでなく、最終学歴や将来収入にも影響します。
たとえば、小学校時点で上位だった生徒は大学進学率や収入面でも有利になることが示されています。
本章では、子どもの能力を正しく評価し、それに合った環境選びをすることが、長期的な成功につながると結論付けています。
また、「順位」の伝え方や教育環境の工夫によって、生徒たちの自己効力感を高める重要性も強調されています。

