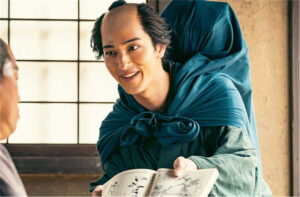みなさん、NHK大河ドラマ「べらぼう」第14話「蔦重瀬川夫婦道中」を観ましたか?
この回、本当に胸に迫るものがありましたよね。
私は正直、画面に向かって「鳥山検校、男気あるなぁ。でも、なんて悲しい人なんだろう」と呟いてしまいました。
そして瀬川には本当に蔦重と一緒になってほしかった…。
彼女の退場シーンでは思わず涙が出てしまいました。
この第14話では、幕府による当道座への手入れから始まり、鳥山検校の入牢、瀬川との離縁、そして蔦重と瀬川の別れという重たい展開が続きました。
特に印象的だったのは、タイトルにもある「夫婦道中」という言葉。
これは単に鳥山検校と瀬川の夫婦関係を指すだけではなく、蔦重と瀬川の精神的な絆をも表しているように思えます。
今回のブログでは、この「夫婦道中」という言葉に込められた二重の意味を掘り下げながら、鳥山検校と瀬川の関係、そして蔦重と瀬川の関係について考えてみたいと思います。
二組の「夫婦」の物語から、愛とは何か、幸せとは何かを一緒に考えてみましょう。
鳥山検校と瀬川の夫婦関係
鳥山検校と瀬川の関係は、1400両という莫大な身請け金から始まりました。
現代の価値に換算すると約1億4000万円とも言われるこの金額は、単なる欲望や所有欲だけでは説明できない、検校の瀬川への深い愛情の表れだったのでしょう。
しかし、お金で人の心まで買うことはできません。
検校はそのことを痛感することになります。
第13話では、瀬川の部屋から蔦重の本が見つかり、彼女の本当の気持ちを知ることになりました。
市原隼人さん演じる鳥山検校の表情には、怒りよりも深い悲しみが浮かんでいたように思います。
そして第14話での検校の決断。
「そなたの望みは何であろうと叶えると決めたのは私だ」という言葉とともに、瀬川との離縁を告げるシーン。
この台詞には、所有や束縛ではなく、愛する人に自由を与えるという究極の愛の形が表れていました。
SNS上では、この鳥山検校の姿に「人の愛し方を知らなかった悲しい人」という評価がある一方で、「相手を手放すことで幸せにするという愛の形を知っていた」という見方も見られます。
大河ドラマ考察系YouTuberのトケル氏も「検校の離縁=瀬以を自由の身とする」という行為は「検校の愛」だったと分析しています。
鳥山検校の男気ある決断は、彼自身の成長の証でもあり、瀬川への最後の愛の表現でもあったのでしょう。
「好きだからこそ手放す」という、最も難しい愛の形を選んだ検校の姿に、多くの視聴者が心を打たれたのではないでしょうか。
蔦重と瀬川の精神的夫婦関係
一方、蔦重と瀬川は幼馴染として育ち、互いに特別な存在として心を通わせてきました。
第9話では蔦重が瀬川に「俺がお前を幸せにしてえの。だから、行かねえでください」と告白し、二人は将来を誓い合いました。
しかし運命は二人を引き離し、瀬川は鳥山検校の妻となりました。
それでも二人の絆は切れることはありませんでした。
第14話では、松葉屋で静養する瀬川のもとを蔦重が訪れ、「本屋を開くから、一緒にやらないか」と夢を語ります。
「幼い頃から答えのでないことには、楽しい空想をすることにしてた」という蔦重の言葉に、瀬川も微笑みながら応じる場面は、二人の純粋な関係性を象徴していましたよね。
しかし現実は厳しく、瀬川は最終的に蔦重のもとを去ることを選びます。
彼女が残した「あんたには夢を見続けてほしい」という言葉には、蔦重への深い愛情と、自分の存在が彼の夢の障害になることへの懸念が込められていたのでしょう。
二人は法的な夫婦にはなれませんでしたが、精神的には深く結ばれた「夫婦」として描かれています。
この「夫婦道中」は、二人が共に歩む道ではなく、別々の道を選びながらも心は共にあるという意味なのかもしれません。
ネット上では「瀬川だけが”救われる側”じゃなくて”救う側”になってるのが泣ける」という感想も見られました。
瀬川の決断は、蔦重の将来を思っての自己犠牲であり、それこそが彼女なりの愛の表現だったのでしょう。
松崎の襲撃事件の影響
物語が少し落ち着きを見せた矢先、松葉屋に身を寄せていた瀬川が襲撃されるという衝撃的な事件が起きます。
犯人は女郎・松崎(新井美羽)。
彼女が瀬川を襲った背景には、吉原で生きざるを得なかった女性の苦しみと怒りが深く関係していました。
松崎は「両親が座頭金返済のために自害し、自身が吉原へ売られた過去」を背負っていたんです。
鳥山検校の妻だった瀬川を憎み、心の奥に積もった怨念が爆発して、包丁を隠し持って瀬川に襲いかかったんです…。
この事件は瀬川にとって大きな転機になります。
彼女は「はじめて自分が恨まれる立場になっていたことを実感する」ことになったんです。
自分が鳥山検校の妻であったことで、知らず知らずのうちに多くの人々を傷つけていたという事実に向き合うことになりました。
この襲撃事件は、単なる暴力事件ではなく、「誰かの幸せの裏で誰かが傷ついている」という社会的テーマを浮き彫りにしています。
松崎の背景には、吉原という場所で生きることを強いられた女性の現実があり、それは同時に「鳥山検校という一人の権力者の存在が、いかに多くの人の運命を変えてきたか」を示しているんですよね。
瀬川はこの事件をきっかけに、自分が蔦重と一緒にいることが、彼の将来にも悪影響を及ぼす可能性を強く意識するようになります。
「瀬川が嬉しそうに愛する人と本屋など営んでおれば、人々の恨みと嫉妬は瀬川だけではなく蔦重や、ひいては吉原の再興にも支障をきたす」
という思いが、彼女の心を捉えたのでしょう。
「夫婦道中」というタイトルの意味と象徴性
第14話のタイトル「蔦重瀬川夫婦道中」には、実に深い意味が込められていますよね。
このタイトルは二重の意味を持っていると考えられるんです。
まず一つ目は、鳥山検校と瀬川の実際の夫婦関係の終焉を表しています。
検校が瀬川との離縁を決断したことで、彼らの夫婦としての「道中」は終わりを迎えました。
検校の「そなたの望みは何であろうと叶えると決めたのは私だ」という言葉には、瀬川への深い愛情と、彼女を自由にするという決断が込められていました。
二つ目は、蔦重と瀬川の精神的な絆を表す比喩的な夫婦関係です。
二人は法的な夫婦にはなれませんでしたが、心の中では深く結ばれていました。
「本屋を一緒にやらないか」という夢を語り合い、短い時間ながらも「夫婦」のように寄り添う時間を過ごしたのです。
この「夫婦道中」というタイトルは、「共に歩む夢」と「別々の道を選んでも想い合う心」という両義性を持っているのではないでしょうか。
二人は実際に共に歩むことはできませんでしたが、心の中では常に寄り添っているという意味が込められているのでしょう。
vodeverydayのサイトでは、この回を「”夫婦道中”というタイトルに込められた意味とは、共に歩む夢と、別々の道を選んでも想い合う心。その二重の意味をしっかりと感じさせてくれる一話」と評しています。
タイトルが暗示する物語の展開は、まさに二人の別れと、それでも続く心の絆を象徴していたのです。
ネット上の反応や考察
第14話「蔦重瀬川夫婦道中」の放送後、ネット上では様々な感想や考察が飛び交いました。
多くの視聴者が瀬川の退場に悲しみや喪失感を表明し、「一緒になって欲しかった」という素直な感情を吐露しています。
noteに投稿された感想では「ちょっと…どうしたらいいんでしょう…言葉が見つからない」と、ショックのあまり言葉を失う様子が綴られています。
また別の視聴者は「最後まで、鳥山検校が超絶良い男で号泣ーーーッ!!」と、市原隼人演じる鳥山検校の男気ある姿に感動したことを伝えています。
大河ドラマ考察系YouTuberとして知られるトケル氏は、蔦重と瀬川の関係について「蔦重の愛の提案は現実的でなかったかもしれないが、夢や空想に生きることの大切さが描かれていた」と評価しています。
また、松崎が瀬川を襲撃する事件についても「松崎の過去と思想背景が瀬川への怨恨につながった」と分析し、瀬川が自ら蔦重のもとを去る決断に至った背景として「鳥山と瀬川両者の愛の形態が影響したのでは」という視点を示しています。
瀬川の退場理由については様々な説があります。
「検校のせいでエライ目に合った大勢の人々にすれば、その寵愛を受けていた瀬以も恨みの対象となっている」ため、「瀬川が嬉しそうに愛する人と本屋など営んでおれば、人々の恨みと嫉妬は瀬以だけではなく蔦重や、ひいては吉原の再興にも支障をきたす」と考えたという説が有力です。
しかし、蔦重から自ら身を引いた瀬川の思考はまさに鳥山検校と同じです。
「愛する者のために、身を引く」
この思考法は、まさに瀬川と鳥山検校が「精神的にも同じような考えをする仲の良い夫婦だったことを暗示している」ように思えてなりません。
瀬川が蔦重と別れたのは、鳥山検校の「瀬川への愛」が瀬川の意識下で大きく影響していたように思えます。
多くの視聴者がこの回を「最終回レベルの感動」と評価し、トケル氏も「ドラマのその場しのぎの愛ではない、人間の内面性や関係性に迫っており、視聴者にちょっとした洞察を与えている」と締めくくっています。
瀬川の静かな退場は、多くの視聴者の心に深い余韻を残したようです。
瀬川の退場の真意
瀬川が蔦重のもとを去った真意は何だったのでしょうか。
彼女が残した「あなたには夢を見続けていてほしい」という短い手紙には、様々な思いが込められていたように思います。
まず考えられるのは、蔦重の夢や吉原の再興の妨げにならないようにという配慮ですよね。
瀬川は松崎の襲撃事件を通じて、自分が鳥山検校の妻だったという事実が多くの人々の恨みを買っていることを痛感しました。
そんな自分が蔦重と一緒にいることで、彼の将来にも悪影響を及ぼす可能性を危惧したのは確かでしょう。
SNS上では「瀬川が嬉しそうに愛する人と本屋など営んでおれば、人々の恨みと嫉妬は瀬以だけではなく蔦重や、ひいては吉原の再興にも支障をきたす」という考察が見られます。
瀬川は自分の幸せよりも、蔦重の夢や吉原の未来を優先したのでしょう。
また、鳥山検校との関係や座頭金問題による社会的影響も無視できません。
当時の社会では、不義密通(不倫)は重罪とされ、最悪の場合は死罪になることもありました。
瀬川は自分と蔦重の関係が公になることで、彼に危険が及ぶことを恐れたのかもしれません。
そして、自身の新たな人生を歩むという決断もあったでしょう。
瀬川は鳥山検校の妻として、そして蔦重の幼馴染として生きてきましたが、これからは自分自身の道を見つけたいと思ったのかもしれません。
私自身は、瀬川にはこう思ってほしいという「願い」があります。とにかく前を向いてほしい…。
ネット上では「瀬川だけが”救われる側”じゃなくて”救う側”になってるのが泣ける」という感想も見られます。彼女の決断は、自己犠牲を伴う愛の形だったのでしょう。
物語の展開によっては、瀬川が再登場する可能性も考えられますよね。
私だけではなく、多くの視聴者が彼女の再登場を期待しているようです。
それは今後の「べらぼう」の展開次第ですね。
史実との比較
ドラマ内で退場した瀬川ですが、実在した「五代目瀬川」のその後の人生はどうだったのでしょうか。
歴史的資料によると、瀬川のその後については興味深い記録が残されています。
天保14年(1843年)に書かれた『筠庭雑考(いんていざっこう)』には、瀬川が鳥山検校との離縁後に“飯沼某”という武士の妻になったことが記されています。
さらに、飯沼氏と死別した後は、“大工・結城屋八五郎”の後妻となり、晩年は出家して尼になったという記録もあるようです。
トケル氏は自身のYouTubeチャンネルで「瀬川が吉原を出た後どうなったのかは、今のところ分かっていない」としつつも、「ドラマでは驚くような物語になる可能性もありそうです」と次話への期待を寄せています。
このように史実と創作が交錯する部分は、大河ドラマの醍醐味の一つと言えるでしょう。
ドラマ「べらぼう」では、史実を尊重しながらも、視聴者の心に響く人間ドラマとして瀬川の物語が描かれています。
今後、史実に基づいた瀬川のその後が描かれるのか、それとも全く新しい展開が待っているのか、楽しみです。
まだまだ、蔦重と一緒になる物語を私はあきらめていません。
今後の展開予想
瀬川が去った後、蔦重はどのような道を歩んでいくのでしょうか。
彼女の「あなたには夢を見続けていてほしい」という言葉を胸に、蔦重は本屋の夢を追い続けることになるのでしょう。
歴史的には、蔦屋重三郎は江戸時代を代表する出版業者となり、浮世絵師・葛飾北斎や喜多川歌麿などの才能を世に送り出した人物として知られています。
ドラマでも、蔦重が瀬川との別れを乗り越え、出版業の道で成功していく姿が描かれるのではないでしょうか。
また、新たなヒロインの登場も期待されます。
史実では蔦屋重三郎には妻がいたとされていますので、今後のドラマで蔦重の新たなパートナーが登場する可能性もあります。
しかし、多くの視聴者は瀬川との関係に深く感情移入しているため、新たなヒロインの登場には複雑な反応があるかもしれませんね。
蔦重の妻は、名を変えた瀬川であってほしいなあ…。
吉原の再興についても、今後の重要なテーマになるでしょう。
蔦重は「金なし親なし家もなし、ないないづくしの吉原者」から「鼻を利かせ風を読み、やがて江戸のメディア王」へと成長していきます。
その過程で、吉原という場所がどのように変わっていくのかも見どころの一つです。
瀬川との別れは辛いものでしたが、この別れが二人の新たな始まりであることを信じたいですね。
二人がそれぞれの道を歩みながらも、いつか再会する日が来ることを密かに期待している視聴者も多いはずです。
まとめ
「べらぼう」第14話「蔦重瀬川夫婦道中」は、愛の多様な形と、それぞれの登場人物の決断の重さを描き出した感動的な回でした。
鳥山検校の男気ある離縁、蔦重と瀬川の叶わぬ夢、そして瀬川の自己犠牲的な退場は、視聴者の心に深い感動と余韻を残しました。
この物語が問いかけるテーマは、単なる恋愛模様を超えた深いものです。
愛とは何か、幸せとは何か、そして夢と現実の間でどう生きるべきか—
これらの問いは、江戸時代という制約の中で描かれながらも、現代を生きる私たちにも強く響きます。
鳥山検校が示した「相手を自由にする」という愛の形、瀬川が選んだ「愛する人のために身を引く」という決断、そして蔦重が抱き続ける「夢を見続ける」という姿勢。
それぞれの選択には、深い愛情と覚悟が込められていました。
江戸時代という厳しい社会の中でも、人々は自分なりの愛の形を模索し、苦悩しながらも前に進もうとしていたのですね。
それは現代を生きる私たちにも通じる普遍的なテーマではないでしょうか。
第14話を通じて、私たちは改めて「愛」の多様性と、人間関係の複雑さを考えさせられました。
これからの「べらぼう」の展開にも、引き続き注目していきたいと思います。