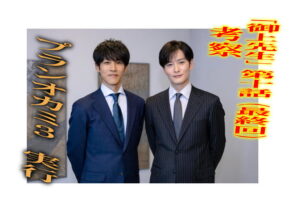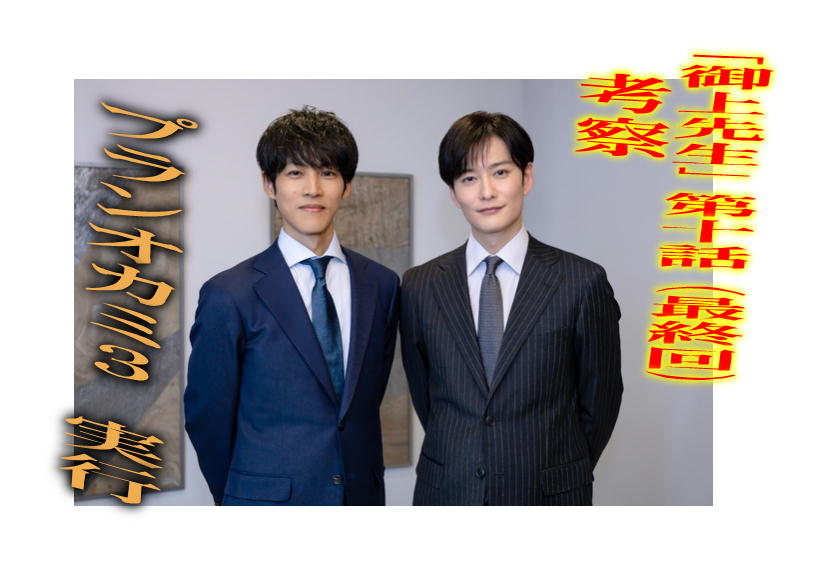
日曜の夜、多くの視聴者が見守る中、「御上先生」の最終回が放送され、文部科学省のエリート官僚・御上孝が隣徳学院で繰り広げた教育再生の物語が感動のフィナーレを迎えました。
最終話では、不正入学問題の核心、教育とは何かを問う授業、そして生徒たちの成長が描かれ、視聴者の心に深い感銘を与えましたね。
本記事では最終回の内容を振り返りながら、このドラマが投げかけた「考える力」の本質と、教育改革へのメッセージを徹底考察していきましょう。
第10話のあらすじ~プランオカミ3の実行と最後の授業~

最終回は、御上(松坂桃李)と文科省の同僚・槙野恭介(岡田将生)が中心となって「プランオカミ3」と呼ばれる作戦を実行するところから始まります。
この作戦は、隣徳学院、文部科学省、永田町をつなぐ不正入学の証拠を集め、その実態を世に知らしめるというものでした。
神崎拓斗(奥平大兼)たち3年2組の生徒たちの協力により、不正入学者リストや音声データが集められました。
次元(窪塚愛流)の部屋で神崎が冴島(常盤貴子)から受け取ったUSBメモリから出た「不正入学者リスト」と、槙野が仕組んだ盗聴器からの音声データを合わせれば決定的証拠になるとの判断。
さらに是枝(吉岡里帆)が税理士から譲り受けた写真も重要な証拠となりました。
これらの証拠から明らかになったのは、古代理事長(北村一輝)、塚田(及川光博)、そして千木明遥(高石あかり)の父親が古い知り合いであり、隣徳学院が不正入学を受け入れる見返りとして多額の助成金が渡される仕組みだったということです。
一方、御上先生は隣徳学院の教室で「考える力とは何か」をテーマにした特別授業を行いました。
「戦争はいけないこと。でも正しい戦争はあるのか?」という明確な答えのない問いを生徒たちに投げかけ、教室は静まり返ります。
この授業を通じて、御上先生は生徒たちに「考える力とは、答えが出ない問いを投げ出さずに考え続ける力だ」というメッセージを伝えました。
最終決戦は、古代、塚田、中岡(林泰文)が集まる料亭で行われました。
そこに槙野が現れ、御上は不正を暴露する記事が掲載されると古代らに伝えます。
「永田町と霞が関、そして隣徳の癒着した関係が、闇の仲人によって育まれ、ひとりの罪のない若者が刺殺されるまでの誰も想像しなかったバタフライ・エフェクトの物語です」と御上は畳みかけました。
御上先生が伝えた「考える力」の真髄
最終回で最も印象的だったのは、御上先生による「考える力とは何か」についての特別授業ですね。
この授業は、不正という重い現実を背景にしながらも、生徒自身の思考の在り方を問い直す極めて本質的な内容となっていました。
これは、皮肉なことに文科省が、ずっと言い続けてきたことです。しかし、世間には伝わらなかった内容そのものです…。
文科省関係者や真の学力向上を見据えていた現場教師たちは、「私たちが行ってきた、生きる力・考える力の育成とは、まさにこのことなんです…。」と、この物語を複雑な思いで見ていたと思います。
話を戻します。
御上先生が黒板に「考える力」と書き、生徒たちに提示した「戦争はいけないこと。でも正しい戦争はあるのか?」という問いは、明確な正解がないものでした。
この問いは、道徳や倫理、国家の方針などが複雑に絡み合う問題であり、簡単に答えを出すことができるものではありません。
御上先生はこの困難な問いを通じて、生徒たちに「問い続けること」の大切さを教えようとしたのです。
やむを得ないとされる戦い、その”やむを得なさ”を誰が決めているのか、そしてその決断が誰の人生を左右するのか。御上の問いかけは、政治や社会の構造にまで踏み込む深いものでした。
授業の最後に御上先生は「考える力とは、答えが出ない問いを投げ出さずに考え続ける力だ」と語りました。
この言葉は、教育が単に「答え」を求めるものではなく、”考え続ける姿勢”こそが現代社会を生き抜くために必要な力だというメッセージが込められていたのです。
答えのない問いと向き合う教室の空気

御上の問いかけに、最初は戸惑いを見せていた生徒たち。
しかし、彼らは次第に自分の価値観や知識を基に思考を深めていきました。
教室の空気が変わり、「正しい戦争」という概念の是非について、それぞれの視点から意見が交わされるようになります。
注目すべきは、御上がこの授業をただの思考実験ではなく、現実の不正入学問題と結びつけていたことです。
不正は悪いことだが、教育改革のためと信じて行った不正は許されるのか?
この倫理的ジレンマは、古代理事長の立場や千木良遥の葛藤にも通じるものがありました。

千木良遥の葛藤と選択
不正入学問題の中心にいた千木良遥の内面の葛藤も、最終回の重要なテーマでした。
神崎は学校の屋上で千木良に不正入学者リストの件を伝えます。
千木良は「わかっていたよ」と答え、自分の境遇を悟っていたことを明かします。
千木良は、自分が大人たちの利権に巻き込まれてしまったとは言え、それを悟った後は人一倍勉強を頑張り、成績も優秀になっていました。
彼女は単に被害者ではなく、その事実と向き合い、自分なりの答えを見つけようとする姿勢を見せていたのです。
神崎が「すごく残酷なことをしてるのは分かってる…でも一緒に考えたいんだ」と言うと、千木良は「ごめん、無理…」とその場を去ります。
この反応は、彼女の中で起こっている激しい葛藤を表しています。
自分が不正によって入学したという事実と向き合うことの苦しさと、それでも逃げずに考え続けようとする意志の狭間で揺れる彼女の姿は、御上先生が教えた「考える力」そのものを体現していたと言えるでしょう。
プランオカミ3の真髄とバタフライエフェクト
御上と槙野が実行した「プランオカミ3」は、単に不正を暴くだけでなく、教育システム自体の変革を目指した作戦でした。
御上は「不正を暴くことが目的じゃない。教育のシステムが変わらないと意味がないんだ」と槙野に語っています。
この作戦の核心は「バタフライエフェクト」という考え方にありました。
御上は料亭での最終対決で、「永田町と霞が関、そして隣徳の癒着した関係が、闇の仲人によって育まれ、ひとりの罪のない若者が刺殺されるまでの誰も想像しなかったバタフライ・エフェクトの物語となったのです」と語ります。
バタフライエフェクトとは、蝶の羽ばたきが遠く離れた場所で台風を引き起こすという比喩で表される、小さな出来事が予想もしない大きな結果をもたらすという概念です。
不正入学という一見小さな問題が、教育システム全体の歪みを生み、最終的には取り返しのつかない悲劇につながることを示唆しています。
神崎が書いた記事は、このバタフライエフェクトを明らかにするものでした。
「神崎くんが書いて父親に託した。まさに自律。あなたの教育が、素晴らしい成果を出した瞬間を目撃できますよ」と御上は古代らに告げます。
主要キャラクターの成長と変化
最終回では、様々なキャラクターの成長や変化が描かれました。
特に注目すべきは以下のキャラクターたちです:
御上孝の使命と葛藤
御上先生は文科省官僚としての立場と教師としての使命の間で葛藤しながらも、最終的に教育改革のために行動を起こしました。
彼の兄・宏太の死という過去のトラウマも、このドラマを通じて少しずつ解消されていきます。
御上は中学時代に自分が兄に投げかけた一言が兄の死の最後の一押しになっていると考えていました。
しかし、彼は次第に兄の死と向き合い、「兄の分まで2人分生きるから」と母親に伝えることで、何十年ぶりに「たかし」と呼んでもらえるようになりました。
この和解は、御上自身が「考える力」を持ち、過去から逃げずに向き合った結果とも言えるでしょう。
槙野恭介の視点と役割
槙野は「ヤマトタケル」として裏で動き、御上を支援していました。
彼もまた、官僚システムの中での正義のあり方に悩みながらも、自分の信念を貫きました。
最終回では、御上の部屋で生徒たちについて話す一幕がありました。
槙野は「それにしてもすごいな。お前の生徒だよ。あんななの? 今の高校3年生」と感心すると、特に富永について「あれ人生何回目だ」と呟きます。
この発言は多くの視聴者の感想を代弁するもので、富永の深い洞察力と思いやりに多くの人が驚いていたことを表しています。
富永蒼の深い洞察力

富永(蒔田彩珠)は「人生何周目だ」と言われるほど深い考えを持ち、常に周囲を支える存在でした。
彼女の言葉が御上先生を動かすこともありました。
富永は「私たちは裸で丸腰で先生と向き合っているのに、どうして先生は鎧を着ているのか」と御上に問いかけ、それが御上が自分の過去を生徒たちに打ち明けるきっかけとなりました。
この言葉は、教師と生徒の関係性の本質を鋭く突いたものでした。
また、富永には弟がおり、下半身不随の弟に対して「いいかげんにしなさい!」と言ってしまい、後悔していたという背景も明かされました。
御上先生と共に母親に会いに行った彼女は、最終的に弟に「大好きだよ」と言えなかった気持ちを伝えることができました。
古代理事長の矛盾と葛藤
古代理事長は、教育に関して素晴らしい信念を持ちながらも、教育改革を成し遂げるために不正入学で助成金を貰うという苦渋の選択をしていました。
この姿は「システムを変えようとしてシステムに組み込まれる」という皮肉な状況を表しており、カール・マルクスが唱えた疎外の概念(人間が作ったシステムに人間が振り回される状況)を想起させます。
出身大学で生徒の評価が決まるような世の中だからこそ、全国でトップになってからその風潮を変えていきたかったという古代の立場は、多くの社会人の姿を象徴しています。
「今働いている会社は割とグレーなことをしてるけど、俺が役職に上りつめて変えてやる!」と思いながら、結局何もできないという社会人の象徴として描かれているのです。
ドラマが描き出す教育の問題と社会の連関
「御上先生」は単なる学園ドラマではなく、教育問題と社会構造の深い連関を描き出しています。
不正入学問題は、単に一つの学校の問題ではなく、永田町(政治)、霞が関(行政)、学校(教育現場)の癒着という構造的な問題として描かれました。
このドラマの特徴は、「学校の外で起こっていることが自分たちが通う学校にどのような影響を与えているか」という視点を重視していることです。
これは、教育問題を学校内の問題だけでなく、社会全体の問題として捉える必要性を示しています。
第1話から第5話までは、「生徒・教師・学校・省庁・政治家」とそれぞれの立場と環境が次々と提示され、第6話からは御上先生のバックボーンや彼の目的が明らかになっていきました。
このような構成は、教育問題の根が社会の様々な層に絡み合っていることを視聴者に実感させます。
また、このドラマでは「根っからの悪人は存在しない」という人間観も示されています。
一見、余裕で生きているように見える人たちにもそれぞれの苦しみがあり、最初は他人のことは「我関せず」だったクラスが互いを支え合うようになっていく姿が描かれていました。
最終回を踏まえたドラマ全体の評価
「御上先生」は全10話を通して、教育問題、官僚制度、政治と教育の関係など、様々なテーマを取り上げてきました。
最終回ではそれらのテーマがひとつに集約され、教育改革という大きな目標に向かって物語が進みました。
視聴者からは「単に犯人をみんなで考察するドラマではない」「まったく娯楽番組ではなくドラマの台詞どおり『考えて!』をテレビの中から投げかけられている」という感想も寄せられています4。この言葉通り、「御上先生」は視聴者に考えることを促すドラマでした。
特筆すべきは、このドラマが単に「善と悪」を明確に分けるのではなく、複雑な現実を描いている点です。
古代理事長のように、善良な意図を持ちながらも不正に手を染めてしまう人物、あるいは御上のように、システム内で戦いながらもシステムを変えようとする人物など、多様な立場が描かれています。
また、生徒たちの成長も丁寧に描かれています。最初は自分の問題だけに関心を持っていた生徒たちが、徐々に社会の問題に目を向け、自分たちに何ができるかを考えるようになる。
これは御上先生が伝えたかった「考える力」がしっかりと根付いていることを示しています。
「御上先生」を検索する人々の疑問と共有したい感想
「御上先生 第10話 考察」というキーワードで検索する人々は、どのような疑問や感想を持っているのでしょうか。
検索者が持ちやすい疑問
プランオカミ3の詳細は?
〇 最終話でついに実行された「プランオカミ3」の具体的な内容と、その成果について知りたいという疑問
プランオカミ3は、隣徳学院の不正入学問題を根幹から暴くため、御上孝(松坂桃李)と槙野恭介(岡田将生)が立案した三段階構成の作戦です。
第一段階で生徒たちが不正入学者リストを入手、第二段階で槙野が文科省内に仕掛けた盗聴器から政治家主導の資金流用を記録。
最終段階では是枝(吉岡里帆)が入手した助成金授受の写真証拠を組み合わせ、永田町・霞が関・学校の癒着構造を可視化しました。
特に神崎拓斗(奥平大兼)が父の新聞社経由で公開した記事「教育の闇に潜むバタフライエフェクト」が決定的役割を果たし、世論を動かすと共に古代理事長(北村一輝)らの自白を引き出しました。
成果として不正入学制度の廃止と教育助成金の透明化が実現し、ドラマ終盤で御上と生徒たちが文科省前で見つめた桜は、教育改革の新たな芽生えを象徴していました。
千木良遥の最終的な決断は?

〇不正入学が発覚した千木良遥がどのような決断をし、どのような未来を選んだのかについての疑問
千木良遥は不正入学発覚後、隣徳学院を退学せず在籍を継続しながら高卒認定試験を受験する道を選んだのだと私は思いましたが、皆さんはどうみましたか。
私が、どうして「千木さんは、退学せずに高卒認定試験を受けた」と考えたのかというと、文科省主導の特例措置(在学中の認定試験受験許可)を活用した考えたからです。自らが関与した不正への責任を取るため、本人は退学を望んだとは思います。
しかし、御上先生や、是枝先生が退学を阻止したのではないでしょうか。
だから、千木さんは御上の最後の授業に参加したのだと思います。
ただし、不正入学問題の調査が完了するまでは「卒業資格保留」状態であったため、みんなが卒業証書を持っているけれど千木さんだけもっていなかったのだと推察しました。
養護教諭・是枝(吉岡里帆)の配慮で御上の最終授業に臨んだこの行動には三重の意味が込められていると思います。
(1)クラスメイトとの精神的別れの儀式参加、
(2)御上の「自分の人生を選び取る力」という教えへの応答、
(3)不正によって得た形式的資格ではなく、真の学びを選択した証し。
彼女が選んだ高卒認定試験ルートは、制度的には「高校卒業」と「大検合格」の二重資格取得を可能にする現実的解決策であり、ドラマ終盤で桜の下を歩く姿が示すように、自らの過ちと向き合いながら前進する「再生の象徴」として描かたのだと思います。

バタフライエフェクトの意味とは?
〇御上先生が言及した「バタフライエフェクト」が物語の中でどのような意味を持つのかについての疑問
ドラマにおけるバタフライエフェクトは、小さな不正が巨大な社会的悲劇を生む連鎖構造を比喩的に表現しています。御上先生が指摘した「隣徳学院の不正入学→助成金不正流用→神崎刺殺事件」という因果関係は、教育現場の微細な歪みが政治・官僚組織を経て人命に関わる事態に拡大するプロセスを可視化しました。
この概念は「個人的な過ちがシステム全体を腐敗させる」という現代社会の脆弱性を告発すると共に、御上たちの教育改革が「羽ばたき」となり新たな未来を創る可能性を示唆しています。
教育改革は実現したのか?
〇御上先生と生徒たちの行動によって、実際に教育システムに変化はあったのかという疑問
これは、これからでしょう。
私たちが30年近く努力しても、改革は途上。
卒業した生徒たちが歩いてゆく姿、課題は未来に託されるということでしょう。
登場人物たちのその後は?
〇物語の後、御上先生や生徒たち、そして古代理事長や塚田などのキャラクターがどのような道を歩むのかについての疑問
登場人物たちのその後は、各キャラクターの信念とドラマの教育的テーマを反映した展開が予測されます:
(あくまで私の独断的推察です)
- 御上孝:文科省に復帰し「生徒主導型教育推進室」を新設。「生徒が文科省に入省」予想通り、神崎拓斗ら教え子を官僚候補として育成。文科省前の桜(最終回象徴)の下で次世代官僚と語らう姿が。
- 古代理事長:不正入学問題の責任を取り辞職。「教育に関して素晴らしい信念」を活かし、教育NPOを設立。元教え子の冴島悠子と協力して全国の教育格差是正に取り組む。
- 塚田:事務次官の座を失い、「永田町との癒着」が発覚し政界引退。海外の教育コンサルティング会社に転身するも、御上の改革を陰から支援する複雑な立場に。
- 神崎拓斗:予想通り東大文科一類に進学後、文科省入省。御上の後継者として教育現場と行政の橋渡し役に。ドラマ冒頭の殺人事件を題材にしたノンフィクション「教育のバタフライエフェクト」を執筆。
- 富永蒼:「弟の介護」経験を活かし、特別支援教育の専門家に。文部科学省特別参与として発達障害児支援政策を主導。御上の兄・宏太の意志を継ぐ形で教育改革に参画。
- 是枝文香:副校長に昇進。御上が残した「考える力」カリキュラムを全国の高校に普及。「保護者対応」経験を基に、家庭と学校の連携ガイドラインを策定。
「こうなったらいいな」
という、筆者の希望を反映した予想にしてみました。
「考える力」が導く新たな教育の姿
「御上先生」が最終的に提示したのは、「考える力」を中心に据えた新たな教育の姿です。
御上先生は「不正を暴くことが目的じゃない。教育のシステムが変わらないと意味がないんだ」と語りましたが、これは現代の教育改革にも通じるメッセージです。
現在の教育システムでは、出身大学によって生徒の評価が決まるような風潮があります。
そうした中で、本当の「考える力」を養う教育がどれだけ実践されているでしょうか。
ドラマは、教育の本質が「考える力を育むこと」にあると示唆しています。
御上先生は最初から完璧な教師として描かれたわけではありません。
「学校の先生よりも学校の先生すぎる」という指摘もあるように、官僚でありながら教壇に立ち、流暢に授業を行う姿に違和感を覚える視聴者もいたようです。
しかし、それは「教育」という本質に忠実に向き合う姿勢の表れとも言えるでしょう。
最終的に、御上先生が生徒たちと築いた関係性、そして彼が伝えた「考える力」の本質は、形式的な教育の枠を超えた真の学びの姿を示しています。
それは、知識を詰め込むのではなく、自分で考え、行動する力を養うこと。
そして、答えのない問いに向き合い続ける勇気を持つことの大切さです。
まとめ:教育の未来に「考える力」を
「御上先生」は、教育問題という重いテーマを扱いながらも、希望と感動を与えるドラマでした。
卒業式を終えた生徒たちに対し、御上先生が行った最後の授業。
それをうるうるした目で聞く生徒たちの姿…。
観ていて、こちらも思わずもらい泣き…。
最終回では、不正入学問題の解決だけでなく、その先にある教育改革の可能性を示しています。
御上先生が生徒たちに伝えた「考える力」は、このドラマの視聴者にも強く訴えかけるメッセージとなっていたと思います。
複雑な問題に簡単な答えはなく、だからこそ考え続けることが大切だという教えは、現代社会を生きる私たちにとっても重要な指針となるでしょう。
このドラマが残したレガシーは、教育の本質についての問いかけと、それを実現するための具体的な行動の大切さではないでしょうか。
システムを変えることは難しいけれど、諦めずに考え続け、行動し続けることで、少しずつでも変革は可能だというメッセージが、最終回を通じて伝わってきます。
「御上先生」は単なるエンターテインメントを超え、現代社会における教育の在り方について深く考えさせてくれる作品でした。
ドラマは終わりましたが、その問いかけは視聴者の心に残り、現実の教育や社会に対する新たな視点を提供してくれたことでしょう。
これからも、このドラマがきっかけとなって、教育について、社会について、私たち一人ひとりが「考える力」を発揮することを期待したいと思います。
最後に、
このドラマの制作者の皆様、すばらしいドラマを届けてくれてありがとう。