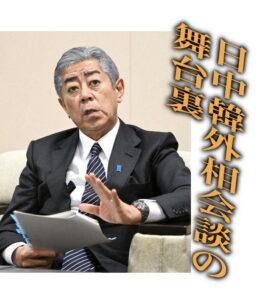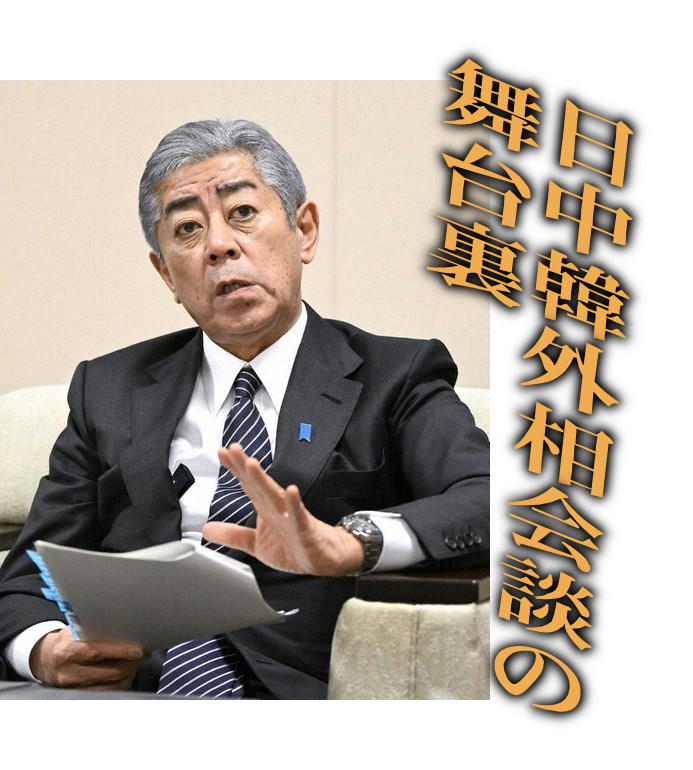
揺れる国際情勢の中での会談開催
2025年3月22日、東京都内で日中韓の外相が集まる重要な会議が開かれました。
日本の岩屋毅外相、中国の王毅外相、韓国の趙兌烈(チョ・テヨル)外相が顔を合わせ、「未来に向けた協力」をテーマに話し合いました。
この会談が行われた背景には、世界中で起きている様々な問題があります。
ウクライナでの戦争や中東での紛争が長引いており、アメリカのトランプ政権が取る「自国優先」の政策が世界経済に大きな影響を与えています。
こうした不安定な状況だからこそ、日本・中国・韓国という東アジアの主要国が協力することが、この地域の安定にとって非常に大切になっています。
岩屋外相は会談の冒頭で「国際情勢が日に日に厳しくなっており、歴史的な転換点と言っても言い過ぎではない」と述べました。
石破茂首相も中国と韓国の外相との個別会談で「両国はとても大切な隣国です。問題点も含めて話し合い、未来に向けた協力関係を築きたい」と強調しました。
会談の主な成果
経済協力と人的交流の促進
会談では、経済面での協力を深めることや、人々の交流を増やすことで相互理解を深める取り組みが合意されました。
特に注目すべきは、2025年から2026年にかけて行われる「日中韓文化交流年」です。
これは若い世代を中心に三国間の文化交流を促進し、お互いの理解を深める大切な機会となります。
また、三国が共通して直面している「少子高齢化」という問題についても、一緒に研究を進めていくことで意見が一致しました。
高齢者が増え、子どもが減っていく社会では、医療や年金、労働力不足など多くの課題があります。
これらの問題に三国が協力して取り組むことで、より良い解決策が見つかるかもしれません。
王毅外相は「協力が深まれば深まるほど、リスクを防ぐ力が強くなり、発展の土台がより固くなる」と述べ、経済協力の重要性を強調しました。
日中韓関係に対する否定的な反応:SNS上の声から見る実態
SNS上では、日中韓の文化交流や経済協力に対して強い否定的意見が多く見られます。
特に中国に対する警戒感や拒否感を示す声が目立ちます。
中国との関係に対する否定的意見
「日中友好は日本だけの幻想だ」という主張は多くの共感を集めていました。
ある投稿では「仲良くするために中国の無理な要求を飲む。仲良くするために日本の総理大臣は靖國神社へ参拝できない。仲良くするために中国にODAを出さなければならない。仲良くするため日本人が失うものは多い」と指摘されています。
また、「喧嘩するでもなく、一定の距離を保つ」べきだという意見も多く、「日本人が良く言う『俺とお前』の関係にはしない方がいい。いつまでも『私とあなた』という関係でいること」という冷静な距離感を保つべきだという主張も見られます。
韓国との関係に対する反応
韓国に対しても「わがままで、秩序を守れない民族となぜ友好関係を結ばなければならないのか」という厳しい意見が散見されます。
特に文化交流に関しても、「韓国人は欧米人のように自己主張がはげしく、嫌なものは嫌だとはっきり言う習慣がある」という文化的差異を指摘する声があります。
靖国参拝問題に関する世論調査では、日本側は「参拝しても構わない」「私人としての立場なら構わない」が7割を占め、韓国側の反対意見(6割が「参拝すべきではない」)との大きな認識の差が見られます。
現実的な国際関係への視点
一方で、「トランプ政権下のアメリカの姿勢では、いやだが中国とか韓国とも連携を進めるぞという格好は見せておく必要がある」という現実的な意見も存在します。
これは米中対立の中で日本の立ち位置を考慮した戦略的な見方です。
中韓の連携強化に対する警戒感も強く、「韓国の中国重視の流れは変わらない。かつてのような友好的な日韓関係はもう戻ってはこない」という分析も共有されています。
若い世代の異なる視点
興味深いことに、若い世代では異なる意見も見られます。
大学生の間では「若い世代の間ではアイドル、化粧品など日常的な文化交流を通じて日中間の相互理解がある程度進んでいる」という声もあります。
しかし、「メディアが中国のネガティブな面を伝える報道を見ると、日本の方が住みやすい、平和だ、良い社会だと感じることができるので、そのような報道が好まれる」という分析もあり、メディアの報道姿勢が国民感情に与える影響も指摘されています。
日中韓の関係改善に対しては、「将来を考えれば考えるほど交流を継続して行なっていかなければならない」という前向きな意見もありますが、全体としては警戒感や距離感を保つべきという意見が多数を占めているのが現状です。
首脳会談の早期開催に向けて
会談では、昨年5月以来となる三国の首脳(各国のリーダー)による会談を早く開催することでも合意しました。
趙兌烈外相は「一度止まった車輪を再び動かすのはとても難しいことです。今の前向きな流れを維持すべきです」と述べ、首脳会談を定期的に開くことの大切さを強調しました。
首脳会談が実現すれば、より大きな決断や合意が可能になり、三国の協力関係がさらに強化されることが期待されます。
北朝鮮問題:三国の立場の違い
会談では北朝鮮の問題についても話し合われましたが、ここで三国の考え方の違いがはっきりと現れました。
岩屋外相と趙兌烈外相は、北朝鮮が進めている核兵器やミサイルの開発、そしてロシアとの軍事協力に強い懸念を示しました。
特に岩屋外相は、北朝鮮に拉致された日本人の問題をすぐに解決するよう、中国と韓国の理解と協力を求めました。
一方、王毅外相は「問題の本質をしっかり見て、関係国がお互いに歩み寄ることが必要です」と述べました。
これは、北朝鮮だけを一方的に非難するのではなく、対話を通じて解決することの大切さを強調するという一見正しく見える言い回しです。
この立場の違いは、北朝鮮問題に対して三国が協力することの難しさを浮き彫りにしています。
特に、中国が北朝鮮に燃料などを密かに送っているという見方や、中国の企業が軍事に使える物資をロシアに輸出しているという指摘は、地域の不安定さにつながる心配があります。
日中関係:協力と問題点の両面
外相会談の後に行われた日中の外相による個別会談では、岩屋外相と王毅外相が「戦略的な互恵関係」を全面的に進め、「建設的で安定した関係」を築くという方向性で一致しました。
特に、6年ぶりに開かれた「日中ハイレベル経済対話」では、省エネルギーや二酸化炭素排出削減などの分野での協力が確認されました。
しかし同時に、岩屋外相は尖閣諸島の周りでの中国船の侵入、日本の水産物に対する輸入制限、中国当局に拘束されている日本人の問題など、様々な問題点について抗議し、早く解決するよう求めました。
また、台湾海峡の平和と安定が重要であることも強調しました。
これらの問題に対して中国側から積極的な返答はなかったとされていますが、日本の水産物の輸入再開に向けた話し合いが進展したことは、一定の成果と言えるでしょう。
日韓関係:協力の深化
日韓の外相による個別会談では、岩屋外相と趙兌烈外相が「日韓関係の良い流れをこれからも維持し、さらに発展させていこう」と確認しました。
また、「日本・韓国・アメリカの連携をさらに強めていくことが日韓双方にとっての戦略的な利益である」という認識でも一致しました。
また、岩屋外相は拉致問題について韓国政府が一貫して支持してくれていることに感謝の意を表し、引き続きの協力をお願いしました。
趙外相はこれに応え、拉致問題解決に向けた協力を約束したと見られます。
日韓関係は過去の歴史問題などで時に緊張することがありますが、北朝鮮問題や経済協力など、共通の課題に対して協力関係を深めることの重要性が再確認されています。
文化外交の新次元:2025-2026年日中韓文化交流年
2025年3月22日の日中韓外相会談で合意された「日中韓文化交流年」は、単なる文化イベントの開催を超えた、三国間の相互理解を深める重要な取り組みとなります。
この文化交流年は、2024年5月のソウルでの首脳会談で基本方針が確認され、今回の外相会談で具体的なプロジェクトが明らかになりました。
共同歴史教科書編纂プロジェクト
日中韓三国の歴史認識の違いは長年にわたり関係改善の障壁となってきました。
この状況を打開するため、三国の歴史学者が協力して共通の歴史教材を作成する取り組みが進められています。
このプロジェクトは2004年に始まった民間レベルの取り組みが基盤となっており、当時中国社会科学院近代史研究所の呼びかけで『未来をひらく歴史』が出版されました。
しかし、この初期の取り組みは各国の政治的立場が反映され、特に中国共産党史観が強く表れているとの批判がありまます。
今回の共同歴史教科書編纂は、こうした過去の経験を踏まえ、より学術的で政治的中立性を保った内容を目指しています。
日本からは成均館大学校東アジア学術院客員研究員の上山由里香氏など、2011年から日中韓3国共同歴史編纂委員会に参加してきた専門家が中心となり、三国の若い世代に向けた新たな歴史教材の開発が進められています。
若手官僚交換プログラム「東アジア未来塾」
三国間の相互理解を深めるためには、将来の政策決定に関わる若手官僚の交流が不可欠です。
「東アジア未来塾」は、2010年に実施された「日中韓次世代リーダーフォーラム」の経験を発展させたプログラムです。
このプログラムでは、三国の外務省、経済産業省、文化省などの若手官僚が3か月間、相互の国の省庁で研修を受けます。
参加者は「市民社会」「低炭素経済発展」「安全保障」などのテーマについて共同研究を行い、政策提言をまとめます。
国際交流基金の報告によれば、過去のプログラムでは「信頼感の醸成と長期的なネットワークの構築」が重視され、参加者同士の絆が形成されました。
今回のプログラムでは、デジタル技術を活用したオンライン研修も併用し、より多くの若手官僚が参加できる仕組みが整えられています。
伝統医療のデジタルアーカイブ化
日中韓三国は、それぞれ独自の伝統医療を発展させてきましたが、その根源は共通しており、長い歴史の中で相互に影響を与え合ってきました。
「伝統医療のデジタルアーカイブ化」プロジェクトは、こうした共通の文化遺産をデジタル技術で保存・共有する取り組みです。
日本への韓国伝統医学の伝来は6世紀に始まり、10世紀の日本医書には韓医籍最古の書名が引用されています。
また、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際には多量の李朝版医書と出版技術が日本に伝わりました。
中国の伝統医学も含め、三国の伝統医療は「漢字という通用文字により、容易に国境や海峡を越えていた」という歴史があります。
このプロジェクトでは、各国に散在する貴重な伝統医療文献をデジタル化し、三言語(日本語・中国語・韓国語)で閲覧できるオンラインアーカイブを構築します。
これにより、失われつつある伝統知識の保存だけでなく、現代医療への応用研究も促進されることが期待されています。
首脳会談実現への地政学的条件
日中韓外相会談で合意された首脳会談の早期開催は、三国関係の改善を象徴する重要なステップですが、その実現には複数の地政学的条件が関わっています。
開催への障壁と進展状況
首脳会談実現の鍵となる要素として、米中関係の改善、日韓の世論好感度、中国公船による領海侵犯の減少などが挙げられます。
現時点でのこれらの達成度は必ずしも高くなく、特に中国公船による尖閣諸島周辺での領海侵入は依然として大きな問題となっています。
2012年9月の尖閣諸島国有化以降、中国公船による領海侵入は急増し、2013年には年間72隻に達しました。
その後も侵入は続いており、日中関係の改善を妨げる要因となっています。
日中相互認識の厳しい現実
日中関係については、お互いの国民感情が非常に厳しい状況にあります。
言論NPOと中国国際伝播集団による第20回日中共同世論調査によると、中国国民の日本への好感度が2023年から2024年にかけて大きく低下し、日本に「良い印象を持っている」中国人は37.0%から12.3%に激減。
同時に日中関係が重要だと考える中国国民の割合も60.1%から26.3%に落ち込んでいます。
一方、日本側の数字も厳しく、中国に「良くない印象」を持つ日本人は89.0%に達しており、笹川平和財団の調査では中国に「親しみを感じない」日本人が73.1%と前年より増加しています。
さらに「中国との付き合いは最低限にしておく必要がある」と考える日本人も43.8%に上昇しました6。
SNS上では「なぜ中国側の数字ばかり気にするのか」という声が多く、「日中友好は日本だけの幻想だ」「日本側だけが関係改善を求めている」との批判が見られます。
あるXユーザーは「中国は日本の世論操作を試みている。日本の対中政策を考える上で重視すべきは日本国民の意思であり、非民主的な中国の世論を過度に気にする必要はない」と投稿し、多くの共感を集めています。
これらの調査結果は、過去20年間で最も厳しい相互認識を示しており、両国の民間レベルでの関係改善が必要かもしれませんが、その前提として互いの国民感情の現実を直視する必要があります。
首脳会談実現のシナリオ
こうした状況を踏まえ、首脳会談実現には複数のシナリオが考えられます。
最も早い場合、2025年10月に大阪で開催予定のG20首脳会議に合わせて日中韓首脳会談を開催するシナリオがあります。
これは日本がG20議長国となる機会を活用するもので、国際的な注目度も高まることから、三国にとって望ましい選択肢です。
一方、政治日程との兼ね合いから、2026年に延期される可能性もあります。
特に中国の国内政治情勢や日本の政権交代の可能性などが影響する可能性があります。
最も懸念されるのは、台湾海峡での緊張が高まった場合の中止リスクです。
台湾有事が発生した場合、日中関係は急速に悪化し、首脳会談の開催は困難になると予想されます。
日米韓連携との関係
日中韓首脳会談の実現に向けては、日米韓の連携も重要な要素となっています。
スナイダー氏は、「良好な日韓関係がアメリカの国益にとっても極めて重要」と述べています。
北朝鮮問題への対応が三国間協力の重要理由となるからです。
一方で、米中対立が深まる中、日中韓協力を進めることは、アメリカの「中国囲い込み」政策とのバランスを取る必要があります。
日本と韓国は、中国との経済協力を進めつつも、安全保障面では米国との同盟関係を維持するという難しい立場に置かれています。
岩屋外相は外相会談で「力による一方的な現状変更は認められない」と強調し、ウクライナ情勢や台湾問題に対する日本の立場を明確にしています。
こうした発言は、中国との協力を進めつつも、国際秩序に関する基本的価値観を譲らない日本の姿勢を示すものです。
水面下の交渉戦術と未来への展望
会議の舞台裏:飯倉公館での駆け引き
日中韓外相会談が行われた飯倉公館は、日本外交の重要な舞台として知られています。
この歴史ある建物での会談には、表に出ない様々な工夫がありました。
まず注目すべきは会場の設定です。
三カ国の外相が同じ高さの椅子に座り、円形のテーブルを囲むという配置が選ばれました。
これは「対等な立場での対話」を視覚的に表現するための工夫です。
過去の会談では、主催国が中央に座るなど微妙な力関係が表れることもありましたが、今回は完全な対等性が強調されました。
また、通訳者の役割も重要でした。特に王毅外相が言及した「四つの政治文書」(日中共同声明、日中平和友好条約、日中共同宣言、日中共同声明)の解釈には、微妙なニュアンスの違いがあります。
通訳者は単に言葉を訳すだけでなく、こうした外交文書の背景にある意図を正確に伝える役割を担っていました。
会談後の夕食会のメニューにも外交的なメッセージが込められていました。
和食の基本である「出汁」の文化と中国の「火鍋」、韓国の「コムタン」など、スープ文化の共通点を強調したメニューが選ばれたのです。
これは「異なる味を持ちながらも、共通の食文化を持つ」という三国関係の象徴として解釈できます。
若者の反応
若者の交流に関しては、いくつかの事実が確認できます。
日中韓ユース・フォーラム(JCK)という取り組みが2010年から始まっており、三国の若者が模擬国連やシンポジウム、文化交流などを通じて相互理解を深めています。
また、日本国際交流センター(JCIE)が主導する「日中韓の絆再発見プロジェクト」では、2014年から2017年にかけて、三国の文化的共通点や新しい共有文化、共通の課題などをテーマにしたセミナーが開催されました。
これらの取り組みは、若い世代を中心とした三国間の交流や相互理解の促進を目指しています。
三国の若者の交流に関しては、中国のGlobal Timesの記事で「三国の若者が同じアイドルを追い、同じ映画やドラマを見て、同じゲームをプレイし、似たような食の好みを持っている」という指摘がありました。
これは文化交流を通じた相互理解の深まりを示唆していますが、具体的な政策提言などには言及されていません。
未来への3つの鍵
日中韓外相会談の成果を踏まえ、今後の三国協力を成功させるための鍵となる要素が見えてきました。
1. 透明性の確保
技術協力や経済交流を進める上で、透明性の確保は不可欠です。
特に技術移転の際には、軍事転用の防止や知的財産保護が重要な課題となります。
この問題に対処するため、第三国の専門家による監査機関の設置が提案されています。
例えば、EUの専門家チームが日中韓の技術協力プロジェクトを定期的に評価し、透明性を確保する仕組みです。
これにより、相互不信を減らし、健全な協力関係を築くことができるでしょう。
2. 危機管理の仕組み
尖閣諸島周辺での中国公船の活動など、偶発的な衝突のリスクが高まる中、危機管理の仕組みづくりは急務です。
具体的には、三国間のホットライン(緊急連絡網)の強化や、領海侵犯が発生した際の即時通報システムの構築が考えられます。
こうした仕組みは、小さな衝突が大きな対立に発展するのを防ぐ「安全弁」として機能するでしょう。
3. 市民参加の促進
政府間の協力だけでなく、市民レベルでの交流も重要です。
特に若い世代の参加は、長期的な関係構築に不可欠な要素です。
SNSを活用した三国間の市民対話や、学生交流プログラムの拡充など、様々な取り組みが考えられます。
また、ブロックチェーン技術を活用した「市民参加型政策評価システム」も注目されています。
これは、三国の政策合意の進捗状況を市民が監視・評価できる仕組みで、政府の説明責任を高める効果が期待されています。
まとめ:揺れる世界の中での日中韓協力の意義
国際秩序が大きく変化する中、日中韓三国の協力関係は新たな段階に入ろうとしています。
今回の外相会談は、様々な課題を抱えながらも、三国が「未来志向の協力」を進める意思を確認した重要な機会となりました。
特に注目すべきは、経済協力や文化交流、少子高齢化対策など、三国が共通して直面する課題への協力姿勢が示されたことです。
これらの分野では、政治的対立を超えた実務的な協力が可能であり、具体的な成果が期待できます。
一方で、北朝鮮問題や尖閣諸島問題など、安全保障に関わる課題では三国の立場の違いが明らかになりました。
これらの問題は簡単に解決できるものではありませんが、対話を続けることで相互理解を深め、少しずつ溝を埋めていく…。
岩屋外相が会談で述べたように、「対話と協力によって分裂と対立を乗り越える」という姿勢が、未来のアジアを切り開く鍵となるでしょう。
三国の協力関係が深まれば、それはアジア全体の安定と繁栄につながります。
今後、首脳会談の実現に向けた動きが加速する中、私たち市民も三国間の相互理解を深める取り組みに参加していく必要があるでしょう。
文化交流や学術交流、観光など、様々な形での交流を通じて、国境を越えた関係をしっかりと見据えていきましょう。
揺れる世界の中で、日中韓三国が協力して未来のアジアを切り開く国の姿を、これからも注目していきたいと思います。