こんにちは、なおじです。
現役の先生方、富山の堀川小学校って知ってますか?
そこで、こんな授業を観ました。
「私は、おじさんに、ギターのピックケースをつくってプレゼントしたいです」
富山の堀川小学校、5年生の家庭科の授業で、5分間の沈黙の後に女の子が発した一言です。
この一言が、クラス全体の空気を一変させました。
なぜでしょうか。
教師が「ある子の思い」を授業に位置付けたからです。
これこそが、楽しく明るい学校をつくる核心なのです。
【このブログを読んでわかること】
- 学級経営の土台となる「安心感」の育て方
- 総合的な学習で「課題」を「問題」に転換する方法
- 子どもの自己有用感を高める具体的実践
- 「褒め言葉のシャワー」という画期的な手法

教育の土台は「安心感」にある
学校における教育の土台として、最も大切なのは何でしょうか。
それは、人への安心感です。
教室で自由にものが言える雰囲気があること。
友達や先生に対する安心感が成立していることが、教育の土台となります。
受容的な雰囲気の中にこそ、楽しく明るい学校が実現できるのです。
「課題」を「問題」に転換する教師の技
総合的な学習の時間で、どのように課題をもたせればよいのでしょうか。
課題を教師が課した「題」ととらえるならば、課題が課題のままでは、児童の興味・関心は深まりません。
教師が体験的活動を仕組むなどして、子どもにとっての「切実な問題意識」を育てなければならないのです。
切実な問題意識を育てるためのポイントは、次の3つです。
- 話合い活動を適切に位置付け、問題意識を全員で共有できるようにする
- 協力して体験できる場を設定する
- 自尊感情を刺激する
授業の中に育てたい子を位置付ける
総合的な学習では、教師が育てたい子を授業の中に位置付ける、という高等テクニックがあります。
ある子を授業の中に位置付けるためには、その子の特性を教師が事前につかんでおく必要があります。
その子が普段取り組んでいること、興味を持っていること、疑問に思っていることなどです。
富山の堀川小学校、5年生の「プレゼントを作ろう」という家庭科の授業を参観したときのことです。
教師が「誰にどんなプレゼントを作りたいですか」と発問しました。
長い沈黙、おそらく5分程度の大沈黙の後、ある女の子が発表しました。
「私は、おじさんに、ギターのピックケースをつくってプレゼントしたいです」
「どうして、おじさんにピックケースをプレゼントしたいの」と、ある子がつぶやきます。
教師はすかさずその子のつぶやきを全体へと位置付けました。
「○○さん、▲▲さんが『どうして』って、聞いてるよ」
その女の子が、ボソボソと話し始めます。
「私は、おじさんが小さい頃から大好きなの。小さい頃はよくケーキとか買ってくれたり、一緒に遊びに連れて行ってくれたのね。でも、一番好きなのは、おじさんがギターを弾いて一緒に歌ってくれたことなの。おじさんはギタリストっていう仕事をしていて、とてもギターが上手なの」
「へー」とか、「すごい」とかの周りの声が聞こえます。
「でも、おじさんは今病気なの。もう半年も入院しています」
(エっという声。そしてざわつき)
「私は、おじさんに早く良くなってほしい。でも頑張ってって、なかなか言えない」
「だから私は、ピックケースをつくっておじさんにプレゼントしたいの」
この子のこの発言を聞いた後、クラスの子らはこの子の発言に触発された自分の思いを語っていきました。
『きっとみんないいプレゼントを作ることができるだろうな』
おそらく参観した者すべてがそう感じたことでしょう。
「その子のその思い」を、授業に位置付けた教師の見事さ。
単なる「プレゼントを作ろう」という家庭科のよくある課題では、子供の本気を触発できません。
ある子の思いを授業に位置づけたことで、教師の単なる課題が、児童にとって切実な問題意識に裏付けられた「問題」に変化したのです。
教師から子供に「課する題」を、子どもの思いを位置付けることで、一人一人が「自分のこと」と捉えられる「問題」とする教師のテクニック。
暫くその場を動けませんでした。
「褒め言葉のシャワー」という実践
ある学校のあるクラスにお邪魔しました。小学校5年生、全員で30名弱のクラスでした。
そのクラスには普段皆から「いじめっ子」と呼ばれているA君がいました。
帰りの会の時間です。
先生が、「今日のシャワーはA君です。では、○○君からおねがいします」と言いました。
すると、子どもたちは、A君の今日一日の生活の中で「いいな」と思った点をポンポンポンポンと、短い言葉でA君の方を向いて語りかけていきます。まるで褒め言葉のシャワーです。
皆の言葉が終わったときに、A君を見ると目に涙をためていました。
子どもの安心感・自己有用感を育てる本当に良い実践だと思いました。
安心感を育むための仕掛け
先生は、自分のクラスの子どもたちが、日々の学校生活の中で、お互いを認め合える時間をどのように設定していますか。
学級経営の土台は、教師と子どもの信頼関係です。信頼があるからこそ、子どもたちは安心して授業に臨み、先生の指導にも耳を傾けます。
具体的な方法としては、次のようなものがあります。
- 毎日のあいさつを丁寧にする(目を見て名前を呼ぶ)
- 子どもの話を最後まで聞く
- 小さな努力を褒める(成果よりもプロセスを認める)
- 互いに認め合える雰囲気をつくる
もし、まだ何もしていないのなら、そういう実践をしている教師がいる。自分も何か出来ないかと、「意識する」ことから初めてみませんか。
まとめ:楽しい明るい学校づくりQ&A
Q1:学級経営の土台となる「安心感」とは何ですか?
A:教室で自由にものが言える雰囲気があり、友達や先生に対する信頼関係が成立していることです。受容的な雰囲気の中にこそ、楽しく明るい学校が実現できます。
Q2:総合的な学習で「課題」を「問題」に転換する方法は?
A:教師が課した題のままでは興味・関心は深まりません。子どもの切実な思いを授業に位置付けることで、一人一人が「自分のこと」と捉えられる「問題」に転換できます。
Q3:「褒め言葉のシャワー」とは何ですか?
A:帰りの会で、特定の子の今日一日の生活の中で「いいな」と思った点を、クラス全員が短い言葉で次々に語りかける実践などを指します。子どもの安心感・自己有用感を育てる効果があります。
Q4:授業の中に育てたい子を位置付けるとは?
A:その子の特性(普段取り組んでいること、興味、疑問)を教師が事前につかみ、その子の思いを授業に位置付けることです。その結果、その子だけでなく、その子を取り巻く子らが成長します。
Q5:先生は自分のクラスでどんな手立てをすべきですか?
A:毎日のあいさつを丁寧にする、子どもの話を最後まで聞く、小さな努力を褒める、互いに認め合える雰囲気をつくるなどです。まだ何もしていないなら、「意識する」ことから始めましょう。
楽しい、明るい、美しい学校づくりは、一朝一夕にはできません。しかし、「安心感」という土台を丁寧に育てることで、必ず実現できます。子どもたちが「自分は大切にされている」と実感できる学級を、一緒につくっていきましょう。
【この話は、なおじが指導主事時代にある学校の先生方への話をリメイクしたものです。】
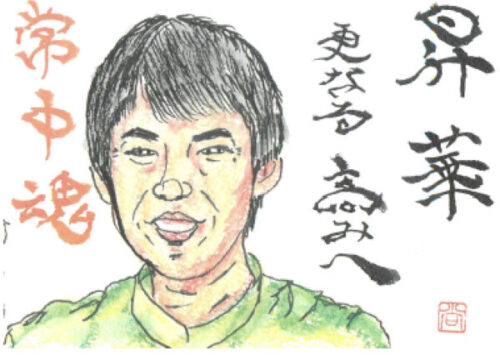
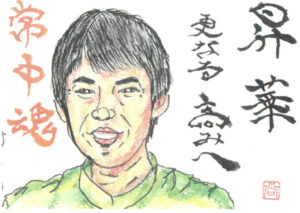
コメント