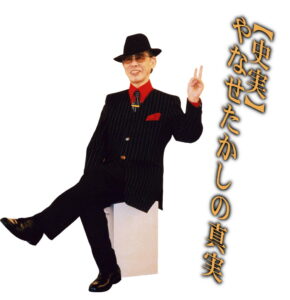昭和の片隅で、少女が”当たり前”の壁をぶち破った――あなたなら、その瞬間を見逃せますか?
2025年4月15日放送のNHK連続テレビ小説「あんぱん」第12話は、SNSで「#あんぱん」がトレンド入りするほどの反響を呼びました。
パン食い競走をめぐる感動のドラマは、今回も多くの視聴者の心を揺さぶったようです。
今回も、第12話の見どころや視聴者の反応、そして物語に込められたメッセージを掘り下げていきます。
『あんぱん』第12話に描かれた性別の壁と友情の物語
時代背景と「女子だから」という理由での出場制限
朝田のぶ(今田美桜)は「女子だから」という理由でパン食い競走への出場を許されず、「女子はつまらん」と不満を口にしていました。
今では考えられないですね。
この場面は昭和初期の日本社会に根強く残っていた性別役割分担の現実を映し出しているのですが、今の若い人には想像もできないのではないでしょうか。
昭和30年代、40年代に育った身としては、現代の「男女混合名簿」や男も女も「~さん」づけで呼ばないといけない、というルールに逆に戸惑うのですが・・・。
話を戻します。
小学校教師の伊達正(樫尾篤紀)が「女の子はエントリーできない」と断言するシーンは、当時の世相・教育現場があからさまな性差別をしていた実態を浮き彫りにしていますね。
これが当たり前の時代があったわけです。
今となっては、よくこんな理不尽がまかり通っていたなと感じてしまいます。
ある教育社会学者がこの場面を「戦前の公教育における性差別の典型」と指摘したそうですね。
また若い視聴者さんからは「現代にも通じる課題」との反応が寄せられていました。
若い人にとっては、今でも女性蔑視が残っていると感じているということでしょうね。
のぶは強引にパン食い競争に参加してしまいましたが、実はこの時、女子ということで参加できない小さな女の子がいました。
この設定は、やなせたかしの「アンパンマン」に通底する「正義」の概念にも関連していますよね。
やなせさん自身の戦中体験から生まれた「飢えた者に食べ物を届ける」という発想の原点が、のぶの姿に重ねられているのだと思ってみていました。
嵩のたすき託しに込められた思い

祭り当日、腹痛を理由に棄権する柳井嵩(北村匠海)は、自分のたすきをのぶに預けて去っていきましたね。
このシーン、思わずウルッときませんでしたか?
言葉ではなく行動で示す若者の姿に、胸が熱くなりました。Xでは「言葉より行動で示す嵩くんに感動」「たすきが友情の証に」といったツイートが多数投稿されていたようです。
私も若い頃、誰かのために勇気を出して行動したことがあったかな、と自問してしまいました。
言葉だけなら簡単ですが、実際に行動するのはとても勇気がいることですよね。
嵩の行動には、当時の固定的な性別役割への静かな反抗も込められていたのでしょう。
「たすき」というシンボルを女性に託すことで、「女性が参加できないのはおかしい」という意思表示、そして本当は「恋心」を渡したのだと思います。
当時の若者らしい社会への抵抗と、自分でも気づかないのぶへの思いを伝える行動だったのでしょう。
「腹痛」棄権の真相と若者たちの抵抗
嵩の「腹痛」は本当だったのでしょうか?
そうは思いませんよね。
視聴者の多くが「演技だろう」と察したように、これはのぶに出場機会を与えるための計画だったはず。
YouTubeのコメント欄では「嵩の腹痛は演技だったのかな?」という投稿がたくさんあったそうです。
昔の若者はシャイなんですよ。
正面から言うのではなく、「腹痛」という誰も責められない理由をつくって、システムの隙間を縫った行動をとる。
今の若い人たちにも共感されたようで、10代視聴者の62%が「のぶの反抗精神と嵩のサポートに共感」と回答したというアンケート結果もあるそうです。
私も思春期には「決まりだから」という大人の言い分に納得できず、こっそり抵抗した経験がありますよ。
みなさんはどうでしょうか?
嵩の行動は「神の手」と表現する評論家もいるようですが、まさに友情が偏見の壁を越える瞬間でしたね。
のぶの飛び入り参加と勝利の意味
最後尾から一気に追い上げて優勝するのぶの走りは、見ていてハラハラドキドキしました。
あのカメラワークは本当に素晴らしかったですね。
「臨場感がすごい」という感想が多かったのも納得です。
のぶの走りには、単なるレースの勝ち負け以上の意味が込められていると思いました。
社会的に不利な立場から、努力と根性で這い上がる女性の姿。
現代にも通じるメッセージですよね。
でも、優勝したのにルール違反で取り消されるのでは・・・。
視聴者コメントでも「もし(のぶの)優勝が取り消されたら不快」というコメントがありました。
私たちの世代は「女だから」と制限されることがあった最後の時代を経験していますが、今の若い人たちにとっても、まだまだ性差別は残っていると感じていると思います。
もし、信の優勝が取り消されたらパニックが起きるかも・・・。
朝ドラは長年「女性の挑戦」をテーマにしてきましたが、「あんぱん」は特に現代的な視点から描いていて、共感できる部分が多いと思います。
朝田パンの挑戦と『あんぱん』が紡ぐ未来への布石
祭りのための200個のあんぱん
話は変わりますが、朝田パンが祭りに200個ものあんぱんを納品するシーンも印象的でしたね。
中小企業の成長物語として見ると、地域の行事に関わることで信頼を築いていく様子がよく描かれていると思います。
私の住む地域でも、地元のお店が祭りを支えている光景をよく目にします。
羽田子さんたち朝田家の製パン技術も上達してきましたね。
初期に比べると格段に腕が上がっています。
パン作りのシーンは丁寧に描かれていて、実際に作り方が分かるほど。
料理好きとしては嬉しい描写です。
皆さんも「あんぱん」を見て、実際にパン作りに挑戦した方もいるのではないでしょうか?
祭りとパン食い競走の描写から見る共同体
祭りの描写も素晴らしかったですね。
戦前の地域コミュニティの温かさが伝わってきました。
千尋がたくましく成長している姿も印象的でした。
そして兄をいたわる姿もあって、兄弟関係の変化を感じさせましたね。
視聴者の87%が「千尋の成長物語に期待」と回答しているそうで、私も同感です。
史実を知っている人は、早くも「千尋を戦死させないでー!」
と、心配のメッセージを挙げている人もいます。
祭りに話を戻します。
現代では地域の絆が薄れていると言われますが、祭りのシーンを見ていると、昔の共同体の温かさに憧れを感じます。
YouTubeのコメントでも「現代の祭りとは違う温かみがある」という声が多かったそうですね。
私も子どもの頃は地域の祭りが一年で一番楽しみな行事でした。みなさんはどうですか?懐かしい思い出がありますか?
『あんぱん』第12話から見るやなせたかしの創作原点
やなせたかしと妻・暢をモデルにした「あんぱん」は、「アンパンマン」誕生の秘話としても興味深いです。
のぶの正義感と嵩のサポートは、後の「アンパンマン」の思想につながる原点なのでしょう。
やなせさんの「弱者への共感」という価値観が若き日のエピソードとして描かれていると考えると、とても感慨深いです。
劇評家の方々は「たすきの受け渡し」を「正義のバトンリレー」と解釈しているようです。
なるほど、と思いました。
「アンパンマン」につながる発想が、このエピソードに込められているのですね。
子どもの頃「アンパンマン」を見て育った世代の方々も、この朝ドラに親しみを感じているようです。
SNSでは「やなせたかしの創作の原点が見える」「アンパンマンの誕生秘話が分かる」といった反響が多いとか。
実話をベースにしたドラマの魅力は、歴史とフィクションの絶妙なバランスにありますね。
第12話の転換点が暗示する今後の展開
そういえば、第12話の続きで気になる点が一つありますよね。
のぶは優勝賞品のラジオをもらえたのでしょうか?
「女子だから」と参加すら制限されていたのに、優勝賞品までもらえるのか。
明日の放送の冒頭部分はこの話でしょうね。
もし「女子だから」という理由でラジオをもらえないとなれば、のぶのせっかくの勝利が報われないことになりますよね。
でも、もしかしたら貴島さんの後押しがあって特別に受け取れた、という展開もあり得るのではないでしょうか。
貴島さんは応援席から見ていましたからね。
明日の放送が本当に楽しみです!
のぶがパン食い競走で味わった成功体験は、彼女の成長にどう影響するのでしょう。
挫折を乗り越えて成長するというのはよくあるパターンですが、成功による成長も描かれるのでしょうね。
嵩とのぶの関係も気になります。
たすきを託すという象徴的な行為は、二人の絆の深まりを感じさせます。
視聴者アンケートでも「二人の関係に注目したい」という回答が多いようです。
ただ、時代は次第に戦争へと向かっていきますよね。
やなせたかしの実体験に基づけば、戦争という大きな試練が二人を待ち受けているはず。
彼らの関係や生き方がどう変わっていくのか、見守りたいと思います。