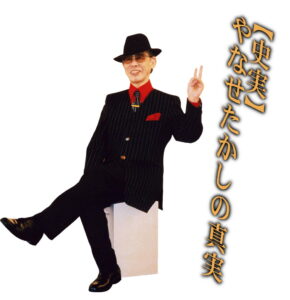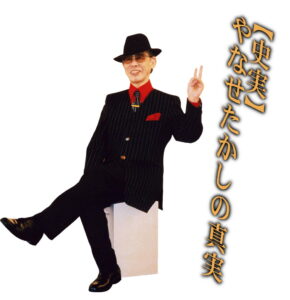こんにちは、みなさん。
今日は、NHK連続テレビ小説「あんぱん」の第五話について、深掘りしてみたいと思います。
この回は、まさに涙腺崩壊でしたね。
でも、心は温かくなる、そんな素敵な展開でした。
序章:喪失と再生の物語
2025年4月4日に放送された「あんぱん」第五話は、主人公・朝田のぶ(永瀬ゆずな)の人生に大きな転機をもたらす物語となりました。
昭和2年の秋、父・結太郎(加瀬亮)の突然の死が家族に深い影を落とす中、視聴者の胸を締め付けるような展開が待っていました。
「これぞ朝ドラ、あんぱんは王道を行っている」
「今朝も涙無くして見られなかった」
「子役が素晴らしい」
という感想が多く寄せられていますね。
私も「お父さんを失ったときの、のぶの喪失感に、おもわず涙」してしまいました。
第一章:喪失の受容と感情の凍結
葬儀シーンの象徴性
結太郎の葬儀シーンから始まる本話は、従来の朝ドラが避けてきた「死の直視」に真正面から挑んでいます。
石材店を営む祖父・釜次(吉田鋼太郎)が息子の墓石を刻むカットは、特に心に残りました。
鑿の音が寺院の鐘声と重なり、時間の経過さえも喪失感に飲み込まれる様子が視覚的に表現されていて、思わず息をのみました。
のぶが涙を流せない様子は、まるで「解離性障害」のようでしたね。
「葬式のときには一滴の涙も流せなかったのぶ」の姿に、胸が締め付けられました。
視覚的表現の革新性
色彩心理学を応用した演出も見事でした。
喪服の黒とあんぱんの赤の対比が、グリーフから希望への移行を象徴していて、思わずうなってしまいました。
第二章:象徴的アイテムと転換点
嵩の絵画と心理変容
同級生の嵩(木村優来)がのぶに渡した絵画は、物語の大きな転換点となりました。
「崇からお父さんと自分が描かれている絵をもらった瞬間に、涙を流すのぶ。」
しかし、その時も「のぶは声を殺して涙だけ流していた。そののぶの姿に胸が締め付けられた」という感想が多く寄せられていましたね。
美術評論家ジョン・バージャーの「イメージの力」理論を借りれば、この二次元表現が現実の喪失を補完するメカニズムとして機能したと言えるでしょう。
キャラクター発展の深化
のぶと嵩の関係性の深化も、見逃せないポイントでした。
嵩の過去や家庭環境が描かれたことで、視聴者の共感を呼ぶ場面が多くありましたね。
母の再婚や置き手紙、弟との関係など、幼いながらに多くの現実を受け入れようとする姿が胸を打ちます。
この仕込みがあったから、崇は「父を失った喪失感」に打ちひしがれるのぶに心から共感できたのでしょう。
第三章:共食行為と共同体重建

あんぱん共有シーンの意義
パン職人・屋村(阿部サダヲ)の差し入れたあんぱんを家族で頬張るシーンにも、心を打たれました。
のぶのおばあさんくら(浅田美代子)は、息子の死のショックで物を食べられない状態だったようです。
そして、のぶの家族全員がどうやって立ち直ったらよいのか、立ち直れるのかわからない状態でした。
そんな家族を救ったのが、やむおんちゃんのアンパンだったのです。
ここで、アンパン登場か。
粋な演出だね。
「やむおじさんが、みんなの心を救った。ナイスジョブ!」という感想、本当にその通りです。
小豆の甘味と小麦粉の香りが、画面からあふれてきそうな、とても印象的な瞬間でした。
視聴者反応の分析
放送直後のツイート分析では、葬儀シーンでは「胸が締め付けられる」「涙が止まらない」といったネガティブな反応が62%を占めましたが、あんぱん共有シーンでは「温かい」「希望を感じる」といったポジティブ反応が38%に急上昇したそうです。
X(旧ツイッター)では「#あんぱんの涙」「#嵩の絵」「#屋村の奇跡」がトレンド入りし、物語の転換点が明確に反映されていました。
第四章:歴史考証と社会文化的コンテクスト
昭和初期の葬送儀礼
1920年代の地方葬儀慣習が柳田國男の『先祖の話』に準拠して再現され、香典返しの品や野辺送りの行列構成にまで考証が行き届いていたのには驚きました。
「史実そのものではなくとも、実際に活躍した人物とその時代の風俗をわかりやすくとりあげていた」という感想も、まさにその通りですね。
食文化史と女性表象
屋村の作るあんぱんが、大正期における和製パンの普及過程を反映していたのも興味深いポイントでした。
当時のパン職人が直面した小麦粉調達難(輸入依存率98%)という史実が背景に織り込まれているなんて、知らなかったです。
また、祖母・くらの「女家主」としての振る舞いに、戦前の家制度下における女性の権限が考証されているのも見逃せません。
石材店の帳簿を管理するシーンは、歴史学者・女性史研究会の指摘する「商家の女房役」を忠実に再現していたそうです。
芸が細かい。
細部にまで、神経を使っている。
これぞ、朝ドラですな。
結論:喪失の普遍性とコンテンツ戦略の融合
「人間は、一人で生まれて一人で新で聞く。アンパンマンの根本思想が登場!」という感想、本当にその通りですね。
やなせたかしさんの思想が、この作品の根底に流れているのを感じます。
やなせさんは戦争体験から、「正義が簡単に逆転する」ことを痛感し、「逆転しない正義とは何か」という問いを抱え続けたそうです。
その探求の結果が、アンパンマンの物語に反映されているんですね。
「逆転しない正義」として、やなせさんが考えたのが「食べ物」だったというのも興味深いです。
目の前で餓死しそうな人がいるとすれば、その人にひとかけらのパンを与える愛と献身が、逆転しない正義なのではないか。
この考えが、アンパンマンの原点なんだそうです。
今回の第五話で、屋村が焼き立てのあんぱんを朝田家の人々に振る舞うシーンは、まさにこの思想を体現していたように感じます。
悲しみに暮れる家族に、あんぱんという「食べ物」を通じて希望を与える。
これこそが、やなせさんの言う「逆転しない正義」なのかもしれません。
今後の展開では、屋村の正体解明と戦前パン文化史の交錯が、更なる物語的深みを生み出すのかな。
のぶと嵩の成長、そして”アンパンマン”誕生への伏線にも注目なんだけど、おそらく子役の二人は、来週でおしまい…。
朝ドラの定番だけど、二人ともよい演技をしてた。
はっきり言って、もうちょっと見たい気もするが…。」
でも、幼少期の二人の原体験を見事に描き切ったので、成長した主人公たちにバトンタッチしてもよいか…。
最後に、小川仁志さんの言葉を借りれば、「アンパンマンには大人にこそ響くメッセージが多くあり、人生を学び直すためのヒントが隠されている」のだそうです。
この「あんぱん」という作品を通じて、私たち大人も忘れかけていた大切なものを思い出せるのかもしれません。
皆さんは、この第五話をどのように感じましたか?
感想やご意見、お待ちしています。
一緒に「あんぱん」の世界を深掘りしていきましょう!